
|
 |
 |
 |
出雲王家の谷で発掘された
埋葬品を元に復元された出雲で
活躍した聖徳太子の皇子「日置王」の
復元姿「出雲弥生の森博物館」
|
出雲市西谷王家の谷の四隅突出墳丘墓 |
埋葬品を元に復元された王の葬儀 |
| 上の写真はいずれも出雲市弥生の森公園と博物館にて |
 |
|
古代出雲王朝は紀元前5世紀に初代大名持(主王)菅の八耳で始まった。
紀元前3世紀末に秦国人徐福(記紀ではスサノオ)の渡来で主王八千矛(記紀では大国主)と副王事代主が徐福手下の穂日らに幽閉殺害されたが、その後も王朝は続いた。王の皇子たちの中には大和、越、諏訪へ移住しそれぞれ王国を築いた。
3世紀終わりに、徐福子孫の九州物部王国の第2次東征に参加した朝鮮渡来人ヒボコの子孫但馬の守の急襲で第17代山崎帯(たらし)王で出雲王朝は終わる。しかしその後も出雲や大和の王家とその分家は、海部、磯城、物部、平群の王朝を支え大和朝廷の成立に多大な影響を与え続ける。しかし、持統が命じて不比等が編纂させた記紀では 出雲王朝は抹殺されるのである。
島根県東部、松江市や出雲市周辺には古代出雲王朝の史跡が沢山あり、また八千矛や事代主の息子たちが移住した関西地方や諏訪地方にも 古代出雲王朝にちなんだ場所、神社がたくさんある。それらを訪ねて行こう。
※古代出雲王朝は主王(役職名は大名持ー記紀では意図的に大己貴と変えられた)と副王(役職名は少彦ー記紀では意図的に少彦名と変えられた)の二人の王で統治された。西出雲王家(神戸臣家)と東出雲王家(向家)から交互に主、副の王を出したとされる。
|
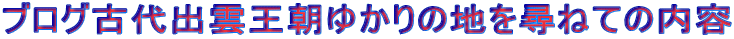
|
記事番号をクリックすると直接そのページへいけます↓
|
記事番号が細字のものはグーブログが突然休止したため 現在修復中です。
|
|
備考 |
記事番号 |
| 84奈良県御杖村に行った時に、偶然見つけて参拝した「御杖神社」のパンフレットをよく見たら なんと古代出雲王朝の国教である 「幸の神三神」をそのまま主祭神にしていることが分かり、びっくりしました。全国の神社を参拝し続けていますが 幸の神三神をそのまま主祭神にしているのをはじめてみました。 |
2025年8月5日 |
84
blog 8 |
| 83早春の大和三山トレッキングをしたときに、奈良県橿原市の畝傍山周辺には、たくさんの出雲王朝ゆかりの施設があるのが分かりました。そこでこれらの施設をまとめました。神功皇后を祀る畝傍山口神社、それと大和朝廷第一代大王から第四代大王の御陵です。 |
2025年3月6日
5月6日 |
83
blog 8 |
| 82. 京都トレイルを歩いた時に、貴船神社を参拝しましたが その時に見た貴船神社由緒書きがとても面白く感じましたので紹介します。架空の大君神武の東征時の事が書かれていました。 |
2024年10月1日 |
82
blog 8 |
| 81. 「古代出雲ゆかりの地を訪ねて」 今回は甲斐の国河口湖畔の「産屋ヶ崎神社」と 笛吹市の 「一宮浅間神社」を訪ねました。 |
2023年11月20日 |
81
blog 8 |
| 80.下野国一宮(しもつけのくにいちのみや)と呼ばれる日光二荒山神社へ行きました。山旅から帰宅する前です。大国主と奥方、その皇子を主祭神としていますが 奥方の名前を間違えたり建物形式が大社造りとは程遠く裏切られた気持ちで帰宅しました。 |
2022年12月9日
|
80
blog 8 |
| 79. 2022年古代出雲ゆかりの地を尋ねる旅その4は 徐福二度目の和国への上陸地点、佐賀の浮盃(ぶばい)です。 |
2022年4月3日
|
79
blog7 |
| 78. 2022年古代出雲ゆかりの地を尋ねる旅その3は古代史の舞台 伊都国 (福岡県糸島市)です。 |
2022年4月3日 |
78
blog7 |
| 77. 2022年古代出雲ゆかりの地を訪ねる旅その2は宗像大社です。 |
2022年4月3日 |
77
blog7 |
| 76.. 2022年九州旅は各地の古代出雲ゆかりの地を訪ねる旅です。その1は 宇佐神宮です。 |
2022年4月1日 |
76
blog7 |
| 75. 三番目に歴史に登場するヒミコの豊姫が祀られている丹生都比売神社へ行きました。なぜこの神社が「世界文化遺産紀伊山地の霊場と参詣道」に登録されたのか その不思議を考えてみました。 |
2021年11月26日 |
75
blog7 |
| 74. ヒミコのまとめの最後は イクメ大王とヒバス姫皇后の娘で、初代伊勢斎王となられた大和姫です。 |
|
74
blog7 |
| 73. ヒミコのまとめの次は魏書に台与と書かれて、和国駐在武官張政により 親魏和王の宇佐豊玉姫女王の後任に指定された 豊来入姫です。 |
|
73
blog7 |
| 72. ヒミコのまとめの次は 佐保姫です。 |
|
72
blog7 |
| 71. いわゆるヒミコと呼ばれる5人の姫巫女を順にまとめて 次は二番目の宇佐豊玉姫です。この方こそ正真正銘のヒミコです。和国駐在の魏の武官から直接親魏和王の証書と金印を受け取りました。 |
|
71
blog7 |
70. いわゆる ヒミコと呼ばれる5人の姫巫女を順にまとめていきたいと思います。
まずはモモソ姫です。彼女が司祭する春と秋の隊際には各地から大勢の豪族が巻向に集まりました。 |
|
70
blog7 |
| 69-2 ヒミコゆかりの地を訪ねました。奈良市のサホ姫ゆかりの神社と、桜井市大神神社と檜原神社、それに巻向の周辺です。三輪山へは時間の関係で登拝できませんでした。 |
2021年3月20日 |
69-2
blog6 |
| 69-1. 陰険な藤原一族の罠にはめられて失意のうちに亡くなった菅原道真は死後その祟りを恐れた藤原一族や天皇家により、学問の神様にしてた上げられました。彼の生家跡に建てられて 松江藩の手厚い保護を受けた松江市の「菅原天満宮」を訪ねた記録に少し補足説明をしました。 |
2021年2月2日
|
69-1
blog6 |
| 68. 出雲大社の北側島根半島の西端部の日御碕神社を訪ねました。推古女帝の孫、かつ上の宮法王(いわゆる聖徳太子)の皇子の日置王が豊富な財力で造営した日御碕神社は徳川幕府により 跡形もなく作り替えられていましたが 片隅にひっそりと佇む韓国神社や宗像神社にかすかに古代出雲王国の片りんを感じる事が出来て満足でした。 |
2020年9月10日 |
68
blog6 |
| 67. 諏訪湖地方を開拓した出雲族 建御名方(たてみなかた) をはじめ 出雲族と越の人々が諏訪湖周辺を開拓して、出雲文化を広めたことを再編集しました。 |
2019年12月25日 |
67
blog6 |
| 66. 熊野古道と熊野三山 それに神武東征の道についてまとめてみました。 |
2019年11月20日 |
66
blog6 |
| 65. 以前訪れた長野県安曇野市穂高神社の再編集をしました。 |
2019年4月9日 |
65
blog6 |
| 64. 大阪府南河内郡太子町はオホド大王の孫推古女帝が 親族の古墳を集めて造営した 一大古墳群があります。「近つ飛鳥」と呼ばれる地域です。その古墳と大王家の陵を訪ねました。推古陵、用明陵、敏達陵、孝徳陵です。そしてオホド大王のひ孫の上之宮太子(聖徳太子)の陵とその子孫の出雲の足跡も載せました。 |
2019年3月21日
|
64
blog6 |
| 63-2. 越前三国国造家蘇我総本家へ婿入りした出雲富家彦太の君とその伴侶振比売の足跡を尋ねました。後のオホド大王(贈り名を継体)です。 |
2018年4月5日 |
63-2
blog6 |
| 63-1 NHKテレビで放映していた「世界遺産 沖ノ島」を観ましたが、あまりにもひどい内容だったので がっかりしました。 |
|
63-1
blog6 |
| 62.. 稲葉の国一ノ宮「宇部神社」に参拝しました。イクメ大王(垂仁)に大和を追われた武内宿禰が一時的に住んだ場所で、途中からイクメが放った刺客に追われ更に逃げて 旧出雲王家向家に保護されるまで 住んでいた場所に建てられました。 |
2017年10月12日 |
62
blog6 |
| 61.稲葉神社は襲津彦大王が息長帯姫との三韓征伐に出発する前に この地の金亀古墳に先祖の墓参りをし、戦勝を祈願して旗を立てた場所に建てられた神社です。 |
2017年10月12日 |
61
blog6 |
| 60..「白兎神社」 九州物部家を中心とする 都萬王国宇佐王国連合軍の東征で宇佐王家の菟上王が 出雲王国を攻めたあとこの地に前進基地を造りしばし滞在した陣地跡に建てられました。 |
2017年10月12日 |
60
blog6 |
| 59出雲族が大和葛城地方に移住、開拓して建てた神社を回りました。 その2 大穴持神社、高鴨神社、御歳神社 |
2017年6月6日 |
59
blog5 |
58出雲族が大和葛城途方に移住、開拓して建てた神社を回りました。その1 長柄神社、市杵島姫神社
|
2017年6月6日 |
58
blog5 |
| 57.梁書に書かれた「和国大乱」の舞台を歩きました。鳥取県日南町楽楽福神社界隈です。 |
2017年3月29日 |
57
blog5 |
56小説の主人公の皇子「ヤマトタケル」のお墓を宮内庁がでっち上げているのを地図で発見し、早速見に行きました。
その隣に磯城王朝第6代大王国押人(くにおしひと)大王の稜があるので見学しました。去年11月に訪ねた第 7代大王フトニ大王(孝霊)の父君です。国押人は後漢へ直接朝献に行きました。 |
2017年1月7日 |
56
blog5 |
| 55 葛城長江襲津彦大王のお后「桑津姫」(昔の日向髪長姫)の埋葬されている「島の山古墳」と そのまん前の桑津姫を祀る「比売久波神社」(姫桑神社)を訪ねました。 |
2017年1月7日 |
55
blog5 |
| 54 「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」出雲東王家が杵築大社(今の出雲大社)創建のために斐川に作った別邸が富村となり、御先祖の御霊を祭る「富神社」を創建しました。その富神社と、鳥取県大仙町の高杉神社を尋ねました。高杉神社は 第一次物部軍東征で大和を追われたフトニ大王が 第一次出雲戦争後 愛人たちと 余生を送った屋敷跡の神社です。 |
2016年11月22日 |
54
blog5 |
| 53 石見の五十猛海岸に上陸した徐福(素戔嗚)の長男、五十猛とそのお后の大屋姫を祀る 大田市五十猛の五十猛神社と 太田市大屋の大屋姫命神社を尋ねました。 |
2016年11月20日 |
53
blog5
|
52 九州物部群の東征は瀬戸内海を東進して吉備王国を攻めましたが、別働隊は日本海を東進して出雲王家を滅ぼしました。その本陣跡の物部神社と 佐毘売山(三瓶山)噴火で出来た布引池
に宗像三姉妹が祀られている迩幣姫神社(にべひめ)を訪ねました。 |
2016年11月20日 |
52
blog5 |
| 51 徐福らに殺害された第八代副王事代主の后の沼川姫は 事代主亡き後皇子のタテミナカタを連れて越の国の実家へ戻られます。その越の国の沼川神社を訪ねました。 |
2016年8月8日 |
51
blog5 |
| 50 鳥取県大仙町の妻木晩田遺跡を見学しました。古代出雲王国内の大集落跡です。 |
2016年5月21日 |
50
blog5 |
| 49 島根半島の神社を尋ねました。伊奈頭美神社(いなずみ)、爾佐神社(にさ)、爾佐加志能為神社(にさかしのい)、加賀神社です。 |
2016年5月19日 |
49
blog4 |
48 古代出雲族信仰の原点の一つ「割れ目岩」を祀った女夫岩、およびその周辺の「古墳の森」
佐為神社、大森神社を訪ねました。 |
2016年3月4日 |
48
blog4 |
| 47 古代出雲族が起源だと言われる岩信仰の神社 和歌山県新宮市の神倉神社と三重県熊野市 花の窟神社を訪ねました。 |
2016年2月6日7日 |
47
blog4 |
| 46 イクメ大王から名前が付いたイコマ山に鎮座してイクメ大王を祀る往馬神社、事代主の皇后の美穂津姫(沼川姫)を祀る田原本町の村屋神社、九州物部軍を無事に大和へ道案内した登美家当主加茂建津之身を祀る榛原市ヤタガラス神社 を尋ねました。 |
2016年1月11日 |
46
blog4 |
| 45 ヒミコが祭祀を行った「登美の霊畤」、記紀の編集者太安万侶も一族として祭られている多家の多神社、鏡造り部たちが住んだ土地に建てられた「鏡造り神社」を尋ねました。 |
2015年12月26日 |
45
blog4 |
| 44 東出雲王家向家の王宮のあった松江市大庭町界隈の史跡、出雲大神、風土記の丘、山代神社、岩坂陵墓参考地、からす天狗広場などを尋ねました。 |
2015年12月13日 |
44
blog4 |
| 43 菅原道真の生家跡に建てられた「菅原天満宮」と野見の宿禰 御陵に参拝しました。松江藩の保護を受け、立派な建物でした。 |
2015年12月13日 |
43
|
| 42 その子孫から数々の帝を出した武内臣太田根(武内宿禰)の御陵が保存してある 雲南市神原神社へ参拝しました。 |
2015年11月13日 |
42
|
| 41 出雲大社周辺の大小の重要な神社 出雲井、神奈備、意保美、そして長浜神社 |
2015年11月13日 |
41 |
| 40 徐福を祀る出雲市韓竈神社がなんと縁結びの神だなんて |
2015年11月13日 |
40 |
| 39 記紀の作り話、神武東征のモデルとなった 物部稲飯、三毛入の熊野上陸地点の浜王子神社と 徐福や穂日らに殺害された出雲の大国主の霊を彼の役職名をつけて祀る吉野大名持神社に参拝しました。 |
2015年11月4日 |
39
|
| 38 伊勢で一番古くて権威ある、伊勢一宮「椿大神社(つばきおおかみやしろ)」に参拝しました。出雲の神「サルタヒコ」と豊の国の豊姫(豊来入り姫または鈿女の命)を祀っています。 |
2015年10月7日 |
38
|
| 37 日光、上毛野国の古代出雲王家やその血を引く豊来入彦の足跡を尋ねる |
2015年9月15日 |
37
|
36-1 高倉下が母親の大屋姫とともに移住した紀の国のゆかりの地と五十猛を祀る和歌山の各地を回りました。伊達神社(いたて)、射矢止神社(いやと)、大屋津姫神社(おおやつひめ)竈山神社、伊太祁曽神社
を巡りました。
|
2015年9月8日 |
36-1
|
| 36-2 九州物部軍東征の折、紀ノ川河口上陸作戦で高倉下の子孫に戦で殺された物部五瀬を弔う竈山神社や五十猛、大屋姫を祀る伊太祁曽神社を訪ねる |
2015年9月8日 |
36-2
|
| 35 ソツ彦大王が祀られている羽曳野市大塚山古墳、ヒバス姫が父道主大王に造った天理市 東大寺山古墳を尋ねて、それから天理市和邇に坐赤坂彦神社、天理市石上神社、櫻井市大和神社を尋ねました。 |
2015年7月18日 |
35
|
| 34 ヒバス姫がモデルのイザナミが葬られたという神話の比婆山を歩きました。 |
2015年6月6日 |
34
|
| 33 九州南部を訪ねて古代出雲巡りをしました。日向、薩摩の国を尋ねて 都萬神社、西都原古墳群、生目神社、小戸神社、鹿児島神宮を周りました。 |
2015.5.30 |
33
|
| 32 奈良県天理市 手白香姫、イクメ大王、オシロワケ大王の各御陵を尋ねました。 |
2015.4.1 |
32
|
| 31 奈良市にある オキナガ姫、ヒバス姫、ワカタラシ大王の各御陵を巡りました。 |
2015.4.1 |
31
|
| 30 奈良県桜井市 宗像神社、大神神社、狭井神社檜原神社 |
2015.1.29 |
30
|
| 29 奈良県桜井市ホケノ山古墳、箸墓古墳、穴師坐射楯兵主神社、それと意味不明の大和トトビモモソ姫御陵 |
2015.1.29 |
29
|
| 28 奈良県櫻井市 磐余道と巻向を歩く |
2015.1.29 |
28
|
| 27 松江市山代二子塚古墳と安来市荒島王陵の丘 |
2015.1.21 |
27
|
| 26. 出雲王家の谷 西谷遺跡群の四隅突出墳丘墓とその埋葬品 |
2014.6.18 |
26
|
| 25. 古代出雲王朝終焉の地 田和山神殿と久奈子神社 |
2014.6.16 |
25
|
| 24. 徐福(素戔嗚すさのお)が上陸した五十猛海岸(島根県大田市) |
2014.4.24 |
24 |
| 23. 京都嵐山の松尾大社は徐福(ニギハヤヒ)と市杵島姫を祀る |
2014.4.17 |
23 |
| 22. 武内宿禰の武内神社、多岐津姫の阿太加夜神社、味鋤高彦の阿須岐神社 |
2014.4.10 |
22 |
| 21. .素戔嗚を祀る須佐神社と大国主を祀る出雲大社 |
2014.3.5 |
21 |
| 20. 京都八坂神社に祀られている宗像三姉妹 |
2014.2.2 |
20 |
| 19. 黄泉の国(よみのくにーあの世)への入り口黄泉比良坂(よもつひらさか)と揖夜神社 |
2014.1.12 |
19 |
| 18. 玉作湯(たまつくりゆ)神社 大国主と言代主を祀る |
2013.9.6 |
18 |
| 17. 宗像三姉妹を祀る安芸の宮島厳島神社 |
2013.6.23 |
17 |
| 16. 大己貴命(おほなむちのみこと)大国主を祀る大神山神社 |
2013.6.12 |
16 |
| 15. 渡来人徐福(記紀ではスサノオ)の部下穂日親子を祭る近江日野祭り |
2013.5.5 |
15 |
| 14. 大国主と言代主が幽閉されて命を絶たれた岩屋、猪目洞窟と志都の岩屋 |
2013.3.18 |
14 |
| 13. 熊野大社と嵩山布自伎美神社 素戔嗚(徐福)とその息子 |
2013.2.21 |
13 |
| 12. 大和葛城地方へ移住した出雲王朝の人々 その1古代出雲王朝系図と移住地図 |
2013.2.13 |
12 |
| 11. 大和葛城へ移住した渡来系出雲族海部家 その2葛城北部 |
香語山の葛木坐火雷神社 |
11 |
| 10. 大和葛城地方へ移住した出雲王朝の人々 その3葛城中部東出雲王家向家 |
奇日方の鴨都波神社 |
10 |
| 9. 大和葛城地方へ移住した出雲王家の人々 その4葛城南部西出雲王家神門臣家 |
味鋤高彦の高鴨神社 |
9 |
| 8. 事代主の息子タテミナカタを祀る「諏訪大社」 |
|
8 |
| 7. 神魂神社(天の穂日)と女神神社(玉依姫)と野見野宿禰 |
|
7 |
| 6. 石見神楽 2012年2月3日節分の京都松尾大社 |
|
6 |
| 5. スサノオ新婚生活の須我神社 |
|
5 |
| 4.. スサノオが降り立ったという船通山 |
|
4 |
| 3. スサノオ終焉の地と言われる日御碕神社 |
|
3 |
| 2. 古代出雲王朝の一大事 美保神社諸手舟神事 |
|
2 |
| 1. 熊野大社、美保神社、佐陀神社 |
|
1 |



