�x�߂̗��j���ɂ́u�q�~�R�v�Ȃ鏗�������т��ѓo�ꂵ�܂����A�L�I�ł͕s���R�Ȃ��炢
�O�ꂵ�āu�Ђ݂��v�����Ă��܂��B
�L�I�������������������E��b�����s�䓙��ɂƂ��ā@�Ȃɂ��@�܂������Ƃ�����̂ł��傤�B
����Ɂu�Ђ݂��v�̎���̓��}�g��鉤���̎���Ł@�a���͊��S�Ɏx�߂̑�����Ԃł����B
������悵�Ƃ��Ȃ��̂��@�q�~�R������v���ł��傤�B
�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�q�~�R�́@�o�ꏇ��
1.�����\�P�@�@�@2.�F���L�ʕP�@�@3.�T�z�P�@�@4.�L�P�@�@5.��a�P�@�@�ł��B
�|�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̃u���O�Ł@���݁@������q�~�R�ɂ��Ă̂܂Ƃ߂��s���Ă��܂��B
�����ł��̃y�[�W�ł́@���ꂼ��̃q�~�R�̏ڂ���������@���̎���w�i�͊ȒP�ɐG��邱�Ƃɂ���
����́u�q�~�R�̂܂Ƃ߁v�ɏڂ����������Ǝv���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
1.�T�z�P
�܂��T�z�P�̂䂩��̒n��K�˂܂����B
�T�z�P�̓��}�g��鉤����\��剤�@���q��(�Ђ����܂��A�F���Ƃ��������)�̕P�c���ł��B
�Z�����ەF�ƕF����ł��B
���q���剤�̍c�q�@�F����(�F���m�F�z�Ƃ��������)���a玂̒n�ő�\���剤�Ƃ��Đ������s���܂��B
���傤�ǂ��̂���@��B�������Ƃ̃C�N������������Ł@���˓��C��i�݁@�g�������𐧈�����
��g�ɏ㗤���܂��B
�����Đ���R�n���đ�a�N�����悤�Ƃ��܂����@����R�n�̓����Ł@���ەF�̑�R���C�N�����̍s�����
�j�݂܂��B���̂��߁@�C�N�����͎R���ɉi�����܂�@���̎R�̓C�N�����̖��O����C�R�}�Ɩ��t�����܂��B�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����ʂĂ��C�N�����́@���ەF�A�T�z�P�ɖ��g�𑗂�a�r��\������܂��B�T�z�P�͂����
����ā@�C�N�����̍@�ƂȂ�A�C�N�����͂悤�₭��a�ɓ���܂��B�������܂��剤�Ƃ͂Ȃ�܂���B
�T�z�P�͎O�֎R�̑��z�̏��_�����J����P�ޏ��ƂȂ�u����쏗�M(�����Ђ�߂ނ�)�v�ƌĂ�܂��B
�����������̓r���Ł@�����L�A�������̍ō��w�����̉F���L�ʕP�͕a�����܂��B
��e�̖L�ʕP�̑��V���I���@�x��Ă���Ă����@�L�P�A�L�F�����L���R�̓C�N�������T�z�P�ƌ������A�T�z�P��
���z�̏��_���J��@����쏗�M�Ƃ��Ă���̂Ɂ@�V���b�N���܂��B
���Ƃ��ƘA�������́@�F���L�ʕP�̌��ǂ̐_��Ă��܂�������B�����ŖL���R�͍��ەF�ƃT�z�P���U�����܂��B
�T�z�P�́@�L���R�ɒǂ��ā@�z���c���P�c�q����č��ەF�ƂƂ��Ɂ@�ߍ]��������֓������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����_���[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
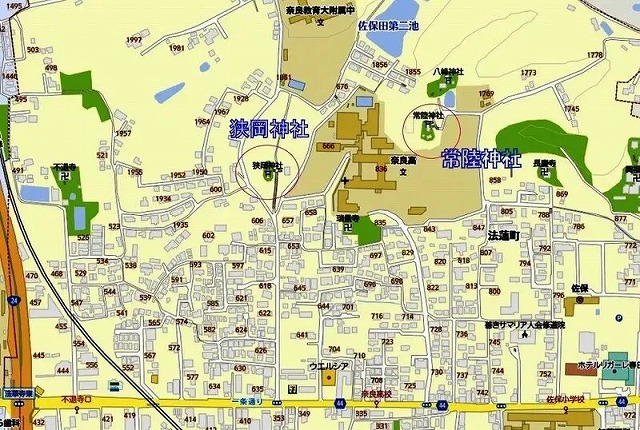
����K�˂�_�Ђ͏��߂ăl�b�g�Œ��ׂ܂����B�����͐Ė؉_�B�搶�̖{�Œ��ׂ�̂ł���
�T�z�P�̐_�Ђ��Ȃ���������ł��B�l�b�g�ɂ͂�������̃T�z�P���o�Ă��܂����B
���ɂ͐D���̏��_�Ƃ��@�t�̏��_�Ƃ���������܂������@�啔�������m�c�@���J��Ə����Ă������̂�
�����ɂ݂���܂����B��̒n�}�̓������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Z��X�̓˂�����ɂ���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ킩��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
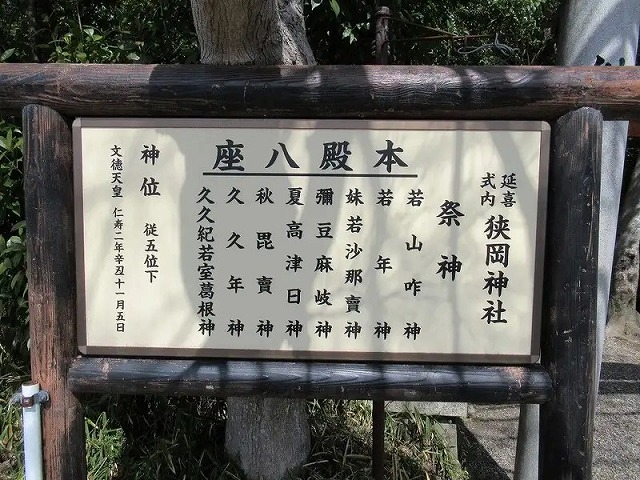
�Ȃ��߂Č���_�l�Ł@�T�z�P�Ƃ͂����Ȃ������ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�܂����������Ȃ��Ǝv���Ȃ���@�Ƃɂ����i�݂܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ă������ɐΔ�Ɛ����Ŕ�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
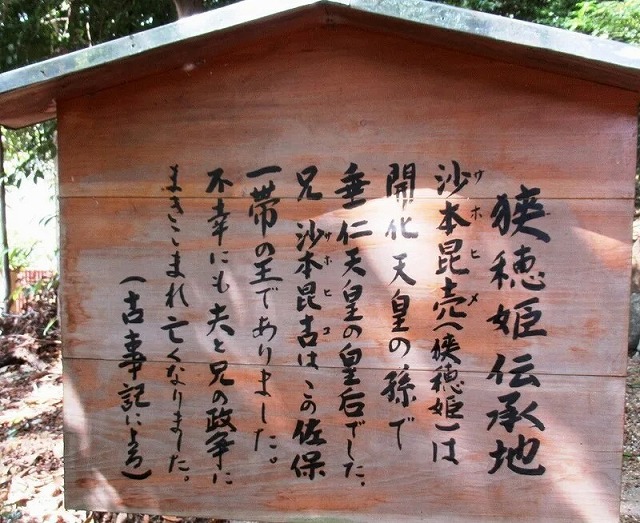
�L�I�����p�������ɂ͐��m�ł��B�������ɑ���X�剤�̑��ŁA�ꎞ�̓C�N���剤�̍c�@�ł�������B
�L�I�͑�10����q���Ƒ�11��F������B���Ă��܂�����A�T�z�P�̕��e�������Ȃ������̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�V�����Δ肪����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������T���Ă��T�z�P�̎ЁA�K�͂���܂���ł����B
�l�b�g�ł͉��l���̕����@�T�z�P���K�͏헤�_�Ђֈڂ��ꂽ�Ə�����Ă����̂�
������։��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�l�b�g�̒n�}�ł͏헤�_�Ђ͋����_�ЂƁ@�ޗǍ��Z�������Α��ɂ������̂ł���
�T�����܂����B����Ƃ��̈ē��W���������܂������A
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�T������Ă��Ȃ��Ȃ�������܂���B���傤�ǒʂ肩�������Ԃ̕��ɕ�����
���̊Ԃ����̂������ł��B
���͓ޗǍ��̑̈�فA�E�͓ޗǍ��̃e�j�X�R�[�g�Ł@�w�Z�̕~�n���Ǝv������܂���ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ƌ�����������������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ȃ�L�����������������T���܂����@������̐_�����
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������̐_������@�݂ȏ��߂ĕ����悤�Ȑ_����Ł@�Ȃ��Ȃ��T�z�P�͌�����܂���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̂͂���ɏ������K�������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ߊ���Ă݂�Ɓ@����Ƃ���܂����B�T�z�P��_�@�Ə����Ă���܂����B
�ǂ������������Ł@���̋����_�Ђ��炱���ֈڂ��ꂽ�̂��@�����킩��܂���ł����B
�Ƃɂ���������ɒ�������Ă��܂����̂Ł@�[�X�ƎQ�q�����ā@���Ɍ������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@�q�~�R�䂩��̒n��K�˂�c�A�[�@����2�@�����A�O�֎R�A�����_�Ђ֑���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
69-2�@�q�~�R�䂩��̒n���a�ɐq�˂�c�A�[�@
�@�@�@�@�@����2�@�q�~�R�̕���
�@�@�O�֎R�Ɗ����̒n����ƖL�P�̒n�@2021�N3��17��
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�q�~�R�䂩��̒n��K�˂�c�A�[�@�@����2�@�q�~�R�̕���@�O�֎R�Ɗ����̒n����ƖL�P
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�T�z�P�̒n����@���x�̓����\�P�ƖL�P�̒n�Ɍ������A����s�ɓ���܂����B
�����Ȃ肱��ȃo�J�����Ŕ����o�}���ł��B�Ŕ̒��g�͂�낵���B��������s�̎O�֎R�A�����R
���S�Ƀq�~�R�A�܂�P�ޏ��l���������ꂽ�̂ł�����@���̂Ƃ���ł��B
���������̏�����Ă���ڎ��̎��������܂���B2000�N�O�̎x�ߐl�������@����̍���l�X��̂�
���O�̎������܂��ɂ��肪�������Ďg���Ȃ�āB
����s�̔n���Ȏs�����̐E�������A�����Ɠ��{�l�Ƃ��Ă̌ւ�������Ȃ����B�p��m��A������B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��_�_�Ђ̑咹�����猩���O�֎R�ł��B�_�Ђ̂��_�̂ł��B
�����炲�_�̂̎R�ɓo�q���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

��_�_�Ђ̒����ł��B���̌`���o�_���̒����̌��_�������ł��B
�o�_�ł́@���]�s�̐��n�_�ЂɗB��c���Ă���Ɖ_�B�搶�̖{�ɏ�����Ă��ā@�K�˂܂�����
��������܂���ł����B
�����̋������狷��_�Ђ�������������o�q���܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�r���̔֍��_�ЂɎQ�q���܂��B�����ɂ́@���F�܂莖���ƋL�I�Ŗ��O��ς���ꂽ�o�_����
�攪�㕛���̔��d�g�Ðg���J���Ă��܂��B
���Ȃ݂ɑ�_�_�Ђɂ͏o�_�����攪��剤�A�܂��E���u�喼���v�̔��疵�����J���Ă��܂��B
�L�I�ł͑卑��Ɩ��O��ς����܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

������ɂ��Q�q���܂����B�s�n���_�ЂŁ@�s�n���P���J���Ă��܂��B
�@���O�o���̖����Ł@��������x�ڂɗ���������ɉł���āA�������Ƃ̑c�A���o���ƕ䉮�P��
�䐶�݂ɂȂ�܂����B�䉮�P�͏����̒��j�ŕ��Ⴂ�̌Z�́@�\�҂ƌ����������a�����剤��
�V�̑��_���䐶�݂ɂȂ�܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����_�Ђ̒������Ñ�o�_���ł��B�����̋�������300�~���ĎO�֎R�ɓo�q���܂���
�c�O�Ȃ���@�J�����͌ߑO�������Ƃ������ƂȂ̂Ł@�o�q�ł��܂���ł����B
���܂Ł@���_�̂̎R�́@������r�R�_�Ђ���j�̎R�ցA��؎R�_�Ђ����؎R�֓o�q�������Ƃ�����܂���
�����Ƃ��o���5���Ԃ�����܂����B
�O�֎R��20�`30���œo�q�ł������Ȃ̂Ɂ@�Ȃ��ߑO�������o�点�Ă���Ȃ��̂��킩��܂���
�Ƃɂ����郋�[���Ȃ̂ł��悤���Ȃ��ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���傤���Ȃ��̂Ł@�������ӂƞw���_�Ђ�������Ƃɂ��܂����B
���̕ӂ�͍���s���c�Ƃ����n���ł��B
�o���Ƒ��㓖��̑��c�c���q�́@�o���ƃN�j�A���P�̈����̃����\�P���x�������܂����B
���c�̒n���͑��c�c���q���炫�Ă��܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�O�֎R�R�[���犪�����ӂ߂��Ƃ���ł��B
�ʂ̃y�[�W�̃q�~�R�̂܂Ƃ߂ŏڂ����q�ׂ܂����@���̃q�~�R�̃����\�P���P�ޏ��ɂȂ�Ɓ@���������헐�����܂�
�a���ɂ悤�₭���a���K��܂����B
��ꎟ�����ő�a���肵�������R�ƒn���̏o�_�n��鉤�ƂƂ̑������@�����̌�����������X��
�剤�ɂȂ�Ɓ@�悤�₭���������܂�@�����\�P�̑��z�̏��_���J���Ղɂ́@���}�g�̍����͂��납
�����������������̍������Q�W����悤�ɂȂ�@���������̒n�ɂ�������̏h�ɂ����Ă���
�e�n�̍������Q���܂肵�Ȃ����ՂɎQ��������@���Q�����e�n�̓y�Y�������\�P�̐_�a�ɕ�[���܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����̏W���ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���́u�܂��ނ��v�͓�����ł��ˁB
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�������JR�����w�ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[

�����Ğw���_�ЂɌ������܂����B�������Ñ�o�_���̒����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ��A�O�_�ЂƓ����O����������܂��B
������o�_���ł����@���ݏo�_�Ŏc���Ă���̂́@�o�_���l�_�ЂŁA�Ñ�o�_������Z��喼����
�b�Ö�(���݂�)���J���Ă��܂��B���������Ƃ��ėL���ł��B
���ɂ����K���L�P���K�ł��B
�C�N�����̃��}�g�N���ő�a���������Ă���Ƃ��Ɂ@�ɓs�����݂�鰂̒��ݕ����@�����ɂ��
�a���̏����Ƃ��ĉF���L�ʕP�̌�C�Ƃ��ā@�����ɖL�P���w������܂����B
�L�P��鰏��ɂ́@��^�Ƃ�����@�u�Ƃ�v�Ɠǂ݂܂��B
�N�����u��܂Ƃ����v�Ə����ꂽ�̂��u��܂��������v�ƊԈႦ�ēǂ悤�Ɍ����āu������v�ł͂���܂���B
�L�P�͉F���L�ʕP�̈����Ł@�L�����P�ƌĂ�܂������@�u�Ƃ悫�v�ł́@�L�̍��������Ă������������Ƃ����̂�
���̂Ł@�L�I�ł́@�u�L�L����P(�Ƃ悷������Ђ�)�v�Ə�����܂����B�Ȃ�̂�������B
�Z�̖L�F���@�L������F�ł͂Ȃ��@�L�L����F�Ƃ�����܂����B�@
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

���ʂ̒�������͓��R��������͂��ł����@�����͉������Ђǂ��ĉ��������܂���B
�L�P�͂����w���_�ЂŁu���ǂ̐_�v��Đl�C���W�߂܂����@���̐l�C�Ɋ�@�����������@
�C�N�����͎����̕��Ⴂ�̌Z���̖L�F�ƖL�P��o���Ƃ̉��Γc���F�ɖ����ɖ����ā@���}�g����
�ǂ��o�����܂��B�L�P�̖��H���@�u�Ђ݂��̂܂Ƃ߁v�ɏڂ�����������ł��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�w���_�Ђ́u�R��ӂ̓��v�ɖʂ��Ă��ā@�n�C�J�[�������@�_�А��ʂɒ��X�����肱���֗����
�����������܂��B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�_�А��ʂ̍��͂����قƂ�ǎU���Ă��܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|

�����͂����łɂイ�˒�H��H�ׂ�̂ł����@�����x�������̂Ł@���͂���H�ׂ܂����B
��ς������������̂Ł@���y�Y�ɂ��@���܂����B
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�[
�P�ޏ��c�A�[�@�����
�Ñ�o�_�g�b�v�y�[�W�͂�����ł��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�����j���e�ɂ��Ắ@���ׂĐĖ؉_�B�搶�͂��߁@�匳�o�ł̂��ׂĂ̖{���Q�l�ɂ��܂����B
�_�B�搶���������ς݂ł��B�܂����ׂĂ̎ʐ^�͎��������ŎB��܂����B
�܂��n�}��Mapion������p���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�z�[���y�[�W�̃g�b�v�͂�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
69-1�@�A���ȓ����ꑰ��㩂ɂ͂߂��Ď��ӂ̂����ɖS���Ȃ����������^��
���セ���M������ꂽ�����ꑰ��V�c�Ƃɂ��@�w��̐_�l�Ɏd���ďグ���܂����B
�ނ̂�������Ɍ��Ă��ď��]�˂̎�����ی�������]�s�́u�����V���{�v
��q�˂��L�^�Ɂ@�⑫�����������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2021�N2��2��
�����V���{�Ɩ쌩�̏h�I�̌�˂�K�˂��L�^�Ɂ@���N����̓n���l�ڃ{�R�̐�����lj����܂����B
�܂������Ƃ̑c��@�o�_�n�̓y�t�Ƃ̐������lj����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��B�������Ƃ̓����ŁA�C�N�������ꑫ��ɓ��{�C��k�サ�A�o�_�����̓c�a�R�_�a��j������
鰂���Ⴂ�����{�̋т̌���i�����̌ꌹ�ƂȂ�j���������đ�a���肵���c���Ԏ�i���N�n���l
�q�{�R�̎q���j�́A���������}�g�̉��̂悤�ɐU�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��������̂͂��ŁA�c���Ԏ���C�N������鰂ɕʁX�ɒ����ɍs��(���̃q�~�R�L�ʕP�̎g�҂Ƃ���)�@
���ꂼ�ꂪ鰂̊��ʁu���N���v���������Ă���̂Ł@�c���Ԏ炩�炷��Ɓ@�C�N�����͎����Ɠ��i��
�v���Ă��܂����B
�g�������̓����Ɏ���Ă��A��a�ɒx��Ă���Ă����C�N�����́@�����̖��߂ɏ]��ʓc���Ԏ�Ɏ���Ă��A
�������|�����͂��́u���o�_���Ɓv�ɏo�_�i���R�i�ߊ��@�H��\�獪��ʂ��ā@���}�g�ɏo������
�c���Ԏ�����悤�Ɂ@���������߂܂��B
�������Ƃɓ|���ꂽ�o�_���Ƃ̓��@���o�_���Ƃ̕x��(�Ƃт�)�͖��O�����Ƃɑւ��Ă����B�C�N��������
�H��\�獪��ʂ��ďo����v�����ꂽ���Ɠ���̑��c�F�́@�o�_���Ƃ�łڂ����������Ƃ�
���������B�������o�_���Ƃ̐_���ȓc�a�R�_�a��j�����N�n�́@�c���Ԏ�͂����Ƒ��������B
�����Ō��Ɠ���̑��c�F�́@���O��x(�Ƃ�)�̖��O��쌩(�̂�)�ƕς��ā@�쌩���c�F�Ƃ��ā@�_���ȓc�a�R�_�a��
�j���@�n�����N�l�ڃ{�R�̎q���̓c���Ԏ�ɕ��K����ׂɁ@���̏���������ā@�o�_����
�����A��ă��}�g�i�R���A�c���Ԏ�������ɑł��j��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̐푈���@�L�I�ł͓����K��(�����܂̂��͂� ���c���Ԏ炪�̒n�ɂ��ČN�Ղ��Ă����ꏊ�u�ޗnj��䏊�s�������v��
�^�W�}�̖��O���a��^�C�}�ƌĂ�ē����̎������Ă�ꂽ)�Ɩ쌩�̏h�I(�c���Ԏ�̔s���Ɋ�C�N������
�쌩���c�F�ɕ������Ƃ̏d���̏̍��ł���u�h�I(������)�v��^���đ��c�F�͖쌩�h�I�ƌĂꂽ)�@��
���o�����̂��Ƃ��b�ɑւ����Ă���A�㐢�ɂ͂��ꂪ�告�o�̋N���Ƃ���Ă��܂����B
�L�I�̍��b�����낵�����Ƃɔ��W�������̂ł���B
�L�I�͕������Ƃ̃C�N�������@�o�_���̏�������ā@���}�g�̕�����������Ƃ��Ђ�����B�����߂�
�푈��͔�ׂ̑��o�b�ɂ��肩�����̂ł���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���}�g�ɏZ�ݒ������@�쌩�̏h�H �̎q���̏o�_���́@�Õ��z���Z�p�ɗD��Ă��ā@�C�N�����c�@�̃q�o�X�P��
��˂�z���A���̌�y�t��(�͂���)�ƌĂ�@�y�t�Ƃ𖼏��B
���C�N�����ƃq�o�X�P�̕P�c���̑�a�P�́@�M�S�����@���z�̏��_��Ĉɐ��֍s���@�ɐ��̍���
�ɎG�̋{�̎ЉƁ@���x�F�̕ی�̂��Ɓ@�\���̂قƂ�ɓ��{�����Ăđ��z�̏��_���J�����B
���x�F�͓o���Əo�g�ł���B
��a�P�̎���@��̂͑�a�ɉ^��ďo�_�n�̉�ΉƓ���@��Γc���F(���������Ђ��@�y�t�Ƃ���{�q����)
��ɂ��Õ�������Đl�X�́@�y�t�������������@�y�t��(�͂��͂�)�ƌĂ��@�L�I��
����Ɩ��O��ς��Ĕ���Õ��Ɩ��O�����ւ����B����ɉR�͉R���Ăс@��a�P�͔��ʼnA����˂���
�S���Ȃ����Ƃ����킯�̂킩�����b������������Ɂ@�{�����͂��̉R�̂���ɏ�悹������
�u��a�A�ƂƂу����\�P�v��˂Ȃ�đ�a�P�ƃ����\�P�Ƃ���100�N�ȏ㎞��̈Ⴄ��l�̃q�~�R
�u1�Ԗڂ�5�Ԗڂ̃q�~�R�v�����̂��������������Ă��܂��@���܂��Ă���B���ꑽ�����Ƃ��B
��2015�N1��19���̋L���ɂ̂��Ă��܂��B
�����Ă��̓y�t�Ƃ̎q������͊w��̉ƌn�̐����Ƃ��]�Ɓi��������̉̐l��]���[�₻�̎q���R�w�ҁ@��]���e�j��
���܂ꂽ�ƌ����B���Ȃ݂ɑ�]�Ƃ��ї����A�̑c��Ƃ���Ă���B
���c�a�R�_�a�Ղɂ��Ắ@2014�N6��16���̂��̃u���O�̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Ғ��u�����v�̒n�����̂��邱�̂�����͎R�̒����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̒��������Ɛ����V���{�̎Q�����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����ɂ͂��Ƃ��ƌ����c�F(�쌩�̏h�I)�̂��悪�������Ƃ����B
�쌩�̏h�H �͑�a�œc���Ԏ�̌R����ł��j��A�b����a�ɗ��܂�����A�C�N��������q�̂����y�n��
���q��ɔC���ďo�_�֊M������B���̋A�H�ɔd���̏o�_�n�̍����̉Ƃɏ��҂���Ă��y�����U����ꂽ�B
���������̉Ƃ̎g�p�l�Ɂ@���N�l�q�{�R�̉Ɨ��̎q���������Ă��ā@�H���ɓł��ė����ɂ��̒n��
�}�������ƌ�����B
�쌩�F�̈�̂͂��̒n�Ŗ�������A�吨�̏o�_�����o�_�������Ă��āA�쌴�ɐ��ā@��n���Ő�y���^�с@
�����������Ƃ����B����ł��̒n�͑吨�̐l���쌴�ɗ�����������u����v�ƌ����n���ɂȂ����Ƃ����B
��̂̈ꕔ�́@�o�_�Ɏ����A���ā@���̒n�ɑ���ꂽ�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����œn�����N�l�ڃ{�R�ɂ���
�ڃ{�R�͒C�̉��q�ł��������A���e�̒C�؉�����a�܂�ā@�Ɨ��ƍ�����^�����
�I�ɑD�œ��{�C��n���Ă����B�o�_�����̑喼��(�剤)�ɏ㗤�̋����肢�o�����@�喼����
�u��Z���̓y�n��D��Ȃ����ƁB�o�_�����̔�������(�@��)����邱�Ɓv�������ɏo�������ڃ{�R��
��������ۂ����B���e�Ɏ̂Ă��ĐS���r��ł����̂��낤�B
�喼���͏o�_�A�Ό��A���˂̒n�ɏZ�ނ��Ƃ��ւ����B
�����Ŕڃ{�R�͒A�n�̊ێR��������̂ڂ�@���ݕ��ɏ㗤���悤�Ƃ������o�_���ɒǂ�ꂽ�B
��ނȂ��ڃ{�R�W�c�͏㗬�̑��(�L���s)�̍L�����n�ɑD�𔑂߂đD�㐶�����n�߂��B
�����͊ێR��͌��͋����A�Ë��R�łӂ�����Ă��Ă��̂��ߗ��ꂪ�����㗬�͎��n�тɂȂ��Ă����B
�����Ŕڃ{�R�͐l�X���w�����ā@�Ë��R�����͌����L���ė�����悭����Ə㗬�ɔ엀�ȖL���~�n���o�������B
�V�������n�ƂȂ����ꏊ�Ɂ@�ڃ{�R�W�c�͓c�������W�������Z�ݑ����āA���̎q���͓y�n�̍����ƂȂ����B
�������ڃ{�R�́@�o�_���Ƃ��t���݂��ā@�o�_�����i�����ݑ����B
���̂��߁@��X�ڃ{�R�̎q�����o�_���Ƃɐ푈���d�|�����B
�o�_�����̔d���ɓ˔@�N�����Đ�̂��@�o�_���ƂƑ�a�̈���(�o�_���Ƃ̑�a���Ɠo����)�Ƃ̕��f��}��
���ʏo�_���Ƃ͌Ǘ�����B
�ڃ{�R�₻�̉Ɨ��̎q���͂��܂ł��o�_���Ƃ��t���݂������ā@���̎q�����쌩�̏h�I��
�ł����̂ł���B�������쌩�̏h�I�̌R�ɏR�U�炳�ꂽ�c���Ԏ�͔ڃ{�R�̎q���ł���B
�ق�ܒ��N�l�͎��O�[������Ȃ��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���オ������A�쌩�F�̎q������y�t�Ƃ��o���ā@�������炳��ɐ����ƂƑ�]�Ƃ��o�����B
�o�_�����Ɂ@���i�Ƃ��đ؍݂��Ă����������P�i����悵�j���A���̒n�Ɏ����̑c��̖쌩�F�̕��
�Q�q�ɗ����Ƃ��A�ē����Ă��ꂽ�n���̏��q���@�����Ȃ̂ɋC�ɓ��蒞�����ā@���܂ꂽ�̂����^���Ƃ����B
���^��6�̂Ƃ��ɓs����}�������ā@�e�q�͓s�֍s���@���^�͐����Ƃ̎q�Ƃ��Ĉ�Ă��A������ɂ����
�V���̍˔\���J�Ԃ��ē��p���������炵���B
���̌゠�̓��{�j�̉��_�ł���A���ȓ����ꑰ�i���̎q���͂��ԂƂ�����N�ȏ�c����H�����ɂ��Đ����Ȃ��炦�ā@
�߉q�����͂��ߌ���܂ő����Ă���j�̉A�d�Ɋׂ���Ė��O�̎��𐋂���ꂽ���́@���m�̎��ł���B
���̌�{���ŋN����������ȕ��̉������̘A���ɓ����ꑰ�́@�������^���M�肾�Ƌ��ꂨ�̂̂�
�ނ��w��̐_�l�A�V�_�l�Ƃ��đS�����J��̂ł���B
�ނ̎���@���̐��n�Ɍ��Ă�ꂽ�̂��@�u�����V���{�v�ŁA��㏼�]�ˎ�ɂ��A���ꑱ���ė����Ƃ����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Βi���������o���Ă����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Βi��o��Ɛ��ʂɔq�a������B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�����h�Ȍ������B���]�˂̕ی�������Ă��������͂���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�͂Ȃ�����Б���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�o�_���Ƃ̌������������Ȃ̂ɉ��̂��낤�B
��͏o�_���̏c�킬�ł͂��邯�ǁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Q�W�a�ł͒��x�ߏ��̕����W�܂��ā@25���́u�H�̑�Ձv�̏��������Ă���Œ��������B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�u�쌩�̏h�H�v �̌��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̘e�ɐΒi������A�����o���Ă����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������܂�Ƃ������悪����A�쌩�̏h�H �܂�����c�F�̌�˂��Ƃ����B
�J���������Ȃ��Ă����̂ŁA��˂ɂ��Q�肵����@�����������B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���c�F�̌Õ��́@�������ѓ쒬�쌩��ɂ�����܂��B
������K�˂��L�^�͂�����ł��B
http://blog.goo.ne.jp/yochanh1947-kodaiizumo/e/aa16ed0399a854fe21ff961e972b14f0
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
68�@���������̐��̒[�ɂ�������_��(�Ђ݂̂�������)��q�˂܂����B
�@�@���Ï���̑��Ő������q�̍c�q�ł�������u�����L�x�ȍ��͂ő��c���܂����B
�@�@���������얋�{�ɂ��Ռ`���Ȃ����ւ����܂������A�Ћ��ɂЂ�����ƘȂ�
�@�@�@���_�ЂȂǂɌÑ�o�_�����̕Ђ��������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2020�N9��10���@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�������q�̍c�q�A���u�������Ă������_�ЂɎQ�q���܂����B�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�z��q�ށ@�����_�Ё@�@����1�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����_�Ђ́@�o�_��Ђ̖k�A���������̐��[�ɂ���܂��B
���̒n�́@���{�C�ɒ��ޗ[�z��q�ނ̂ɓK�����ꏊ�ł��B
���̒n�ɗ[�z��q�ށu�����_�Ёv�����Ă��̂́@���u���ł��B
���u���͏�̋{�@��(�����鐹�����q)�̍c�q�ł��B
���̂�����̎���͌�قǏڂ����������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�s���猧�����Ԃő���Ɓ@�₪�ĎR�Ԃɐ_�Ђ̌����Q���݂��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�傫�Ȑ̒�����������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ȃ��Ր_���傫�������ꂽ�Ŕ����o�}���ł��B
�V�Ƒ�_�͑��z�̏��_�Ł@�Ñ�o�_���Ƃ́u�����̖̂��v����a�����ŃA�}�e���X�Ə���������ꂽ���̂�
���z�̏��_���J��̂͂킩��̂ł����@�Ȃ��f���j�܂菙���Ȃ̂ł��傤���B
�������I���O3���I���Ɍ\�ҊC�݂ւ���Ă��ā@�o�_���Ƃ̎剤�ٔ��疵�╛�����d�g�Ðg��
�������ŗH�E�Q���āA�������o�_�����̉��ɂȂ낤�Ƃ��āA�X���������o�_������
��\�ꂳ�����厖���͂܂����̂���(���Ò�)�͓s�̋M���������L�����Ă����Ǝv���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
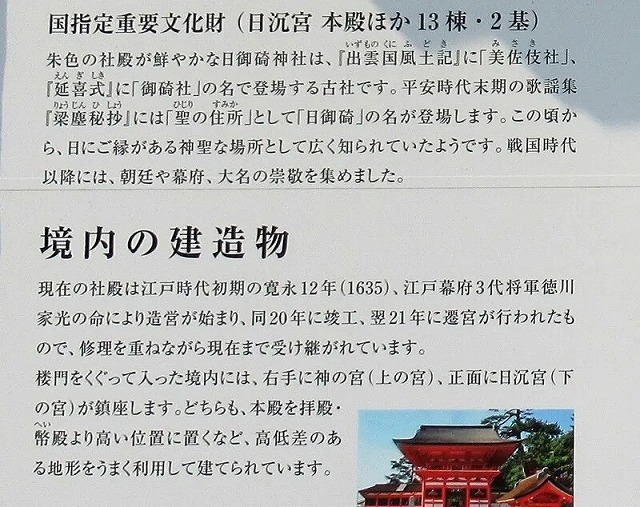
�����Ŕɂ��@���̐_�БS�̂��@���얋�{�ɂ��@�S�ʓI�Ɍ��đւ����Ă���
���̎��Ɏ�Ր_���ւ���ꂽ���@�lj����ꂽ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̒n�����x�z���Ă����@��q�����ї��ɔs��A�ї����G�g�ɉ��肳��ɓ���ɂȂ������߂̂���
�ł�����@�������̒n�ł������̈��s�ɑ��錙���������Ȃ肤����Ă����̂ł��傤�B
�������J�邱�ƂŁ@��Ԃ̂͏o�_��Ђ̋{�i�̉ƌn�����ł�����B
�����ďo�_��Ћ{�i�͖���(�قЁ[�����̒����ȕ����ŏ����ƂƂ��ɏo�_�����Ŗ\�ꂽ)�̎q���ł�����B
���Ȃ݂ɑS���̓V�c�˂Ȃ���̂��@���̎p�����߂��炠�����킯�ł͂Ȃ��A�������̌������̈Ȍ�
���삪���z�̔�p���o���ā@�قƂ�ǂ̓V�c�˂����ւ��Ă��܂��B
���łɎ��݂��Ȃ��V�c�̗˂������肽������ł����B
���ˋ�̑剤��c�q�̐_���A���}�g�^�P���̗ˁA��B����o�����Ƃ̂Ȃ��C�j�G��(���_)�̗�
�����\�P�Ƒ�a�P�Ƃ�������̑S���Ⴄ��l�̕P�c��(������q�~�R)���������Ĉ�̗˂Ƃ�����B
�Ȃ�̂�������Ƃ��������ł��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�Ȑ_��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_��������苫���ɓ���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ʂ��u�����݂̋{�v�ł��B�A�}�e���X���J���Ă��܂����@�����̕����������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�ł��B�Ȃ���т₩�ł��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����������т₩�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͖{�a��^�����猩���Ƃ���ł��B�����͂��ׂāu��������v�Ȃ̂ŁA�{�a��
��Б���Ƃ͎��Ă������Ȃ������ɂȂ��Ă��܂��B���̔q�a�Ƃ̊Ԃɕʂ̌��������܂�Ă��܂��B
�u�̊ԁv�ƌĂԌ����ł��傤���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͐_�̋{�ŁA�[���̒��ޕ����������Č��Ă��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�̋{�q�a�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�����Ő�قǂ́@�����݂̋{�̔q�a�Ǝ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����{�a�ʼnE�̔q�a��菭���傫���悤�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�̋{��������݂̋{������Ɓ@���傤�ǂ��̉��ɗ[�z�������܂����B
�Ƃ������ƂŁ@�����̌����͂��ׂČ�������ƌĂ�錚���Ł@���얋�{���������Ƌ{�������
��H������A��Ă��ā@���c�������̂ł��傤�B
���l�I�ɂ́@�o�_�̕��y�ɂȂ��܂Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂����B����ɑf���j����Ր_�Ƃ���̂�
�����̎q���A�`���l�̖��Ⴝ���̂��邱�ƂŁA���s�̏�����ЁA����_�ЂȂǂ������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̗��ɂЂ�����Ə������K������̂ŋ߂Â��Ɓu�؍�(���炭��)�_�Ёv�Ə����Ă���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ր_�͑f���j�܂菙���͓�����O�ł����@�����ɂ͏����ɉœ��肵���o�_���Ƒ掵��剤
�u�V�̓~�߁v�̕P�c�����������̒��j�u�\��(���������[�̂��̍���R)�v���J���Ă��܂����B
�O���l�܂�n���l���J���Ă��邩��@�؍�(���炭��)�Ɩ��t�����̂ł��傤�B
�_�Ђ̗R�������Ɂ@���̐_�Ђ̋{�i�̉��c���u�V�̓~�߁v���Ə�����Ă����̂ł����@���肦�܂���ˁB
�o�_���Ƃ̎剤�������ɎE�Q���ā@���������ɂȂ낤�Ƃ����z���o�_���Ƃ̎q����
�J��Ȃ�Ă��肦�Ȃ����Ƃł�����B�L���ȓV�̓~�߉��������̑c�悾�ƋU���Ĕ�������������
�̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̂Q�֑���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�z��q�ށ@�����_�Ё@�@����2
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̂��ꂢ�ȉ�L���o���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������ɂ�����������ǁ@���h�Ȃ��Ђ�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ߊ��Ɓu�@���_�Ёv�Ƃ���A�c�S�P(������Ђ�)���Ր_�ł����B
�c�S�P�͏o�_�����掵��剤�̉J�̓~�߂ɉł��ꂽ��B�̏@���Ƃ̎O�o���̒����̕��ł��B
�����ēc�S�P�����܂ꂽ���ƕP�������ɉł���ā@�\�҂��䐶�݂ɂȂ����̂ł��B
�@���Ƃ́@�o�_���Ƒ�Z��剤�̐b�Ö�(���݂ʁ[���������Ƃ��ėL���ł�)�̍c�q�̌�c�Ћ�����B�ֈڏZ����
�J���ꂽ�o�_���Ƃ̕��Ƃł��B
���Ȃ݂ɏ@���O�o���̎����̑���ÕP�͑攪��剤���疵(�����ɗH�E�Q����܂���)�ɉł���܂����B
��������������\���A�����Ďn�c�邩��X�Ȃ鎑���Ƒ����̊C�����������炢�@��x�ڂɍ���̕��u��
�㗤�������Ɓ@�@���Ƃ���߂Ƃ����P�������̎s�n���P(���������܂Ђ�)�Ŏs�n���P�́@�����̎��j
���o���@�ƒ����䉮�P���䐶�݂ɂȂ�܂����B
���o������B�����Ƃ��������̎q������x�ɂ킽�V�������ā@��a���Ƃ�|���̂ł��B
�䉮�P�͏����̒��j�\�҂ƌ������V�̑��_���䐶�݂ɂȂ�V�̑��_���@�����a���Ƃ̉��ƂȂ�̂ł���
�����̎��j�̎q���̓����œ|�����̂ł��B���Ƃ��b�̊C�K�F�ƎR�K�F�̌Z�팖�܂̃��f���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ƃ������ƂŁ@���u�����L�x�ȍ��͂Ō��݂����_�Ђ́@���얋�{�ɂ��Ռ`���Ȃ����ւ����
�ƍN���J��������Ƌ{�̂悤�ȃL���L���������̂ɂȂ�@�l�I�ɂ͍D���ɂȂ�܂���ł�����
�ό��q���N�����悤�Ƃ��Ȃ��@�Ђ�����Ƃ����؍��_�Ђ�@���_�Ђɂ����@�o�_���Ƃ̍��Ղ�
�c����Ă��ā@������K�˂��b�オ����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Ђ𐼂֏o�ĕ����Ɓ@�����ɓ���ꋙ�`������
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����E��Ɍo��(�ӂ݂���)������܂����B�����݂̋{�͂��Ƃ��Ƃ�����ɂ������Ƃ���Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�A�H�Ɍ����𑖂��Ă���Ɖ����ɍ��l�������Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����₻�̒����ȕ����̖���(�قЁ[���̏o�_��Ђ̋{�i�̑c��)���ɂ��@�����_�Ђ̂�������������
���{�C�ɖʂ����u���ړ��A(���Ȃ߂ǂ�����)�v�ŗH�E�Q���ꂽ��@�s�䓙��ɂ��L�I�ł�
���̈�̕l�Ł@�卑��(���疵��)�͍������������@���M���Ђ�����Ԃ��Ă��̒���
��B��ɂȂ�܂����B�ƎE�Q���B���ꂽ���l�ł��B
�܂����̍��l�́@���N�_��(�o�_�ȊO�ł͐_����)�ɑS���̐_�X�����̍��l�ɏ㗤�����
�o�_��Ђ�������Ƃ������b������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��������_�Ђ����Ă�ꂽ���u���ɂ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
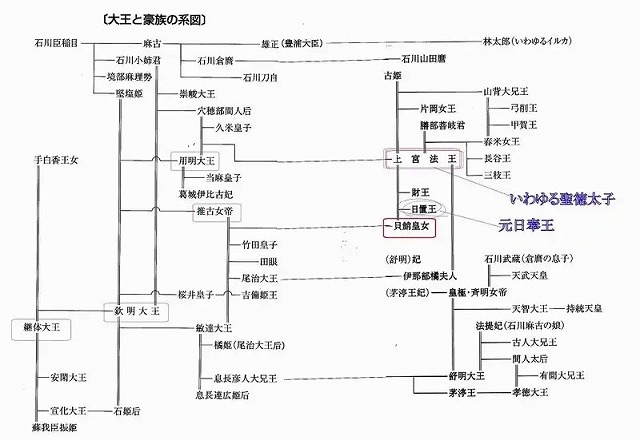
���Ï���̌Z�u�p���剤�v�Ɛ��Â̕P�c���u�L��(��������)�P�c���v�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�c�q��
��l�Ł@���j������(�����炨��)�@���j�����u���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����_�Ђ́@��H�����P(�݂���������Ђ�)�剤(����)�̎w���ŏo�_�̍��ɔz�����ꂽ���u����
���Ï���̊�]�ɉ����@���݂������̂ł��B
�t�g�^�}�W�L�剤(�q�B)�̎w���Őݗ����ꂽ�@����(�Ђ܂��)�͑��z�M�̕����ł��B
�Ñ�o�_���Ƃ₻�̑�a���Ƃ̓o���ƁA���Ƃ͎O�֎R�ő��z�̏��_��M���܂����B
����͓��̏o��q�ނ��̂ł����B����ɑ��ē��͗[�z��q�ނƂ���Ă��܂��B
���u���͂��̓���q�B�A���Â���p���@���Ə̂��Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����o�_�ł́@�L��剤(�Ԗ�)�̎���ɍL��剤�ɂ��@���u�̔���(�ւ��̂Ƃ���)�炪�h�������
�o�_�̉��Ƃ̒J�ɍL��剤�̎w���Ł@�����o�_���Ɛ_��b�Ƃ̂��߂Ɏ��X�Ƌ���Õ������z����܂����B
�L��̕��N���j���(���ق�)�剤(�p��)�Ł@���̕��͓��o�_���Ƃ̒j��瑂̌N�ł�����A������O�̂��Ƃł����ǁB
�����̕ӂ̂��Ƃ͂��̃u���O�̒j��瑑剤���z�O�ɐq�˂闷(2018�N4��5��)�����Ă��������B
���܂����u����������o�_�ɔz�����ꂽ���R�Ȃǂ͂��̃u���O��2019�N3��19���̋L�������ǂ݂��������B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����o�_�ɔz�����ꂽ����́@���łɓ��u�̔����炪���l���ˏo��������������Ă��܂����B
���u���͂��Ƃ��ƒ��N�n�̎����ł��B���̍��s�ł͒��N�n�̑�����(�����Ȃ�)�n�̐����������
���͂ɂȂ��Ă��܂����B�����œ��́@���N�n�̔��Q������邽�߂Ɂ@���u�̖����p����
���u���Ɩ����悤�ɂȂ�܂����B
�����_�Ђ̊������ā@�z�c���剤(����)�͑傻����ꂽ�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎ʐ^�͏o�_�s�̍֒J�ɑ����z���ꂽ�@�o�_�����Ɛ_��b�Ƃ̉��Ƃ̕�@�l���ˏo���u��̈�ł��B
���u���́@�������ő��c���ꂽ�@�㉖��z�R�Õ��ɑ����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ���̓��u���̌Õ����甭�@���ꂽ�i�X�ł��B���̂ق������̑����⑽���̃u���X���b�g�ƃl�b�N���X������܂��B
�������ʂ�l�b�N���X�Ȃǂ̑����i�͉��������g�ɕt���邱�Ƃ�������܂���ł����B
�u�o�_�퐶�̐X�����فv���w�L�͂��̃u���O�́@2014�N6��18���̋L���ɂ���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ�������ꂽ���u���̎ʐ^�ł��B�����ق̃p���t�ɍڂ��Ă���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�u�Ñ�o�_�����䂩��̒n��K�˂āv�g�b�v�y�[�W�͂�����ł��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����̃u���O�̓��e�́@�匳�o�ł̐Ė؉_�B�搶�����ׂĂ̖{�̓��e�ɂ��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�z�K�Ƃ����@�o�_���Ƃ̌��䖼��(���Ă݂Ȃ���)���J�����ƂŒm���Ă��܂��B
���̕ӂ̂��Ƃ����������ڂ����q�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�z�K�Βn�����J�������o�_���@�@����1
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����̓n���Ɛ`���l�ɂ��@�o�_�����̎剤�A�����̎E�Q
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�I���O�O���I���A�����͑吨�̊C�������������A��� �ŏ��������̑��c�s�\�ҊC�݂ɏ㗤�� �a�����u�Ζ�����i�ق�����j�v
�Ɩ����܂��B���O�ɒ����ȕ����́u���ڃz�q�v���o�_�����Ɏg�킵�ā@�㗤�̋������t����Ƃ��������Ȉ��I�݂����Ă���ł��B
���Ȃ݂Ƀz�q�̎q�������̏o�_��Ћ{�i�ł��B�㗤���������͏o�_�ɏZ�݁A�o�_���Ƃ̍��ƕP��W�� ���j�����܂�@�\�ҁi���������j�v
�Ɩ��t���܂��B�����̕��̖������҂ƌ������̂Ł@�u�ҁv��t�����̂ł��傤�B
�������o�_�����̉��@�܂�a���̉��ƂȂ����ł���Ă��������́@�����̏o�_�����̎剤�ƕ�����S���҂ɂ��܂��B
�����̏o�_�� �剤���疵�i��E���͑喼���Ł@�L�I�ł͑卑��Ƃ��单�Ƃ��喼���A����Ə����ꂽ�j�ƕ����̔��d�g�Ðg
�i��E���͏��F�ŋL�I�ł͎����Ƃ������F���Ə����ꂽ�j���z�q��C�������ɖ����ėU���H���ĎE�Q��
�������o�_�̉��ɂȂ낤�Ƃ��܂��� �����̑g�D����������Ƃ��Ă��� ���ꂪ�ʂ������Ɂ@��������`���A�����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�\�ҊC�݂̒n�}�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�t�߂̒n���ɂ́@�w�����͂��ߏ��w�Z�A�����_�ȂǑ����̌\�҂�����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�\�ҊC�݂̐_���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
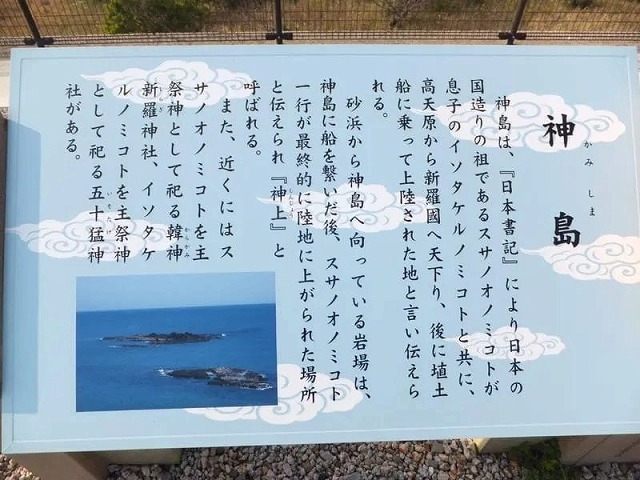
�_���̐����Ŕł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���������㗤�����Ό��\�ҊC�ݖK��L���́@2014�N4��24���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ړ��A�̒n�}�ł��B���Ȃ݂Ɂ@���̒��l�Ƃ́@�L�I�̍��b�ő卑�傪���M���Ђ�����Ԃ��Ă��̒��ɉB��Ă��܂����Ƃ������l�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ړ��A�ł��B�����Ŕɂ́@���̐��̐��E�u����̍��v�ւ̓�������Ə�����Ă��܂����B
�ق�Ƃ̂��Ƃ������Ɓ@�o�_��Ђ̋{�i������܂�����˂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̒n�}�ł��B���d�g�Ðg(�����)�͔��ۊւ̏���P�̌䉮�~�ɂ����Ƃ���ڂ����ɗU���o����āA
�܂�喼�����s���s��������@�������Ă���Ɓ@�U���o����@���̊C(���̒��C)�𐼂��������܂܁@
�s���s���ɂȂ����Ɓ@���Ƃɓ`����Ă��邻���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�s�̊≮���A�̑O�ɂ͒����������Ă��܂��B�������n�Ȃ̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���(�����Ȃ�)�Ƃ͏o�_�����剤�̖�E���喼���̂��Ƃł��B���F��(�����ȂЂ���)�Ƃ͕����̖�E�����F��
�L�I�ł́@�Ӑ}�I�ɊԈႦ�\�L���Ă��܂��B
���t�W�̎���܂ł́@�卑��(�攪��̔��疵��)�Ǝ����(�攪��̔��d�g�Ðg����)�����A�ɗH����ĎE���ꂽ���Ƃ�
�l�X�͒m���Ă����̂ł��ˁB�ޗǎ���̓s�̋M�������̑唼�͏o�_���ł�������A������܂��ł����ǂˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���喼�����H�E�Q���ꂽ���ړ��A�Ə��F���H�E�Q���ꂽ�u�Â̊≮�̖K��L���͂��̃u���O��2013�N3��18���̋L���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�o�_�����̍c�q�����̑�a�ւ̈ڏZ
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����A���̕�������A����̑��q�Β�(�ЂȂǂ�)��C�������ɗH�E�Q���ꂽ
���d�g�Ðg�����i�L�I�ł͎����Ə��������܂����j�̍@�̈�l���ʈ˂�P(�������܂��Ђ�)�͍c�q�̊�����i�����Ђ����j
��A��Ď��Ƃ̎O���i���̑��{�O���S���{���j�ɋA��܂��B
�����Ċ�����͎O���̐l������吨�̏o�_���ƂƂ��Ɋ���n���i���̓ޗnj����鎁�A�䏊�s�j�ɈڏZ���o���Ƃ𖼏��܂��B
�����ā@����������������ɗH�E�Q���ꂽ�@���疵���i�L�I�ł͑卑��Ə��������܂����j�̍c�q�@
�������F�i�������������Ђ��j���吨�̏o�_���������A��Ċ���암�ɈڏZ���@�����Ƃ𖼏��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�������Ŗ\��܂��C�������`���l�����Ƃ̋����������A����n��(���̋����R�A��a����R�̎R��̓���)��
�ڏZ�����@�o�_���Ƃ̍c�q�����̐��͐}�ł��B
�����������̑��q�̌\�҂��O�g�n���ɈڏZ���ā@�u����R�v�Ɩ����܂��B�����č���R�́@�������Ƌ�B�@���Ƃ̎s�n���P�Ƃ�
�Ԃɐ��܂ꂽ�䉮�P(�܂荁��R�̕�Ⴂ�̖�)�ƌ������܂��B
�����č���R�ƕ䉮�P�Ƃ̊Ԃ̒��j���u�V�̑��_�v�Ł@�o�_���Ƃɒx��đ�a����n���֏�荞��ł��܂����B
��a���肵�������̑��̓V�̑��_�����`������̓n���O���[�v�̓��}�g�ŋ���Ȑ��͂ƂȂ�܂��B
�I���O2���I�̓����ł́@����l�K�͂̊C�������́@���������̐��͂Ȃ̂ł��B
�����Ł@�o�_�����̓�l�A�������F�Ɗ�����́@�Ƃ��ɓV�̑��_�������a�剤�ɂȂ�̂������Ďx�����܂��B
�����a�剤�i�������݂ƌĂ�Ă��܂����B�V�c�ƌĂꂽ�͓̂V�������̂��Ƃł��B�j�̍c�@�ƂȂ����̂�
������̖��u����\��P�i�����炢�����Ђ߁j�v�ł��B�����Đ��܂ꂽ�̂��c�q�́u���쎨�i�ʂȂ���݂݁j�v
�œ��ڑ�a�剤�ƂȂ�܂��B
���@�L�I�͓V�̑��_�̖��O�������āu�_���v�Ƃ����ˋ�̖������܂����@���ڂ̏��쎨�A�O��ڂ̋ʎ��(���܂Ă�)�Ȃǂ�
���̂܂܋L�I�ɖ��O��������Ă��܂��B�������C�N���剤�i���m�j�O�ォ��͋L�I�̑剤���͂ނ��Ⴍ����ɂȂ�܂��B
���̃u���O�̋L���ł��ڂ������グ�ĖK�˂Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�V�̑��_�B�����Ă��@���鍿�Η��_��(���炬�ɂ��܂��ЂƂ����Â�����)�ʏ̓J���_�Ђł��B
�Ɨ��Ƃ͐��S�@�̓���(������)�̂��Ƃł��B
�C�������`���l�̎q���͌̋����Âс@��?(�Ƃ�����)�ƌĂ��y�J�𐁂��Ă��܂����B
����œJ���_�ЂƂ��Ă��̂ł��B
��?�̓I�J���i�̒��Ԃ̊y��ŏ��ň��闑�`�̊y��Ł@���̌����J���Ă���y�J�ł��B
�C���̎q���̃n�^���ƌĂ��`���l�̎q���������Z�n�悩��@�������@����Ă��܂��B
���]�s�̐���Â�ÉY���u�̈�Ղ��瑽�����@����Ă��ā@�n�^���̏Z����n���A�܂������̒��j����R
(�\��)���ڏZ�����O�㔼���A�Ȃǂł������o�y���Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���s�g�_�Ђ͓��o�_���Ƃ̌��Ƃ̍c�q�����(�����Ђ���)�����S�ɂȂ�ڏZ�J�A�����_�Ђ�ꌾ��_�Ђ����Ă܂����B
��Ր_�͂�������ł��B�ނ�͌�ɓo���ƂƖ����悤�ɂȂ�܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����_�Ђ͐��o�_���Ƃ̐_��b�Ƃ̖������F(�������������Ђ�)�𒆐S�Ƃ��ďo�_�����ڏZ�J��
�����_�Ђ����Ă܂����B
�Ր_�͂�����e�̔��疵���̂͂��ł����@�Ȃ��������ł��B����Ɖ��ƕP�ł��B
���ƕP�͕����疵���Ɣ��_�P�Ƃ̕P�c���Ŗ������F�̕�Ⴂ�̖��ł��B
�ނ�͍����ƂƂ���ΉƂƖ����܂��B���Ȃ݂ɌÑ�o�_�ł́@�_�̂��Ƃ��u�����v�Ɣ�����
��Ɋ��̎������Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����a����n���ֈڏZ�J���o�_���̑��Ղ�K�˂�L���́@2013�N2��13���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����2�֑���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�U�V�@�@�z�K�n�����J���o�_���@�@����2
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���ې_�Ђƌ��{�{��(�݂ق�����)
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��������(���d�g�Ðg)�̂�����l�̍@�̏���P�͔��ۊւɉ��~���������̂Ŕ��ےÕP(�O��ÕP)�Ƃ��Ă�Ă��܂����B
�����Ď����S����@����P�́@�c�q�̌��䖼���i�^�e�~�i�J�^�j��A��Ď��Ƃ̉z�̍��A���̎�����ɋA��܂��B�@
����������P�̕P�c���̌��{�{���A�܂��͔��ې{�X��(�݂ق�����)�́@����P�̏Z�܂��̔��ۊւ̓@��Ɏc��@
���ې_�Ђ����Ăĕ��̔��d�g�Ðg���J��@�ꐶ����ۂ̒n�ʼn߂�����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���Ȃ݂ɔ��d�g�Ðg�͋L�I�Ŏ����Ə�����@���オ����ƌb����l�ƌĂ��悤�ɂȂ�̂�
���ې_�Ђ͌b����l���J��_�ЂƂ������ƂŁ@�S���̏^�_�Ђ̑��{�ЂɂȂ�܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s���ۊ֒��͔��ې_�Ђ̖�O���ł��B��e�̐Ώ~���ꂽ���œy�Y����������ł��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ې_�Ђ̓�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�Ȑ_���������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�Ȕq�a�ł��B�S���̏^�_�Ђ̑��{�Ђ炵���d���ȑ���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̌��ɖ{�a������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
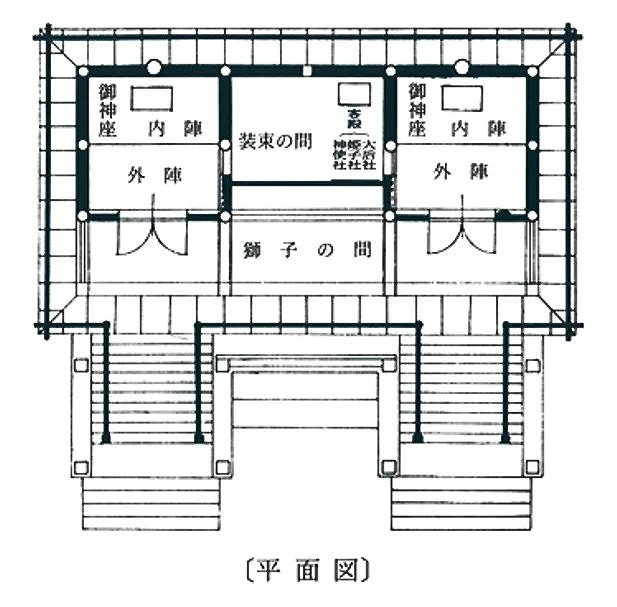
�܂����ې_�Ђ́@���ےÕP(����P)�Ǝ�������J��̂ł��ꂼ���Б������Ăā@������u�����̊ԁv
�ƌĂ�錚���Ōq�����`���̌����Ŕ��ۑ���ƌĂ�Ă��܂��B
���������Ƃ��Ƃ͌��{�{��(�݂ق�����)�̈ꒌ�݂̂��J���Ă����Əo�_�̍����y�L�ɏ�����Ă��������ł��B
�������o�_���y�L�̓C�N���剤���V������������ɓs�ɋ삯���đ剤�ɒ��k�����ā@�o�_�����Ɍ��܂��Ă��������̏\�獪��
�Ђ�����Ԃ��ā@���ڂ̎q���̉ʈ��������ɍ����ɂ��Ă��炢�@�o�_���y�L���ʈ��炪��������Ƃ��l�����
�����Ə���P�̖��O�����܂萢�ɏo�������Ȃ��̂Ł@���̔��ې{�X���������Ր_�ɂ����Ƃ��l�����܂��B
�����Ď������E���ď���P���z�̍��֒ǂ�������Ɛl�́@�����̒����ȕ����̖���(�ق�)�ł�����ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����12���ɍs������ې_�Ёu����M�_��(���낽�Ԃ˂���)�v�ł��B
���ۂ̏���P�̌䉮�~�ɑ؍݂��Ă��������(���d�g�Ðg)�̂Ƃ���Ɂ@�喼��(�卑��)���s���s�����Ƃ����m�点��
���M�Œm�炳�ꂽ�@�̎����������_���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s�̉w�O���X�X�ɂ́@�u����P�v�Ə��������X������܂��B�ȑO����C�ɂȂ��Ă����̂ł���
���̂��X���@�킩��܂���B�������݂₰�����������悤�ȋL��������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����_�Ђ̂���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����P�ƍc�q�̌��䖼���͉z�̍�(���̎�����s)�ɋA��܂��� ���䖼���́@���̌�吨�̉z�̐l��
�o�_����A��Đz�K�~�n�ֈڏZ���z�K�n���̊J��ɓw�͂��Đ������܂��B
�����Č��䖼���i�^�e�~�i�J�^�j�͐z�K�n���Ő��ȑ��h���W�߂܂��B�����ď���P���B
�z�K��Ђ̎�Ր_ �͂�����䖼���i�^�e�~�i�J�^�j�Ɓ@��e�̏���P�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���@�L�I�̐���҂̎��������s�䓙���������̖��Ⴝ���́@�z�K�̐l����������ȑ��h���W�߂�
���䖼�����C�ɓ���Ȃ������炵���A�L�I�ł́@�u�o�_�֍�����̌��ɏo�������^�e�C�J�d�`
�Ȃ�r���҂Ɓ@�o�_�̉��q�@���䖼���i�^�e�~�i�J�^�j���͔�ׂ����ā@�^�e�~�i�J�^�͕����Đz�K�֓������т�
�u��������ꐶ�o�Ȃ������邵�Ă���v�Ɩ���������Ə����܂����B
�ق�x�ߐl�̖��Ⴝ���i��a�����̉��ƂƂ�����N�ɓn��x�������Ď���̎������₵�������s�䓙�̎q�������ꑰ�j�́@
�z�K�̐l�����ɂ� �o�_�����l�̎������ɂ�����疜�ȁ@�X�P�[���̏����ȓz��Ȃ̂ł��B�Ƃ������������
�L�I�����@����������ɂ��艟�����ā@�a���̗��j��c�߂������l�Ȃ̂ł��B
�����������n���l�ŏo�_������|���ďo�����@���������̎x�z�K�����Ƃ�������O�ꂵ�ĉB�����߁@
���������̑c��͓V�㐢�E����_�l���n��Ɏg�킵���_�̎q�̎q�����Ȃ�ā@�ł����グ�ā@
�l�����瑸�h����悤�Ƃ����̂ł��˂��B���܂��˂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̒��ł��B�_�Ж��̊z�ɂ͔ڎ��������Ă��邽�߁@���͏���_�ЂƏ����Ă��܂��B
���������̋��y�̉p�Y���J��_�Ђɂ���Ȕڎ��������Ȃ�āB��߂܂��傤��B
�ڎ��Ƃ����Γ����̎x�ߐl�����͎������������E�ň�ԗD�ꂽ�������Ǝv������ł��āA(���ł������ł���)
���ӂ̖�����ؑ��ƌĂс@�ڎ��⓮���̎��Ăĕ\�L���܂����B
�䂪���̘a�����ڎ��ŕ\��������@���}�g���ɔn�̎��Ă���@�P�ޏ���P�c���̂��Ƃ��q�~�R�Əȗ�����
�ڎ��ŕ\���Ă��܂����B���̔ڎ�����N���o�������݂ł��@���肪�������Ďg���Ă�����j�w�҂�@
�n���̋���ψ���̔n�����������܂��B
�����Ɠ��{�l�Ƀv���C�h�������Ăق������̂ł��B
���Ȃ݂ɓޗnj�����s��K�˂����Ɂ@���̒��ɑ傫�ȊŔ�����u�q�~�R�̗��v�Ɣڎ��ő傫�������Ă���
���R�Ƃ��܂����B���{�l�̃v���C�h���̂ĂĂ��܂���˂��B
�]�ˎ���ɓ��얋�{�ɗ������N����ʏ��g�߂������Ƃ��Ɂ@�e���ɘa���̂��Ƃ�ڎ��ł����Ă���@����ɗ����������{��
�g�߂�ǂ��Ԃ��@�����������e���������Ă��ď��߂Ėʉ���Ƃ����܂��B���{�Ƀv���C�h���������̂ł��˂��B
����̈ꕔ�̔n���ȗ��j�w�҂⋳��ψ���̐l�����������͕����ā@���{�Ƀv���C�h�������Ăق������̂ł��B
����_�Ђ͂ƂĂ��킩��ɂ��������ł��B���̐l�ɕ����Ă��F�������Ȃ��āA��J���܂����B
�����Ŏs�����̊ό��ۂɕ����ɍs���Ɓ@�Ȃ�Ǝs�����ׂ̗ɂ���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̗���ɂ��邱����܂�Ƃ����{�a�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ��ڎ����g���Ă��܂��B���������̌ւ鋽�y�̉p�Y�Ȃ̂Ɂ@�Ȃ��ڎ����g���̂ł��傤�B
�������̌��͎ҁA�E��b�̕s�䓙��Ɂ@�C���g�����̂ł��傤�B
�������������ɂ�߂܂��傤��B�@�V�c���x�𗘗p���Đ�N�ȏ㎄�����₵�ā@���v���ނ��ڂ��Ă��������Ƃ₻�̎q����
�߉q�ƂɋC�������̂́B�����Ɠ�����O�̎����g���܂��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̊��ɂ��Ă����͏o�_���Ƃ̗��ؖ�ł͂���܂���ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�̉����̐�͏o�_���̏��킬�ł͂���܂���ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
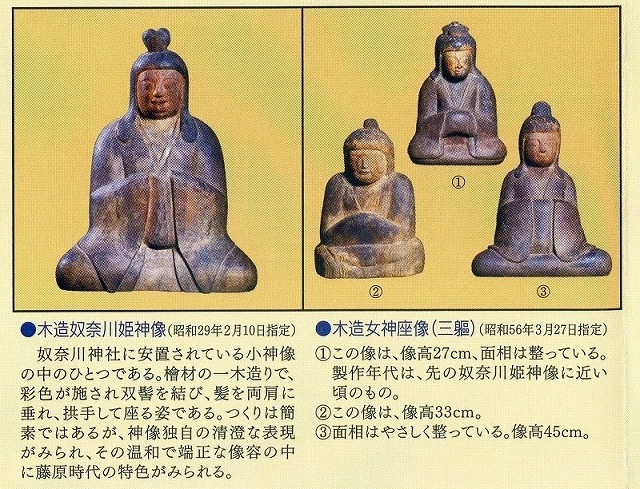
����P�̖ؑ��ł��B���̐_�Ђɓ`����Ă��邻���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�z�K�Ɛz�K���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ȑO�M�B�R�������Ă������@�z�K�ΔȂŎԒ������܂����B
���N���Ă݂�ƌ̒��ɏ��̐l�������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�߂����U�����̐l�Ɂu���̕��͂ǂȂ��ł����v�ƖK�˂Ă��قƂ�ǂ̕�������������܂���ł����B
�N�z�̕��ɕ����Ɓu���̕��͏���P���Ǝv���܂��B�ߌ��̌�P�l�Ƃ������Ƃ����m��܂���v
�Ƃ���������Ă��܂����B
���ƂŒ��ׂ�Ƃ�͂����P�ł����B���䖼���̕��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�܂��z�K��Џ�Ђ�K��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����z�u�}�ł��B�L���ł��˂��B�z�K��Ђɂ́@�ǂ̎Ђɂ��{�a�͂���܂���B��R�����_�̂Ȃ̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�卑�傪�J���Ă��ā@���䖼���̕��_�Ə����Ă���܂������@����͂܂������ł��B
�卑��(���疵��)�͕��ł͂Ȃ��@�����(���d�g�Ðg)�����Ł@����P����ł��B
��Ր_�́@������䖼���Ɓ@���̉��l�Ƃ�����@����l���P�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͉��ЏH�{�ł��B
���Ђ͏t�{�ƏH�{�̓�Ђ���܂��B����͏o�_��������́@�t����ՂƏH����Ղ̓��@���s�����o�_�ōs����
�S���̍����������W�܂������Ƃ��@�e�����Ă���Ƃ����Ă��܂��B�����ČÑ�o�_�����ł́@�t���̓��ƏH���̓���
���ꂼ��1�ΔN��������Ƃ����Ă��܂��B�܂�1�N��2�ΔN�����̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
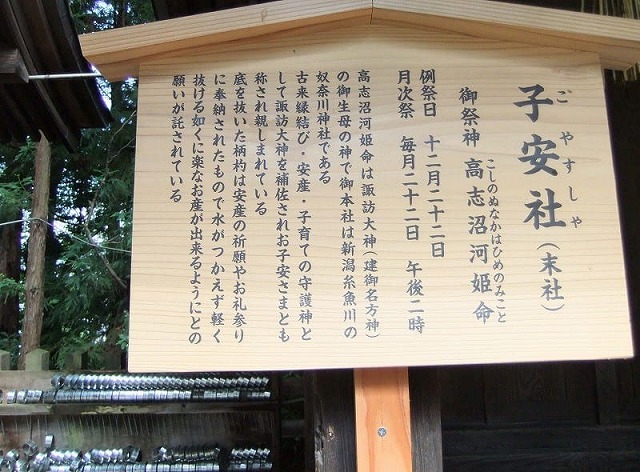
�����ɂ͏���P���J���Ă��܂����B���Y�̐_�������ł��B
���ʈ̐l�̕�e���J����Ɓ@���Y�Ƃ������̕a�C�̐_�Ƃ���܂��ˁB
��C�̂��ꓰ���J���Ă����x�R�̎����@�����ɂ́@�����̃I�b�p�C�̂ʂ�����݂��R�ς݂���ĕ�[����Ă��܂��B
���Y�Ƃ��������悭�o��悤�ɂƂ��@�����̓�����̕����Ƃ����낢�낢���ā@��������̕�����[���Ă��܂��B
���s�҂̂��ꓰ���ꏗ(����Ƃ���)���J���Ă���ޗnj��V�쑺�̕����(�͂͂��ǂ�)�����Y�̐_�Ƃ���Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ЏH�{�ɂ͂Ȃ�Ƃ��́u���ė�(���Ă����Â�)�v���J���Ă��܂��B�o�_�̍�����̒k����
���䖼�����R�e���p���ɂ�������ƋL�I�ɏ����ꂽ�����ł��B�Ƃ������Ƃ́@�N������Ȃ���J�点���̂�
����������܂���ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�H�{�̎萅�͉������Ă���@���C���o�Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Џt�{�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���������h�Ȍ����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�������̐��ʂ͕��a�ł��傤���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ��z�̏���P���J���Ă��܂��B���u�Ƃ͉z�̂��Ƃł��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
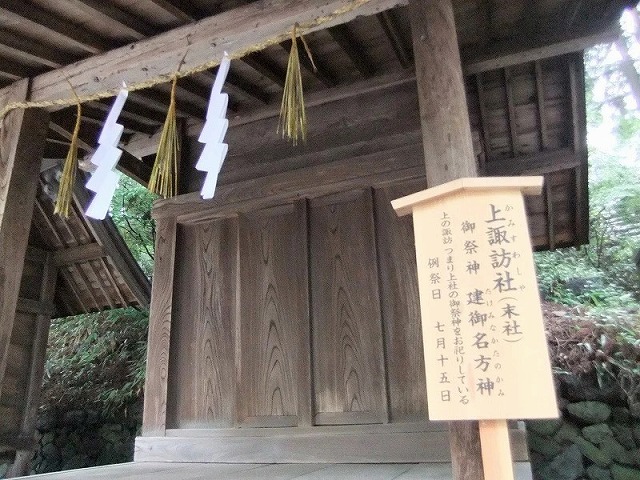
������䖼�����J���Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�z�K�Βn�����J�������o�_���@�@����3�֑���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�U�V�@�@�z�K�n�����J���o�_���@�@����3
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�o�_�������Ƃ���M�Z�l
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ʔ����V���L���������Ă��܂��B
���쌧����s�z�̉z�q�_�Ђ̎�Ր_�́@���{�{��(�݂ق�����)�������ł��B�Ñ㕶���ŏ����Ă��邻���ł��B
�ꏊ�����炵�ā@�����ɂ��z�̍��Ƃ������肻���ł��ˁB
���]�s�ɂ��z�̐l����������ڏZ���Ă��Ă����̂Ł@�Îu�Ƃ��Îu���Ƃ������n������������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
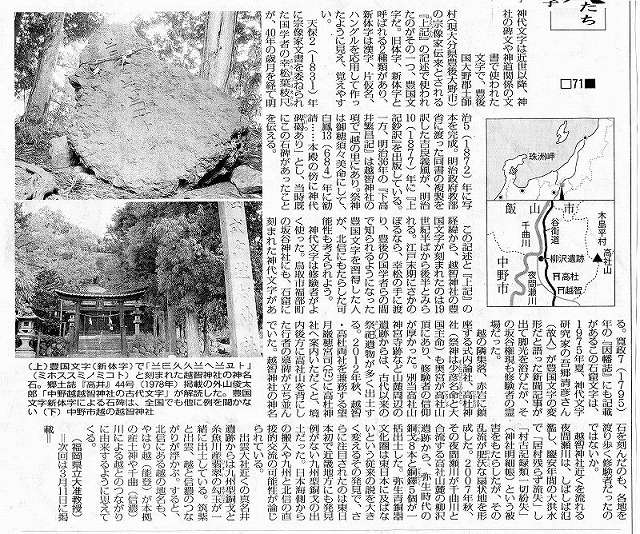
���{�{��(�݂ق�����)�Ƃ͎����Ə���P�̖��ł��B�L�I�ɂ͐�ɏo�Ă��Ȃ����O�ł��ˁB
�������o�_���ɂ́@���Ȃ��݂̌�P�l�ł����B
����傪������ɎE���ꂽ��@���]�s���ۊւɎc�蕃�̎����(���d�g�Ðg)���J��ꐶ���I����ꂽ�P�ł��B
�o�_���ɂƂ��Ắ@�Ȃ��݂̐[����P�l�ł��B
�Ƃ������Ƃ͂��̂�����ɏZ��Ł@�J���̂́@���䖼���ɕt���]���Đz�K�Ύ��ӂֈڂ�Z��
�o�_���̎q���ƍl�����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�o�_���ƌ䒌�̂���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
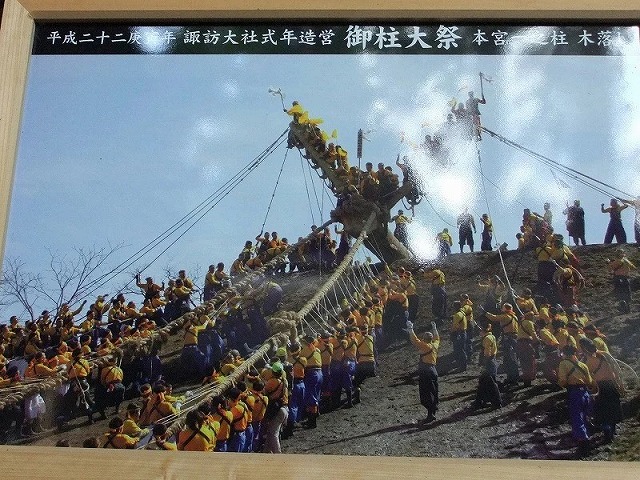
��Ђ̋����Ɍ䒌�Ղ̐����Ŕ�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�H�{�̌䒌�ł��B
�z�K��Ђ̌䒌�Ղɂ��ā@���̉��{���Y���́u�ꕶ�l�̌�������������̂��v�Ƃق߂������Ă��܂����B
����������͈Ⴂ�܂��B
�o�_���̌�������������̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
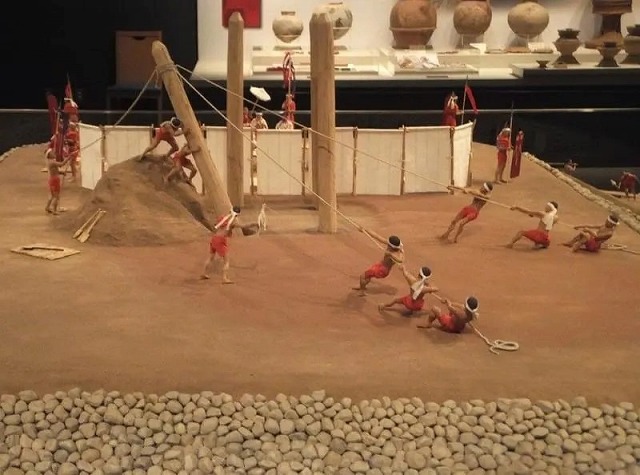
����͏o�_���̑��V�ɕ��u��Ɍ䒌�����Ă�Ñ�o�_�̐l�����ł��B
�q�̋{�̌��݂Ǝv���܂��B�Ȃ�Ǝ������i�Ȃ̂ł��傤�B
�o�_���́@�Õ��z���Z�p�ɂ��@�y�؍H���ɂ������Ă��܂����B�y�t���ƌĂ��l�����ł��B
��a�̑剤�̋��啭��́@�قƂ�Ǔy�t���̐���ł��B
�����̎ʐ^�͏o�_�퐶�̐X�����قŎ����B�e�������̂ł��B
���̃u���O��2014�N6��20���̋L���ɏڂ����ڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����͋ߔN���@���ꂽ�@�Ñ�o�_��Ђ̉F����(��������)�ł��B
���a����1.5m�̋���Ȋۑ��ނ�3�{���˂ā@���������ȉF�����Ƃ��ā@����94m�̋���_�a���x���Ă��܂����B
�F�����Ƃ́@��Б����9�{�̒��̂������ʂ̍ȑ��̒����̒��Ł@��O���ւ͂ݏo���Ă��Ă��̒���
���܂ŐL�тČ������x���Ă��܂��B
���o�_�Ñ���j�����ق̃p���t���b�g�ʐ^�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����_�a�̖͌^�ł��B
���o�_�Ñ���j�����ق̃p���t���b�g�ʐ^�ł��B���ۂɂ��̖͌^���W�����Ă���܂��B
��������̂��̂Ɂu�_���A�a��A���O�@(����ɂ��傤����)�v�Ɖ̂��Ă��������ł��B
�����̓��{��̍����̌������@�_�B�̏o�_���(���͑��Y�̑��ň�Ԃ̈Ӗ��ł�)�œ�Ԗڂ��@��a�̑啧�a�A�O�Ԗڂ�
���s�̑�ɓa�@�Ƃ����Ӗ��������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̋���_�a���ł����̂́@716�N�ŋ��o�_���Ƃ̌��ƂƐ_��b�Ƃ��������o���ā@�卑����J��
��_�a�����Ă܂����B�L�I�ł́@������̑㏞�Ƃ��ā@��a���������ĂĂ�����ƉR�������Ă��܂����B
�䒌�����Ă�Z�p�⋐�啭��c����y�؋Z�p�́@�o�_��������̂��̂ł��B
���̏o�_�̖��̌����@�䒌�_����������̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�o�_�����̍����@�K�m�_�O�_�̂���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ñ�o�_�����̍����́@�K�̐_�O�_�ł����B�܂�N�i�g��_�A������(���Ђ�)�̃~�R�g�A����ɍc�q�_��
�T���^�F�ł��B
���Ȃ݂Ɂ@�T���^�Ƃ͌Ñ�C���h�̃h���r�_��ŕ@�̑傫���Ƃ��@�̒����Ƃ����Ӗ��Ł@�܂荡�̃q���h�D�[��
�u�ې_ �܂�@�K�l�[�V���v�̂��Ƃł��B���オ�������Î��L�Ȃǂł́@���c�F�ȂǂƏ�����܂������B
���ꂮ����@���̐_�ł͂���܂���B
�N�i�g��_�́@��_�R(�������݂��)���J���܂����B�����đ�_�R�́@���̊Ԃɂ���R���ɏW�܂������N�U�V��ǂ���
�u��R(��������)�v�Ȃ�đ����ۂ����O�ɕς����Ă��܂��܂����B�{��R�̐^���������̂ł��傤�ˁB
�����č��ł́u��_�R�_�Ёi�������݂�܂���j�v�����ɂ��̖��O���c���Ă��܂��B
��_�R�_�Ђ̋������Ɂ@�u�s�҂̓��o�R���v�A�u�O�ؕ��o�R���v������܂��B
��2013�N6��12���̋L���ɂ���_�R�_�ЖK��L���ڂ��Ă��܂��B
�������̃~�R�g�͂���������R(���Ђ߂��)���J���܂����B��������̗��R�̗��n���ʐ}�ɂ��u�������R�v
�Ə�����Ă��������ŁA�����N���@�u�O�r�R����ׂ���v�Ȃ�Ē��Ȗ��O�ɑւ����̂ł��傤�B
2500�N���������@�o�_���ɐe���݂̂��鍲�����R�����ė~�������̂ł��B
�����čc�q�_�̃T���^�F�́@�@�������R���Ȃ킿�@�o�_�k�R�̕@���R�i�͂Ȃ�������j���J���ċ��܂��B
�C���h�ɐN�������A�[���A�l�ɉ����o����ā@��C���h����ړ����J�n�����h���r�_�l�̈�h��
�S�r��������o�C�J���ւ��ǂ蒅���A�u���A�[�g�����S���ƍ������J��Ԃ��Ȃ���@�A���[�����
������@���{�C��쉺���ā@���{�ɏZ�ݒ����A���S�̎����ɐ쉺���Ł@������z�����Ƃ����Ă��܂��B
�i���֖؉_�B���@�Î��L�̕ҏW���@���̒����@�匳�o�Łj
���Ȃ݂Ƀh���r�_�l�̈ꕔ�́@�C��n���̃X�������J�ɈڏZ���Ėk���ɏZ�ݒ����^�~�[���l�ƂȂ�A����
�X�������J�̑����l��V���n���l�Ƃ̊Ԃœ���𑱂��Ă��܂��B�����X�������J�œ����Ă���1980�N�㔼��
���т��ѓ��킪�������ĊO�o�֎~�߂��o�đ����̐l���S���Ȃ��܂����B
�h���r�_��ɂ͂��̂ق��@�Ñ㐻�S�@�̃^�^��(��������)��@�J�l(�S)�Ȃǂ�����Ƃ������Ƃł��B
���ڂ����́u�퐶�����Ɠ�C���h�@���W�@��g���X�v���Q�Ƃ��Ă��������B
�o�_�����̏t���ՁA�H���Ղɂ͉������e�n���獋�����W�܂�@�喼���̎i�Ղ̂��Ɓ@�N�i�g��_���͂���
�K�m�_�O�_�ɋF�������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s���̐��R���猩���@��_�R(���̃_�C�Z��)�ł��B�N�i�g��_�̏h��Ƃ��ꂽ�R�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���o�_���Ƃ̋{�a�̂��������]�s��뒬�̍���ɂ́@�J���X�V��L�ꂪ����܂��B
�Δ�ɂ́u��R��q���匠���v�Ɠǂ߂܂��B
�����͋��o�_�����{�a�̂��������̒n�ɂ���A�����̍K�m�_�O�_�̂����N�i�g��_���Ղ��Ă����_�R(���̑�R)��
�y�q�����ꏊ�܂蓌���ƌ��Ƃ̗��^�i�ꂢ���@�������s���y�q���ł�����L��)�������Ǝv���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
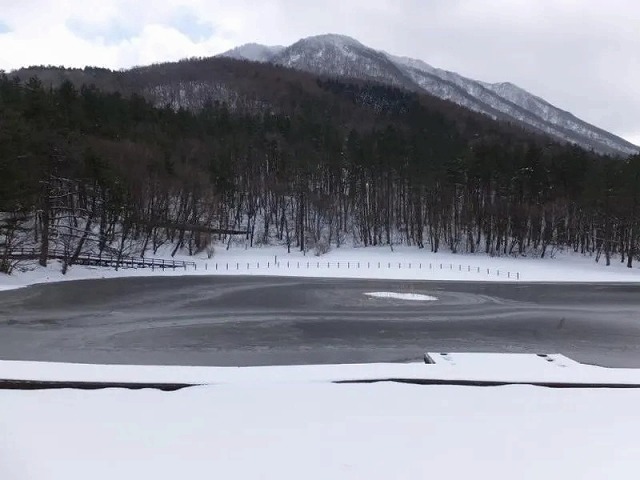
�����̎R�ł��B�O�r�R�Ȃ�Ē��Ȗ��O�ɕς�ʂĂ܂������@�u�l�G�̏h ���Ђߖ�v�Ȃ�č����h�ɂ̖��O�Ɏc���Ă��Ĉ��S���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�s�̏o�_�_�ޔ��_�Ђ̒����̐��ʂɂ́@���c�F���J��@���R(�͂Ȃ�������)�������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�̌Â��_�Ђ̈�@�ӕ۔��_�Ћ����ɂ͍ǂ̐_�ƎR�̐_���J���Ă���܂����B
�ǂ̐_�̓T���^�F���ω��������̂ŁA���c�_�ɂ��Ȃ�܂����B
���͂���⓻�Ɉ��u����āA����̐N����h������A�T���^�F�̕@�̌`����j�����g��\���Ēj���a���̐_�A�q���ɉh�̐_�Ƃ���܂����B
�R�̐_�Ƃ̓N�i�g��_�̂��Ƃł��B�N�i�g��_�͈ɜQ����(�C�U�i�M)�̃��f���Ƃ���܂������@���オ�����R�_�̖�(������݂݂݂̂���)�Ƃ�
�Ă��悤�ɂȂ����Ƃ����B(�J�˒�F�@�K�m�_�Ɨ��@�匳�o��)
�L�I�ł́@��R�_�̖��͍炭��؉ԕP(�C�j�G���Ƃ̊ԂɃC�N���剤�����ÕP�̂��Ƃ��L�I�͂������������܂���)�̕��e�Ə����ꂽ�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�_�s�̒��l�_�Ђ͑�Z��喼���@�������b�Ö�(����݂����݂�)���J��Â��Č��Ђ���_�Ђł��B
���̐b�Ö쉤�͐��o�_���Ɛ_��b�Ƃ̕��Ł@�掵��剤�͓��o�_���ƌ��Ƃ̓V�̓~�߉�������
�攪��剤�����o�_���Ɛ_��b�Ƃ̕��Ł@�ߌ��̔��疵���i�L�I�ł͑卑��Ə����ꂽ�j�ł��B
�Ñ�o�_�����ł́@���o�_���ƌ��ƂƐ��o�_���Ɛ_��b�Ƃ��@�剤�ƕ��������݂ɏo���Ă����̂ł��B
�܂�b�Ö쉤�́@�卑��[���疵���̑c���Ȃ̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
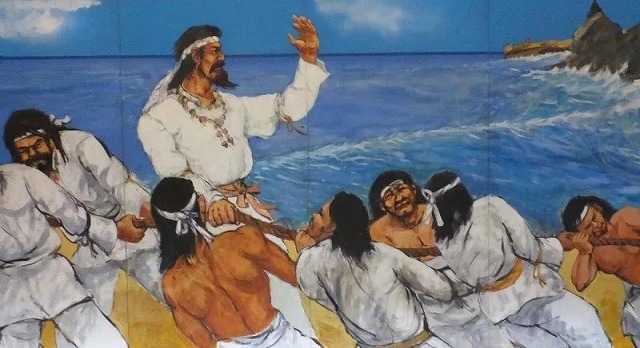
�Ж����Ł@�b�Ö�̐_�̂��D�����Ƃ��Ɏʂ����Ă����������u�����A�����i���ɂ��@���ɂ��j�v�Ƌ���
�������̐_�@�b�Ö쉤�̂��p�ł��B�z�̍���V������@���y���������Ƃ�����_�ł��B
���̒ʏ̂��ɂт����̎���ɏo�_�����͗̓y���ő�ɍL�����Ƃ����ā@���]�s�̑勴��ɂ����鋴��
���ɂт��勴�Ƃ������炢�@�o�_�l�ɂ͂��Ȃ��݂̌Ñ�o�_���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̒��l�_�Ђ̎O�����͌Â��`�̒����̈�Ł@�K�m�_�O�_���J��`�ł��B
�^���N�i�g��_�A���������̖̂��A�E�����c�F��_���J��Ƃ����Ă��܂��B
�����Ă��̒����`���́@��a�ɂ��ڂ���ā@鰏��ɂ����ꂽ��Ԗڂ̃q�~�R�̉F���L�ʕP��
��B�������̃C��G���i���薼�͐��_�j�Ƃ̊Ԃ̕P�@�g���P�i�L�����P�Ł@�L�I�ł͖L�L���P�Ƃ��V�̓p�Ï��̖�
�Ə����ꂽ�P�c����鰏��ő�^�g���Ə����ꂽ�O�Ԗڂ̃q�~�R�j����a�Ō��ǂ݂̐_���Ղ����@�w���_��
�i�ޗnj��N��s�O�ւ̑�_�_�З���j�̎O�����ɂ��Ȃ��Ă���̂ł��B
���w���_�Ђ�2015�N1��29���́@NO30�̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�E���ɂ́@��(���Ȃ�)�̐_���J���Ă���Ə����Ă���܂��B����͓��̕���_��W���̓�����A�܂��������J����
���c�_�̂��Ƃł��B�܂艎�c�F���J���Ă���̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̐Α�����ɍڂ��Ă��܂��B���̌`�͂Ȃ�ƐM�B�e�n�ł悭���铹�c�_�̈�v�w�_(�߂��Ƃ���)�̑��ł��B
�܂�v�w�a���Ǝq���ɉh���肤�_�Ł@���c�F�̕ό`�ł��B
���c�F�͍K�m�_�O�_�̒��ł͎Ⴍ�ė͋����A�����ĕ@�̌`���j�����g������ɂȂ������������ƍl������
�v�w�a���A�q���ɉh�̐_�Ƃ��ā@�܂�����̐N����h���_�Ƃ��ā@���낢��Ȍ`�Ŋe�n���J����悤�ɂȂ�܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ă�����v�w�a���A�q�����A���Y�̐_�������ł��B�j����Ə�����̌`�̐��u���Ă���܂��B
�܂肱������c�F��_���J���Ă���̂ł��B���̐�������Ȃ���@���肢���Ă��������Ƃ����Ă���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ɐ���{�@�֑�_��
�ɐ��ň�ԌÂ����Ђ̂���_�Ђ��֑�_�Ђł��B�ɐ���{�͈ɐ��_�{�ł͂���܂���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�֑�_�Ђ̉��c�F�ƓV���폗(���߂̂�����)�̖�
��a�̏o�_���ƕ��Ƃ̓o���Ƃ��番�Ƃ����@�F���y���Ɓi�����Ƃ����j�ɂ��A�͂₭����ɐ��Ɂu�֑�_�Ёv
�i���������݂₵��j�����Ă��ā@�o�_�̃T���^�F���J���Ă��܂����B
���̌��a���ꂪ�i�ނɂ�ā@�C�N���剤(���m)�ɒǂ�ꂽ�L�����P�́@�ɐ��ɓ���
�F���y���Ƃɕی�����߂��Ƃ����B
�L�����P�́@鰏��ɏ����ꂽ�L���ȓ�Ԗڂ̃q�~�R(�F�������̖L�ʕP�j�̖��ł��B
�i�����Ȃ݂�鰏��ɏ����ꂽ��Ԗڂ̃q�~�R�́u���̕P�c��(�Ђ߂݂�)�������ɗ��ƒ��������헐�����܂�a���ɕ��a��
�K�ꂽ�v�Ə����ꂽ�̂��@�L���ȃ����\�P�ł��B��鉤���攪��̃N�j�N���剤�ƈ��Ƃ̃N�j�A���P�̖���
���Ɠ����c�c���q�̐��b�Ł@�O�֎R�̑��z�̏��_���J��ޏ��Ƃ��Ďi�Ղ��@�e�n����吨�̍����������ɏW�܂����Ƃ����܂��j
������鰍��̘a�����ݕ����̒����ɂ��L�ʕP(�q�~�R)�̌�p�҂Ɏw�����ꂽ�Ƃ������Ƃ�鰂ɔF�߂�ꂽ�a���̏����Ƃ������Ƃł��B
�����Ĕޏ���鰏��ɏ����ꂽ�u�g���[��^�v�̂��Ƃł��B�����a����鰂̑�����Ԃ������̂Ł@�w�������ΐ��^�����̘a�������ł��B
�������C�N���剤���a���ꂷ��Ɓ@��������̓y�Y��t���ā@鰍��̘a�����ݕ����̒�����鰂֑���͂���
鰂Ƃ̊W��f���܂��B�����Ďז��ɂȂ����ٕ�Z���̖L�����P�Ɏh�q������E���܂��B
�ޏ��̖S�[�͑�a�̓o���Ƃɉ^��ďo�_���̓y�t���ɂ��@�z�P�m�R�Õ�(�ޗnj�����s)�ɖ�������܂����B
���z�P�m�R�Õ���2015�N1��29���́@NO29�̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�L�����P�͉F�����痈��ꂽ�P�Ȃ̂Ł@�ŏ��͉F����(������)�̖��ƌĂꂽ���@�C�N���剤���s����ǂ��Ă���Ƃ����̂�
�F�����ł͂܂����̂Ł@�E�Y���ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B
�L�I�ł͓V���폗�̖�(���߂̂����߂݂̂���)���@�����J���ē��[�����c�F�Ɍ����ėU�f���A
���c�F�͔ޏ����ɐ��֘A��čs�����Ə�����܂����B�Ȃ�̂�������B
���ɐ��̍���{�֑�_�Ђ́@2015�N10��7���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�M�Z�̍��̍K�m�_(�����̂���)�̂���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
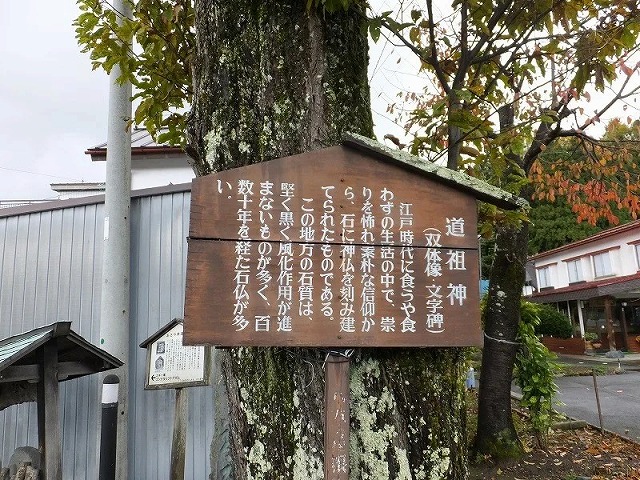
�M�B�R���Ŕ��n���̗[���U���Ō����������n���̓��c�_�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
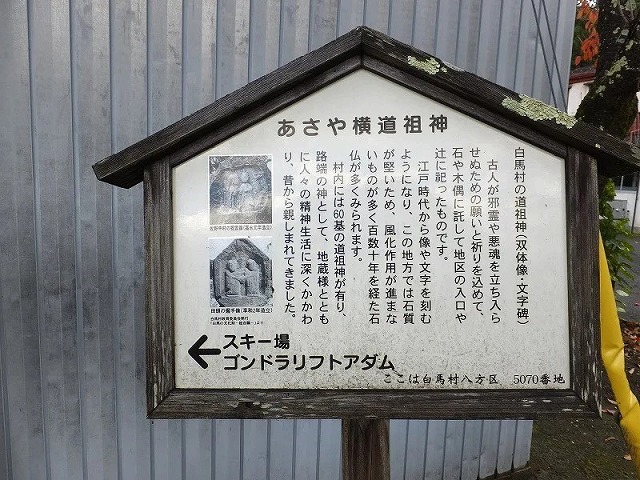
���c�_�̐����Ŕł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
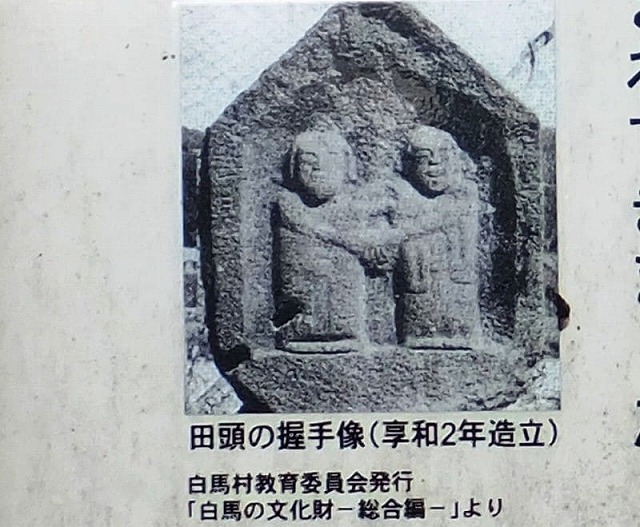
�c���Ƃ����ꏊ�̎般��v�w�_���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������͐�قǂ̏o�_�s���l�_�Ђ̍K�m�_�O�����̎般��v�w�_���ł��B��������ł��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
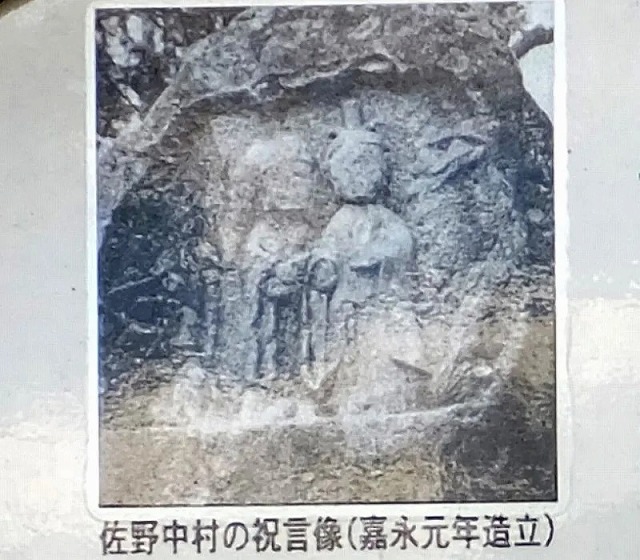
������͍��쒆���Ƃ����ꏊ�̏j���v�w���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����炪�@���n���̓��c�_�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Α��͎����荇���Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂�般��v�w�_���ł��B
����ƒ��������j�������̑����������@��[����Ă��܂����B
����͂܂��������c�F�ł��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ƃ������ƂŁ@�M�Z�̍��ɂ͏o�_���̕��K�������@�F�Z���c���Ă��邱�Ƃ�������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�M�Z�̓��c�_�̎ʐ^�ɂ��Ắ@��R�̎ʐ^�Ɖ�����@�u�K�m�_�Ɨ��@�J�˒�F�@��{�o�Łv
�ɏڂ����ڂ����Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���z�K��Ђ̕���́@�̂��Ɍ��䖼���̐��܂�̋��̏o�_�ɗ��A�肵�܂����B
�o�_�s��쒬�����̌䖼���_�Ђł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ñ�o�_�����䂩��̒n��K�˂ā@�g�b�v�y�[�W�͂�����ł��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�F��O�R�ƌF��Ó��A�����Đ_�������̓�
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�k���ɏZ�ޗF�l���@�ŋ߃c�A�[���s�Ł@�F��O�R�������������ł��B
�������� ���E������Y�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�̎Q�w���͂��ׂĕ����܂����B���ɌF��Ó����ӘH�i���ւ��j�A
���ӘH�i�Ȃ��ւ��j�A�ɐ��H�i�������j�͂��ׂČF��O�R�����݂܂��B�����đ�����퓹�͌F��{�{��Ђ��S�[���ł�����
(�t��)�X�^�[�g�ł�����܂�(����)�B
�F��O�R�Ƃ� ����F�l���������@�F��ߒq��ЁA�F�쑬�ʑ�ЁA�F��{�{��Ђ̂R�̐_�Ђł��� ���̂������
�I���O�R���I���ɉ䂪���ɓn�������`���l�������J���Ă��܂��B
������̐_�Ђ̎�Ր_���F�쑬�ʂ̖��i�͂₽�܂݂̂��Ɓj�Ƃ����܂����A�a�����`�����i�ɂ��͂�Ёj�������͉Ζ�����
(�ق�����)�Ɩ�������`���l�����̂��Ƃł��B�L�I�ł͑f���j(�����̂�)�Ƃ������Ă��܂����B
�����̎q�������́@�`�����̑����̂�@���ʂ̖��ƌĂт܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���E������Y�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�̒n�}�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�I���O�O���I���A�����͑吨�̊C�������������A��� �ŏ��������̑��c�s�\�ҊC�݂ɏ㗤�� �a�����u�Ζ�����i�ق�����j�v
�Ɩ����܂��B���O�ɒ����ȕ����́u���ڃz�q�v���o�_�����Ɏg�킵�ā@�㗤�̋������t����Ƃ��������Ȉ��I�݂����Ă���ł��B
���Ȃ݂Ƀz�q�̎q�������̏o�_��Ћ{�i�ł��B�㗤���������͏o�_�ɏZ�݁A�o�_���Ƃ̍��ƕP��W�� ���j�����܂�@�\�ҁi���������j�v
�Ɩ��t���܂��B�����̕��̖������҂ƌ������̂Ł@�u�ҁv��t�����̂ł��傤�B
�������o�_�����̉��@�܂�a���̉��ƂȂ����ł���Ă��������́@�����̏o�_�����̎剤�ƕ�����S���҂ɂ��悤�Ƃ��܂��B
�����̏o�_�� �剤���疵�i��E���͑喼���Ł@�L�I�ł͑卑��Ƃ��单�Ƃ��喼���A����Ə����ꂽ�j�ƕ����̔��d�g�Ðg
�i��E���͏��F�ŋL�I�ł͎����Ƃ������F���Ə����ꂽ�j���z�q��C�������ɖ����ėU���H���ĎE�Q��
�������o�_�̉��ɂȂ낤�Ƃ��܂��� �����̑g�D����������Ƃ��Ă��� ���ꂪ�ʂ������Ɂ@��������`���A�����܂��B
���喼�����H�E�Q���ꂽ���ړ��A�Ə��F���H�E�Q���ꂽ�u�Â̊≮�̖K��L���͂��̃u���O��2013�N3��18���̋L���ł��B
���������㗤�����Ό��\�ҊC�ݖK��L���́@2014�N4��24���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�A������������ �`�̎n�c��� �X�Ȃ鎑���ƊC��������Ⴂ �s�V�s���̖�����߂�ӂ�����Ęa��(�H����)�֓�x�ڂ̏o�q�����܂��B
�����č��x�͋�B���ꌧ�̕��t�ɏ㗤���܂��B
���x�� �a�����`�����i�ɂ��͂�Ёj�Ɩ���� �o�_���Ƃ̋�B���ƁA�@���Ƃ̎O�o���̖����s�n���P�i���������܂Ђ߁j��W��
���j���o���i�ققł݁j���������܂��B���Ȃ݂ɂ��̂��ƒ����̕䉮�P�����܂�A�o�_�Ő��܂�O��ֈڏZ���A�����đ�a�ɈڏZ����
�����̒��j�\��(��ɍ���R�Ɖ���)�ƕ䉮�P�͌������܂��B
��l�̂̊Ԃɐ��܂ꂽ�u�V�̑��_�v���@�o�_���Ƃ̑�a���Ƃ̓o���Ƃ��ΉƂ̋��͂Ł@�����a�̑剤(��������)�ɂȂ�܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����@�����̎��j���o���́@��B�������Ƃ��N������ ���̎q�������������{����̂ł��B�܂蓌���Ƃ́@�����̒��j�\�҂̎q��
�����̑��̓V�̑��_����a�̓o���Ƃ��ΉƂ̏������Đ��������@��a�̈�鉤�����@���j�̎q���̋�B�����Ƃ��|���Z�팖�܂ł��B
���̎j���͋L�I�ɂ͏����Ȃ����߁@�䉾���̊C�K�F�ƎR�K�F�̌Z�팖�܂̘b�ɂȂ�܂����B
�Ȃ��Ȃ玝������́@���Ō�����������Ȃǁ@�Ȃ��������Ƃɂ��Ď��������̑c��͓V�ォ�獂���̕�ɍ~�Ղ������Ƃɂ���
���������̑c�悪�@�n���l�̐����������Ƃ������Ƃ�O�ꂵ�ĉB�����̂ł��B�o�_�����Ȃ�ĂȂ��������Ƃɂ����̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����165�N���� ��B�������Ƃ́u�F�����v���̍c�q �����̌ܐ�(����)�A���̒���(���Ȃ���)�A�O�ѓ���(�݂�����)��
��ꎟ�������J�n�A�I�m��͌������a���肵�悤�Ƃ��܂����B
�������I�̍��� �����a�剤 �V�̑��_�� ���Ⴂ�̒퍂�q���i�������炶�j�̒n�ՂŁA���q���̎q��������
�苭�������A�}������ �ܐ��͐펀�A�}�R�_�Ђɑ����܂��B�a�̎R�s���ĎR�_�Ђ��Â��đ傫�����h�Ȑ_�Ђł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�}�R�_�Ђ̗��h�Ȑ_��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
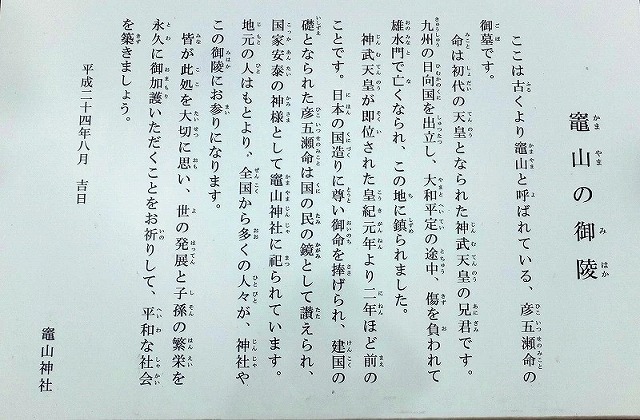
�ĎR�_�Ђ̗R�������ɂ́u�_���V�c�̌Z����Ր_ �v�Ƃ�����Ă��܂��� ���Ȃ����R�ł͂���܂���ˁB
�킽������ɑ�a���肵�ĉˋ�̑�N�_���̃��f���ƂȂ�̂ł�����B
���}�R�_�ЖK��L��2015�N9��8���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����c������тƎO�ѓ������͈�U�I�m�삩��ދp���A�F��։��F����k�낤�Ƃ��܂��B
�����������ł���a�̈�鉤���z���̕��l�����ɍU�߂��� ��������ꂸ��ނȂ����S�ȌF���̒��F�ɗ��܂�܂��B
���̒n�� ��ɌF��{�{��ЂƂȂ�܂����A�����̑�^���ŏ\�Ð쑺����œI�Ȕ�Q�����Ƃ��� �F��{�{��Ђ�������Ė����Ȃ�
���̌㍡�̏ꏊ�ɍČ�����܂����B���{�̐Ւn�ɂ͋���Ȓ��������� �u����i������̂͂�j�v�ƌĂ�č������n�ł��B
���̂Ƃ��̑�^���Ł@��œI�Ȕ�Q�����@��R�̏\�Ð쑺�̑��l�� �̋����̂Ă� �F��Ó����ӘH����� ����R������֏o��
�k�C���ɈڏZ���܂����B�k�C���V�\�Ð쑺�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ɂ͍��͋���Ȓ����������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����ŌF��Ó��̎ʐ^�ł��B�܂����ӘH(���ւ�)����
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH�͍���R����F��{�{�������܂��B�������c�O�Ȃ���a�̎R���A�ޗnj��̐E���̒��x���Ⴍ�@���E��Y�̎Q�w����
�قƂ�lj�Ă��܂��܂����B������Y�ɑ���F�����Ⴂ�̂ł��ˁB
���ӘH�����̎Q�w���Ɠ��l�@�قƂ�ǂ��A�X�t�@���g�̗ѓ��������Ł@���ł����열�_�X�J�C���C�����������܂��B
���ۂɃA�X�t�@���g�̓��H������Ă���Ɓ@���E�̎R�̒��Ɂ@������ł���������邱�Ƃ��ł��܂��B���ɓ��������܂��B
���������C���Ȃ��̂Ł@�ѓ��͍���Ă��@�F��Ó��̕����A�����͂��낤�Ƃ��܂���B�n���ł��ˁB
����q���͂��낤���Ďc���Ă��܂��B���܂ł̐�̒�������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����q���ł��B��������E�֕���Ɣ���q�x�֍s���܂����@���̓��͐Ⴊ�[���Ĉ�l���b�Z���ɔ��ēr���ň����Ԃ��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�\�Ð삩��ʖ������Ė{�{�������܂��B�ʖ����t�߂��̂̓����킸���Ɏc����Ă��܂��B
�ʖ��W���͂܂��ɓV��̏W���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ʖ��W���̒������ӘH���ʂ�A�����ł͖��Ƃ̉����ŋx�e�ł��܂��B������1���Ԃ��炢�����Ďv����̂ɒy���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̉Ƃ̃o�[�����ł��B�e���r��|�X�^�[�Ɉ������肾���̔�����q�[�����ł��B���̎ʐ^���|�X�^�[�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F��{�{��Ђɒ����܂����B�L���C�ǂ��낪���o�}�����Ă��������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Г�����ł��B�͂��߂�����ɂ͔��@�G(�₽���炷)�����܂��B��ŏq�ׂ܂����@���������������R���ɑ�a�̓o���Ƃ̒n�Ղ�
�֗](�����)�ɓ������@�o���Ƃ̓�����Ό��ÔV�g�Ɋ��ӂ��������R���@�x�߂̐_�b�ɂłĂ��锪�@�G�Ƃ��ĉ��Ό��ÔV�g���Ղ������̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�ɂ͔��@�G�̐Α�������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���ӘH(�Ȃ��ւ�)
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH�͋I�ɓc�ӂ���n�܂�܂������̑唼����Ă��܂��̂Ł@�r���̑�K���q��������n�߂܂����B
�{�{�t�߂̓��̕�͊O�l�ό��q�ł��ӂ�Ă��܂��B
�{�{��Ђ���ߒq��Ђւ̓��Ł@���_�撴�����_�撴�����l�C�̃R�[�X�ŕ����̂͂قƂ�NJO�l�łт�����ł��B
�r���̏����W���ɔp�Z�����������h���{�݂�����@�����߂������l�̎Ⴂ�J�b�v���ł����B�����͘a���Ńg�C�����C�͋�����
�H���݂͂�ȂŃZ���t�T�[�r�X�ŐH�ׂ܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��_���z���⏬�_�撴�͂�������̊O���l�ό��q�ł��ӂ�Ă��Ăт����肵�܂����B���Ȃ݂ɂ��̓��͓��{�l�ɂ�
�قƂ�lj�܂���ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F��ߒq��Ж{�a�ł��B�Ȃ�����͕������̉��킬�ł͂Ȃ��o�_���̏��킬�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���@�G�����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ȑ傫�Ȕ��@�G�����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�G�t���ł悭����ʐ^�ł��B�ߒq�̑�Ɛݓn���̓��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ߒq�w�ɂ͂���ȃ|�X�^�[������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH�͌F���̕l�������܂��B�l�̓��ł��B�������Ȃ���̂�т�ƐS�a�܂��ĕ����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�l�̓�������ĐV�{�s���ɓ���ƕl���q�_�Ђ�����܂����B��������ĎQ�q���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
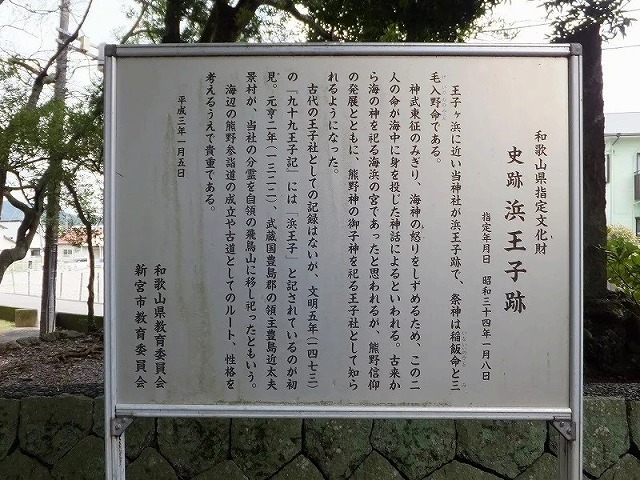
���C�Ȃ���Ր_������ƂȂ�Ƃт�����@�a�̎R�Ő펀�����ܐ��̒킽���́@��тƎO�ѓ���ł��B�L�I�ɂ͐�ɏo�Ă��Ȃ����O�ł��ˁB
�L�I���(��������)�ɂ͂ǂ��炪�Z�Ȃ̂��킩��Ȃ��̂Ł@�����E�}�V�}�W�Ƃ������O�ɂ��Ĕ֗]���肳���A�֗]�F�Ƃ��Ă��܂��B
�L�I���炱�ڂꗎ�����^��������ȂƂ���ɓ]�����Ă��Ċ������@���������s�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����V�{�s���ɂ́@���������Ȃ���̂�����A�����̏㗤���L�O�����Ə����Ă���܂��B�㗤�����̂͏����ł͂Ȃ��@��������
8�ォ9�ソ�����q�������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ӘH�ŏI�͌F�쑬�ʑ�Ђł��B���ʂ̖��Ƃ͂�������`�����Ɩ�����������̂��Ƃł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�ɐ��H
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ɐ��H���唼����Ă��܂��B�n��(�܂���)�����ӂ��������Ŕ��h�s�̊ό��ē����ɒn�}�����炢�ɍs���ƌW���̏�����
�C�̓ł����Ɂu���̂�����̌F��Ó��͂قƂ�Ǎ����ɕς���Ă��܂��B�v�Ƃ���������ā@�B��c���Ă���n������
�R�[�X�̒n�}������܂����B����ȐΏ�̓��͂ق�̏����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�n�������番�ēV��q�R�֏��܂����B�R���ɂ͂Ȃ�ƍ��q��(�����a�剤�V�̑��_�̕��Ⴂ�̒�)���Ղ��Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�R������́@�F��傪���߂��Ă������Ƃ�܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎R���̌i�F���C�ɓ����ā@�������ɂ������q�˂܂����B�F���������Ă��܂������@���P�����̏o���x��������ċP���Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��鉤�����̕��m�����ɃQ����������������� �g�����Ƃꂸ �F���͌��߂��̒��F�ɐw������܂ܓ������ɂ��č�������тƎO�ѓ�������
�Ђ����ɑ�a�̓o���Ɓi�o�_���Ƃ̑�a���Ɓj�֖��g�𑗂� ��a����̓��ē����肢�o�܂����B
������a�� ��鉤�Ƃ���܂�A�����������������Ă����̂� ���̏�Ԃ��ƂƋ��ɕ��肵�悤�ƍl���� �o���Ɠ���� ���Ό��ÔV�g��
�F��삩��@�g���A������̐쉈���̎R�x�n�т��ē����A�������Ƃ�o���ƒn�Ղ̔֗]�i�����j�̒n�Ɉ�������܂����B
���̂i�q�N��s�w���ӂŁ@�x�Ƃ̒n�Ղł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����P���R���⍂���R�R���ɂ͑傫�ȁu�_���v�̑�������u�_���V�c�͂��̒n��ʂ��a���肳�ꂽ�B�v�Ə�����Ă��܂��B
�܂��ǂ݂̂����b�Ȃ̂Ł@�ǂ̓���ʂ点�悤���@����Ȃ̂ł����@���̂P�U�X���������̓��́@��̑O�܂ŗd���▂�������ނƂ����@
�����������҂̌��s�ȓ����z�����H�ł����B�@
��r�I�y�ɑ�a����ł���@168���������̓��ł͂��肪���݂��Ȃ������̂ł��傤�ˁB

����͑��P���̋������̐_�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
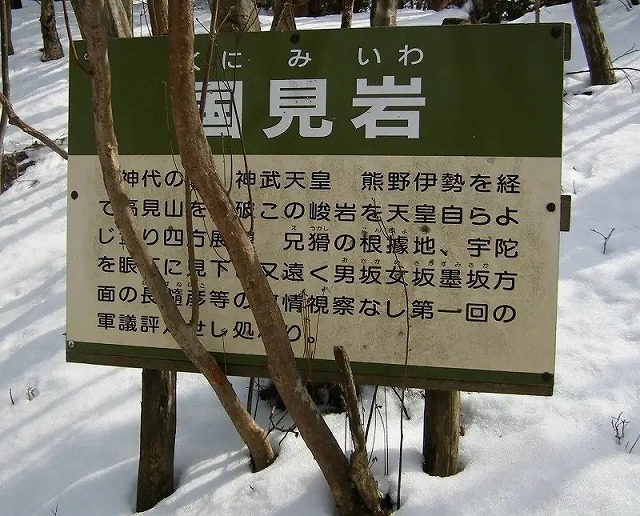
�_���͍����R���ʂ��������ł��B�����R�ɂ킴�킴���Ȃ��Ă��@�֗]�ɂ͂����ƊȒP�ɍs����̂ɂȂ��B
�������o���Ƃ̓��傪���s���ā@���Ă���̂�����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���ꂪ��ꎟ�����ł��� �����Ƃ͈���(�o�_�n�̓o���Ƃ��Ή�)�ɂ����܂����ݍ��܂�� �������Ă��܂��܂��B
�����Ő���248�N�����B�����C��G���i���_�j�ɂ�� ��������n�܂�܂��B
�C��G���̍c�q�C�N�����i���m�@��e�͈����ÕP�@�L�I�ł͍炭�⍟�ԕP�j�̓C�R�}�R�i�C�N���������炭�Ƃǂ܂������Ƃ���
���̎R�������Ă��܂��j���z���� �����̃h���}�̖��ɑ�a���肵�܂��B
�L�I��100�N�߂����ꂽ�@���̓��̓������܂Ƃ߂� �u�_���V�c�i�V�c�Ƃ����Ăі���������̂͂����ƌ�̎���� �V������ł��B�j����������
��a�ɏZ�ޔؑ��肵���v�Ə����܂����B
�� �o�_���̎��Ɍ��킹��� �u���܂��畨���� �ؑ��ł���A�a���ŏ��̍��ƂŗR������o�_���Ƃ�|�����̂��B�v�Ǝv���Ă��܂��B
��a�̕����������n���l�̖���� �����������Ȃ�� ��ɏ����܂����ˁB����Ȃ��̌������ƂȂN���]���܂����ˁB
�����玩�������͓V���獂���ɍ~��Ă����_�� �Ȃ�Č����Ă���̂ł��B
�V�㐢�E���猩�����ڂ̐_�l�̒��Ɂ@�����̂�����́@���ؐ�X�P������̂��@���܂���ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���C�N��������J�̖��ɐ���R���đ�a���肵�A��a�̑剤�ƂȂ�ꂽ�ڂ����������͂��̃u���O��2016�N1��11����
���n�_��(�����ܐ_��)�ɍڂ��Ă��܂��B
�܂����̎��̋L���ɂ͎����̕P�c���̔��ےÕP���Ղ鑺���_�Ђ�@�����̒��j�Ō\�҉��ߍ���R�Ɖ�����������R���J��
�u���_�Ђ��ڂ��Ă��܂��B
�܂�������т�O�ѓ��肪���Ό��ÔV�g�̐擱�ő�a���肵�����ɒʂ����ł��낤�@�F�Ɏs�Y���̔��@�G�_�Ђ̖K��L���ڂ��Ă��܂��B
���̒n�܂ŗ�����@�o���Ƃ̒n�Ղ̔֗]�͂��������Ȃ̂Ł@�����R�͂悤�₭���S���A���Ό��ÔV�g�Ɋ��ӂ��ā@���̐_�Ђ𗧂Ă��̂ł��傤�B
���Ό��ÔV�g(�������Ă̂�)�̖��O�����̂悤�ɕ������A����Ŏx�߂̐_�b�ɏo�Ă��锪�@�G��A�z�����̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�֗]���肵�������Ƃ̉��� ��т��O�ѓ���������Ȃ��̂� �L�I����҂́u�����E�}�V�}�W�v�Ȃ�ˋ�̐l����n��グ�A
�����֗]�F�i�����Ђ��j�Ɩ��Â��܂����B��̑��薼���_���ł��B
����䂦�L�I�ł͈�тƂ��O�ѓ��ƌ������O�͐�ɏo�ė��܂���B
�_���剤�̂��Ƃ��L�I�́u�_��a�֗]���q(���ނ�܂Ƃ����т�)�v�Ə����Ă܂��ˁB
���剤�̖��O�� ����܂ł̎������� �������ɂ��� ���ׂĕς��Ă��܂����̂́@�V�c���x�𗘗p���� ��N�ȏ�ɓn��O�ꂵ�Ď������₵�� �����Ƃ̎n�c�s�䓙��
��F�̍c�q�̑\���̋ߍ]�W�C�ɖ����ĕς����������̂ł��B�L�I���������� �O�ꂵ�ē��{�̗��j��ς��Ă��܂����̂��s�䓙�ł��B
�����ē��ē������Ă��ꂽ�o���Ƃ̉��Ό��ÔV�g�Ɋ��ӂ��� �`���̐_�b�ɏo�Ă���u���^�K���X�v�Ə̂��Ē����F��{�{��Ђ͂��ߊe�n�̕����n�_�ЂɍՂ�̂ł��B
�F��O�R��������Ƃ��ɂ͎��A�o�_�������̖���Ƃ��Ă� �{�a�̏����ɂ��Q�肹���@���Ђ̃��^�K���X�_�Ђɂ������Q�肵�܂����B
�o�_���Ƃ̌������� ���Ό��ÔV�g���J���Ă��܂�����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�b�͕ς��܂��� �a�̎R���A�ޗnj��A�O�d���̌����̔n����l������ ���E��Y�̎Q�w���̉��l�Ɨ��j�I�Ӌ`�������炸 �قƂ�ǂ̎Q�w����j�Ă��܂��܂����B
���� �قƂ�ǂ̌F��Ó����A�X�t�@���g�ܑ��̗ѓ��������ł��B�e���r�ŗǂ����f���Ă��� �Ώ�̓��͂ق�̈ꕔ���ł��B
��퓹�͔�r�I�ۑ�����Ă��܂�������ł��R���̂P���ѓ��Œׂ�Ă��܂��B
���E������Y���쒬�Γ��i��C�̕��̖��鎜���@�����C�̖��鉜�̉@�܂ł̕\�Q���j�Ȃǂ́A �S���t��̒���ʂ��Ă��ĊŔ�
�u�S���t�{�[�������ł��ē������Ă��m���ˁv�Ə����Ă��� ���R�Ƃ��܂��B���̓��������������̊O���l�����ɒp���������v���ł��B
�܂� ���ӘH������Ă����Ƃ��� �h�꒬�ł������т�H �ׂ��Ƃ��ɂ� �X�̃I�o����u���ӘH������Ȃ�ĂقƂ�ǂ� �O���l��B���{�l�͊ό��o�X�ł���Ă���
���C���̊ό��X�|�b�g������ �����Ɨ��������Ă����B���͕��������̂��v�Ƃق߂Ă��炢�܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�_�������̎n���L�@����1
�L�I�͓V�̑��_�̖��O�������āA�_���Ƃ��A���������̑��݊��Ԃ��o�_�����̏����̋I���O6���I���܂ň����グ���̂ł��낢���
�����������Ă��܂��B
�܂��剤�̐�������Ȃ��̂Ł@�剤�łȂ��l��剤�ɂ��Ă��܂��B��B���o�����Ƃ̂Ȃ������Ƃ̃C�j�G�����a�̑剤�ɂ�����(���_)�A
�����є䔄(�_���c�@)�̕����́@�L�O���ÕF��剤�ɂ�����(����)�A�܂�100�Έȏ㐶�����l��啝�ɑ��₵�܂����B
���ɐ_��127�A�C�N��(���m)139�A�I�V�����P(�i�s)149�A�I�I�T�U�L(�m��)143�Ȃǁ@���̑����ۂ��������̑剤������������グ�܂����B
�_���̓������o�_�����̏����܂Ł@���S�N�����グ���̂Ł@�剤�̐�������Ȃ������Ɂ@��鉤��2��̏��쎨(�X�C�[�C)����9��̑���X(�J��)
�܂ł͂��̂܂܍̗p���Ă��܂����@10����q���A11��F����͏�����Ă��܂��B�Ȃ��ł��傤���B
���傤�ǁ@��鉤���ƕ��������Ƃ̐��������Ȃ̂łȂɂ��܂������Ƃł��������̂ł��傤�B
10����q���A11��F����͏�����Ă��܂����@�L�I��10��C�j�G(���_)��14�㒆�ÕF(����)�̓�l��剤�Ɏd���ďグ�ċ��ݍ���
�剤�̐����킹�͂��Ă��܂��B�剤�̐��͍��킹�Ă���̂ł��B�I�݂ȍ��b�ł��˂��B���S���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�_�������̎n���L�@�@����2
���グ��ꂽ�_���剤(�_��a�֗]�F)�́@�����J�ɋ{�����ɂ�肨��܂ō���܂����B�Ƃ������@�o���Ƃ̂���̒��ł��傫�Ȃ��̂�
����ɐ_���̕悾�Ƃ��Ă���̂ł�����A�{���������邱�Ƃ��o�L�ڂł��ˁB
�������{�����́@�c���̗��j�͂��ׂā@���b�̋L�I�ɏ]�킴������܂���B�������Ȃ��ƍ��̍c���̑��݂��������Ȃ��ƂɂȂ�܂�����B
�ł�����@�_���ȊO�̕���@�ˋ�̍c�q���}�g�^�P���̂��������܂����A鰏��ɓo�ꂷ����̃q�~�R(�P�c��)�̃����\�P��
100�N�ȏ㎞�オ�o�����W���ɓo�ꂷ���a�P(5�Ԗڂ̃q�~�R�ł�)�Ƃ�������܂��ɂ��āu��a�g�g�r�����\�P�v�̂�����ł����グ�Ă��܂��B
���̂�����o���Ƃ̉��̂���ł��B�����ꒃ�ł��ˁB��x�R��������ɉR���d�˂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�@�R�̃X�p�C�����ɂȂ�܂��ˁB
����ȉR�Ōł߂��c�������A�����Ƃ����Ƃ������j�Ɋ�Â����j�������炯�o�����ق����@�����ɐe���܂�₷���Ǝv���܂����B
�o�_���Ƃ������̌����������Ƃ��|���A�����ɓn�����N�l�̒C�̉��q����(�Ђڂ�)�̌����Ђ������P�͂��ߑ����Ƃ̌������x�ƂȂ�����
���Q�����̘a�̌܉��������A�I�V���J�A�R�E�P�C�A�I�P�A���J�T�U�L(����)�Ƒ������������a����͓r�₦��B
���o�_���Ƃ̎�N�I�z�h�̌N���@�O�������Ƃ̑h�䑍�{��(�����̏h�I�����F���畐���̐b���c���ɉ����̎q��)�̐U��P�ɖ����肵���I�z�h�m�N��
��a����Ɍ}�����@�j���(���ق�)�剤�ƂȂ��ā@���v(�I�P)�剤�̖��蔒���P(�����炩�Ђ�)���}���čL��剤(�Ӗ�)�����܂�Ĉȗ��@
���̍c���������Ă���Ɓ@�Ȃ������ƍ����ɒm�点�Ȃ��̂��@�ӂ����ł��B
��O�풆�̍c���j�ς́@�����ɂȂ�V����������F�����B�̖��w�ȉ������m���������肠�������̂�����ł��B
���낻�뎝����s�䓙�����グ���@�L�I�̎���������������ꂽ�炢���Ǝv���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ñ�o�_�����䂩��̒n��K�˂ā@�̃g�b�v�y�[�W�͂����炩��߂�܂��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
65�䍂�_�ЖK��L(2013�N9��23��)���ĕҏW���܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019�N4��9��
�䍂�_�Ё@���쌧���ܖ�s�@�䍂���@�@2013�N9��23��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�ȑO�R���̓r���ŖK�ꂽ�@�䍂�_�Ђ̍ĕҏW�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Г����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�萅���瓒�C���オ���Ă��܂����B�����Ȃ̂ł��傤�B
�z�K��Ђ̂�������Ђ̂ǂ����ɂ�����̂����̎萅������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ж����A�q�a�ȂLj�A�̌����́@�V���������ł����B�ŋ߁@���ւ���ꂽ�̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�������ɂ͑�R�̐l���@��������Ⴂ�܂��B�n��̐l�̐M���W�߂Ă���悤�ł��B
�����͕��a�ł��傤���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
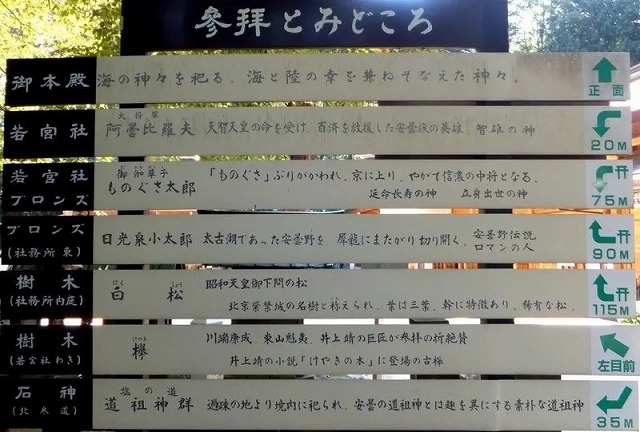
�_�Ђ̐����Ŕł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
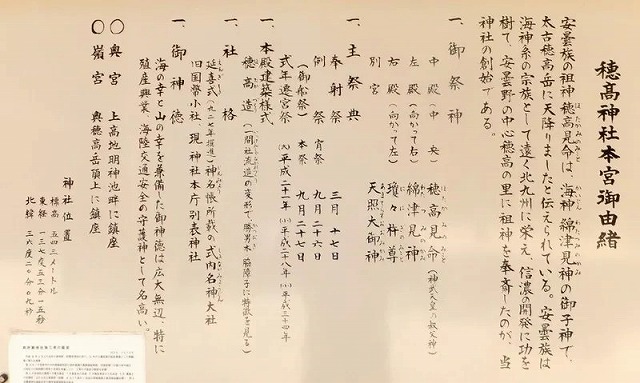
�_�Ђ̗R�������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����ɂ��܂��Ɓ@���̐_�Ђ͊C�̐_�l���J���Ă��邻���ł��B
�C�_�i�킽�݁j�͌䉾���́u�C�F�A�R�F�v�ɏo�Ă���R�K�F���q�˂����{�ɏZ��ł���Ƃ���
�L�ʕP�̕��_�ł��ˁB
�䍂���̐_�͖ȒÌ��̐_�̎q���Ə����Ă���̂Ł@�܂�R�K�F�̌n�����Ղ��Ă���Ƃ������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����ŊC�K�F�i�Z�j�ƎR�K�F�i��j�ɂ���
�Z�̊C�K�F�́@�����̒��j�@�\�҂��N�������C���i���܂ׁj�Ƃ������A��̎R�K�F�́@�����̎��j
���o�����N��������B�����Ƃ������܂��B
�I���O�R���I���Ɂ@�Ό��̌\�ҊC�݂Ɂ@��R�̊C���i�N�j���j�����������A��ď㗤�����̂�
�`���l�����ł����B���O�ɒ����ȕ����̖��ځi�قЁ[���̏o�_��Ћ{�i�̑c��j���o�_���ƂɎg�킵��
�㗤�������Ƃ����@�����ȏ����̂��ƂɎ��s����܂����B�����͎������a���̉��ɂȂ����ł����B
�����͘a�����z�A�J���Ɩ����@�o�_���Ƒ掵��剤�V�̓~�߂̕P�A���ƕP��W�蒷�j�u�\�ҁv���������܂��B
���̌㕔���̖��ځi�قЁj��C���B�ɖ����ā@�o�_���Ƃ̎剤���疵�╛�����d�g�Ðg������
�H�E�Q���܂����A���lj��ɂ͂Ȃꂸ�@��U�`���ɋA�����Ďn�c��ɍX�Ȃ鎑���ƊC���B��Ⴂ
��x�ڂ̏㗤������̕��t�ɉʂ����܂��B�����Ęa�����`�����i�ɂ��͂�ЁA�ɂɂ��ˁ@�Ƃ��������j�Ɩ����@
�o�_���Ƃ̕��Ƌ�B�@���Ƃ̎s�n���P�@��W�莟�j���o���ƒ����䉮�P���������܂��B
���o������B�����Ƃ̎n�c�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
������j�\�҂́@�������ĒO�g�ɈڏZ���āu�C�̍���R�i���܂̂�����܁j�v�Ɩ����C���Ƃ𖼏��܂��B
���̌��a����n���ɈڏZ���܂��B�����ɎE���ꂽ���疵�┪�d�g�Ðg�̍c�q�����͊��ɑ吨�̏o�_��
�ƂƂ��Ɋ���n���ֈڏZ�J�ā@�傫�Ȓn�Ղ�z���Ă��܂������@�x��Ă�������R�͑吨�̊C���B��
�����A��Ă����̂Ł@�o�_���Ƃ̍c�q�́@�������F�������́@����R���a�̉��ƔF�ߖ������F�̕P�剮�P��
�ł����܂��B���܂ꂽ�c�q�����q���ł��B
�������R�́@�ٕ�Z���̕䉮�P����B�����Ƃ���ĂъĔ܂Ƃ��ĊC�̑��_�i�����������Ȃ̂Ō�ɓV�̑��_�Ƃ�����܂��j
���������ā@�V�̑��_���@�o�_���i���ƁA�����Ɓj�̎x�����ā@�����a�剤�ƂȂ�܂��B
���ꂪ�R�K�F�̃��f���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����B�����Ƃ́@�P�W�O�N���ɓ������F��ɏ㗤������@��a���̒�R�Ŗk��ł����F���͌��̒��B��
�����������Ă��܂����B�i���̐Ւn�ɌF��{�{��Ђ����Ă��܂������@�����̑�^���ŗ������
���݂͎R�̒����Ɉړ]����܂����j
�����Ł@�����剤�Ƃ̗͂������č����B�̑����ō������Ă����a�ɖ��g�𑗂�@�x�Ƃ̉��Ό��ÔV�g�̗U����
�悤�₭�x�Ƃ̒n�Ղ̔֗]�̒n�ɓ���܂��B
������сA�O�ѓ��Z��́@�u�֗]�F�v�ƌĂ�܂��B
�L�I�̕ҏW�҂͂��̖��𗘗p���ā@����剤�̖���_��a�֗]�F�ƍ��ς��Ă����������
�Ñ�o�_�����̎n�܂�́@�I���O�U���I���܂ň����グ���̂Ł@�R���R���Ăс@���܂�����Ȃ��Ȃ�
�P�X�O���炢�̑剤�����l������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̌㕨�����Ƃ́@�O�㑱���ēo���Ɓi���Ɓj����܂��������@�����Ɉ�鉤�ƂɈ��ݍ��܂�Ă��܂��܂��B
�����Ŗ�W�O�N��̂Q�R�Q�N�Ɂ@��B�������Ƃ̃C��G���͍Ăѓ������J�n���ē쉺���܂��B
�쉺���ĎF���̈����ÕP�Ƃ̊ԂɃC�N���c�q���������܂��B����ɓ����̖L�����̖L�ʕP��
�܂Ƃ��Č}���@�����L�A��������@�����̏������n�߁@�L�ʕP�Ƃ̊ԂɖL�F�A�L�P���������܂��B
�䉾���̂Ȃ��Ł@���{��̕P���@�L�ʕP�Ƃ�����A���̕����C�_�i�킽�݁j�Ƃ�����܂����B
�ނ�j���Z�̊C�K�F�ɕԂ��ɍs���R�K�F�𑗂��ĊC�ӂ܂ŗ����Ƃ��@�R�K�F�̎q��
�}�ɎY�C�����@�R�K�F���Y�����̉������E�K���ŕ����I���Ȃ������ɖL�ʕP�̓��j�i�o�_�ł͎L�����j
�ƌĂт܂��j�̎p�ɂȂ�L�F���Y�݂܂��B����ŖL�F�́u�����E�K�������A�G�Y�v�Ɩ��t�����܂����B
���Ȃ݂ɕ����F�����Ƃ́@��ꎟ�����̒��{�l�̉��̖��O�Ł@��ꎟ�������I�m��̉͌��Ő펀����
�����ܐ���F�삩���a���肵����сA�O�ѓ������̕����ł��B
�L�ʕP���@���j�̎p�ɕϐg�����Ƃ������́@�F���L�ʕP���o�_���̌��������Ă���Ƃ��������������Ă��܂��B
�@���ƂɎn�܂�F�����Ƃ́@�o�_���Ƃ̕��Ƃł�����B�C�Y�����̓��j�𐒔q���Ă��܂����B
���Ȃ݂Ɂ@������ő�a���肵�ā@��a�剤�ƂȂ����C�N���剤�́@��̑��薼�𐂐m�ƂȂÂ����܂����B
�����Ĉ�x����B���o���ɖS���Ȃ����C��G���́@�L�I�̍��b�ł́@���_�剤�Ɓ@��a�̑剤�ɂł����グ���܂����B
�R���R���Ăс@�{�����͈��Ƃ̌Õ��𐒐_�剤�łƂ��ĊǗ����Ă��܂��B�n���ł��ˁB
�L�F�A�L�P�i鰏��ő�^�g���Ə�����܂����j�͑�a�ł́@�L�����F�A�L�����P�ƌĂ�܂���
�L���i�Ƃ悫�j�ł́@���������ƌ����̂���Ă��܂��̂Ł@�L�I�ł́@�L�L�i�Ƃ悷���j���F�A�L�L���P�Ə����������܂����B
��x�R�����Ɖi���ɉR���������Ȃ���o���܂�����ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����@�V�́i�C�́j����R�Ɏn�܂�C���Ƃ̕��ƂƂ��ā@�����Ƃ��ʂ�܂��B
����́@�������W��n�ՂƂ������炻���Ă�܂��B���݂̃_�C�������h�g���C���̊⋴�R�̓�����
�V�̍���R�̍c�q���q������e�ŏo�_�̕P�ł���剮�P�Ƌ��ɏZ�݁@�u�剮�v�̒n�����t����������Ǝv���܂��B
���̒n��́@�|�̓����̓����ŃC�Y�����̓����̔������ꂽ�����𒆐S�Ƃ����n���菭���k�̒n��Ǝv���܂��B
�܂��C���Ƃ̕��ƂƂ��ā@���܁i���܁j�A�Ƃ��ł��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ƃ������ƂŁ@�O�u���������Ȃ�܂������@���̐_�Ђ��J���Ă���̂́u�C�̐_�l�v�ł͂Ȃ��ā@�C���ƂȂ̂ł��B
�C�̍K�ƎR�̍K�̗����̐_��������Ƃ����̂́@�C�K�F�ƎR�K�F�̗����̕��e��
�`�����i�����j������ł��傤�B
�����n�̐_�Ђł́@�`�����i�ɂ��͂�Ёj��j�j�M�A�����ăz�A�J���͂��ׂď����̘a���ł��B
��Ր_ �̓j�j�M�m���Ə����Ă���܂��ˁB
�C���Ƃ͊C�̖��i���݂�j�ł͂Ȃ��ā@�����Əo�_���Ƃ��琶�܂ꂽ�剤�ƂȂ̂ł��B
�䍂���̖��͐_���̏f���Ƃ����Ă���A�����̋L�I�̒��̐_���͉ˋ�̐l���Ȃ̂Ł@�L�I���o�����ォ��
�L�I�ɂ��킹�ā@����܂ł̒n���̐_�������C�N���č��ꂽ�_�Ȃ̂ł��傤�B���^�c�~�m�_���䉾���̒��̐_��
�A�}�e���X���Ñ�o�_���������̍K�̐_�O�_�̍������̖������f���ɋL�I�ō��ꂽ�̂�
�����i�j�M�n���q�A�j�j�M�j�ȊO�́@���ׂċL�I�ɂ��킹�Ă��܂��ˁB
������O�ł��ˁB���̍ō����͎҉E��b�̕s�䓙�ɂ͒N���t�炦�܂���ł�������B
�����������A�L�I�ƈႤ�L�q������@�����߂ł�����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɐ_�n�Ђ�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�n�̃��f���͖ؑ\�n�������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̉��Ɂ@�{�a�������Ă��܂����A�{�a�̌����͌���܂���ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ܘA�䗅�v�̑��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
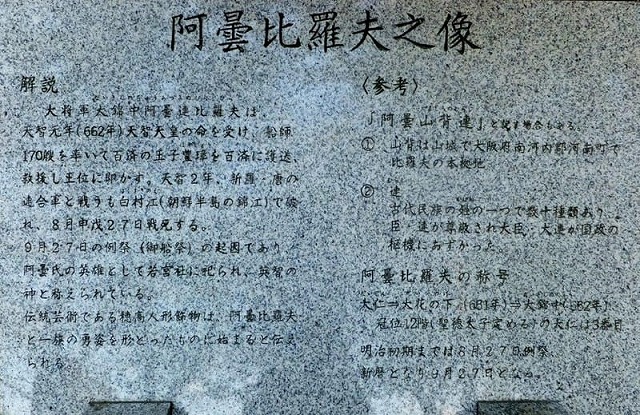
���ܘA�䗅�v�̐����ł��B
�R�w���i��܂���̂��Ɂj�́@���ē��{�̒n���s���敪�������ߐ�����1�ł���R�鍑�̕ʖ��ł��B
�c�O�Ȃ��炱�̒��߂́@�ԈႢ�ł��B���{��͓��S�͓쒬�ɂ��@���̂��ׂ̑��q���ɂ�
���}�V���@�ƌ����n���͂���܂���B���݂̋��s�{�암�ŖؒÐ�̖k�̒n��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����������⑫�������K�v�ł��B
�U�U�O�N�V���@�V�������̉��R�ĕS�ς��U�߂܂��B
�@�@�@�@�P�O���@�S�ς���̂���đ�R�̕S�ϐl���a���ɓ���Ă��ā@���������߂܂��B
�U�U�P�N�T���@�֖����邪�V�������ɏo�����܂��B
�@�@�@�@�V���@�֖�����͒}�O���q�{�Ŏ��S
�@�@�@�@�W���@�C���Ƃ̕��Ɓ@���ܘA�䗅�v�����R�ƂȂ�S�ω���ɏo��
�@�@�@�@�@�@�@���̌㑽�b�E�~�i���������̑c���j�̖���S�ω��q�L�܂̍ȂƂ��ė^��
�@�@�@�@�@�@�@�S�ς֑���͂����B
�U�U�Q�N�W���@��і�N�t�q�i���݂��̂��݂킩���j�����R�Ƃ��ĐV�������Ɍ�����
�@�@�@�@�@�@�@�����]�̊C��ő�s���S�ς̖����悹�Ĕs���A��
�U�U�T�N�@�@�@�Ԑl�c���@��g�{�Ŏ��S
�U�U�V�N�@�@�@����J�s
�U�U�W�N�@�@�@�V�q�剤����
�U�V�P�N�@�@�@�V�q�剤���S
�U�V�Q�N�U���@�p�\�̗��@�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�p�\�̗��̋g�쑤�̑�C�l�̍c�q�͊C���Ƃł͂Ȃ��ā@�ےÂ̍��Z�g�_�Ђ̎ЉƂ̒Î�A��C�̍Ȃ�
��P�i�c�ɏ���j�̎Y�c�q�̉W�ɂȂ����̂Ł@��C�l�F�ƌĂꂽ�̂ł��B
�g�쑤�ɂ��������B�́@���̐b�i���i�����C�̕��j�A�R�ӂ̌N�����C�i���������j�A�唺����
�����q�l�A�����Ĉ��܂̘A��~�����ł����B
���ܘA�ꑰ�͌Ñ�j�ő�ϊ����ЂƂ����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ͏M�̍��g�݂�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�H�Ղ�Ŗ��N���̏M���g���邻���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
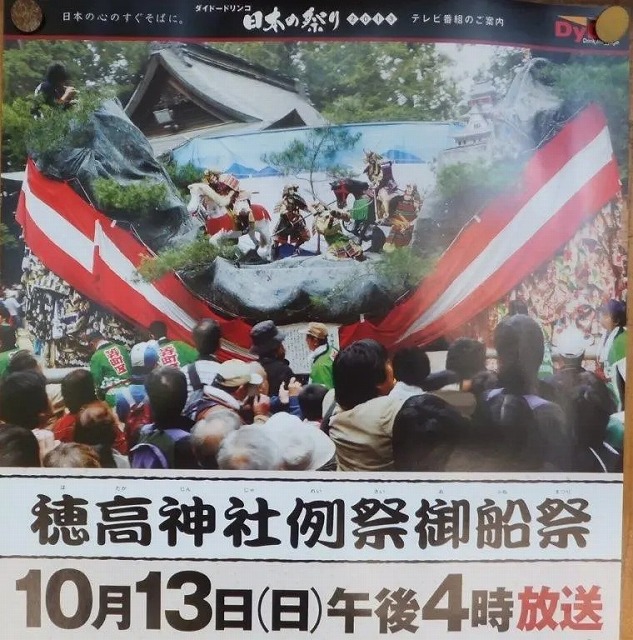
��Ղ̃|�X�^�[�������Ă���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�u�Ñ�o�_�����䂩��̒n��q�˂āv�͂����炩�����܂��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Q�l�����@�֖؉_�B���@�匳�o�Ł@�@�����Ə@�������A�Î��L�̕ҏW���A�䉾���Ƃ��̃��f���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�_�Ƒh�䉤��
�@�@�@�@�@���@�F�F�@�@�匳�o�Ł@�@�e鰘a���̓s
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
64�@�u�߂������v�K��L�@����1�@�@2019�N3��12��
�j��瑑剤�̑��ł��鐄�Ï��邪�e���̌Õ����W�߂đ��c�������������ł��B
���̐��ÁA�p���A�q�B�A�K���̊e�˂�����܂����B
�܂����킹�ā@�j��瑑剤�̂Б��̏�{���q(�������q)�̗˂Ƃ��̍c�q������
�o�_�ł̑��Ղ����킹�čڂ��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�߂������K��L�@����1
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���q���̒n�}�ł��B
����1�Ł@���×ˁA�Ȓ��_��
����2�Ł@�p���ˁA�F���ˁA�q�B��
����3�Ł@��V�{���q�i�������q�j�揊�̉b�����@�@�ȏ��q�˂܂����B
�܂�����3�Ł@���q�̑��q�B�̏o�_�ł̑��Ղ��ڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
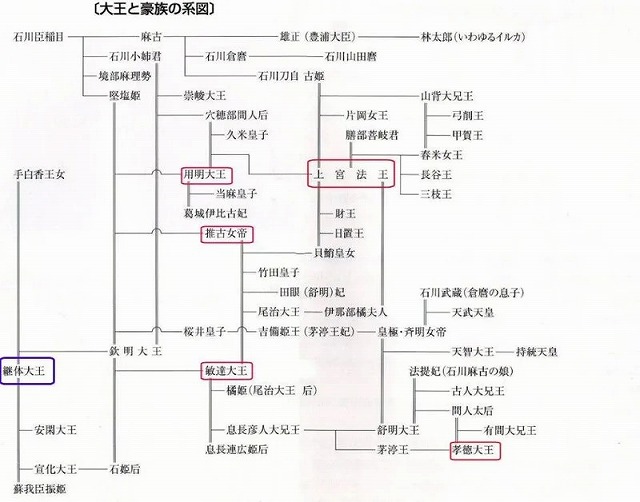
�I�z�h�剤�i�p�́j���瑱���剤�Ƃ̌n�}�ł��B
����͐Ԃň͂剤�̗˂�q�˂܂����B�B���V�{�@���������剤�ł͂���܂��B
�܂����̎���@�܂��V�c�ƌ������t�͖��������̂Ł@�剤�i�������݁j�Ƃ����Ăі��œ��ꂵ�Ă��܂��B
�n�}�͑匳�o�Ł@�֖؉_�W���u�����Ə@�������v�ɂ��܂����B
�܂��֖ؐ搶�̗����ς݂ł��B
���I�z�h�剤�̑��Ղ�q�˂����́@���̃u���O��2018�N4��5���̉z�O�����ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̌n�}�����ċ�������������܂��B
�������邪�w�����ā@�s�䓙�炪�������Ƃ����L�I�̒��Ł@����剤�́u�V�̑��_�v�̖��O�Ƒ��݂�������ā@
�_���Ȃ�ˋ�̑剤���ł����グ���܂����B
�������@���̓o�ꎞ�オ�@�o�_���������̋I���O6���I����܂Ł@�k�点���̂́@�V�̑��_���Z���̌�����
���܂ꂽ�̂��@�����������A����Ł@�a���̗��j��P���Ȃ����Ǝv������ł��܂����B
�I���O3���I���ɐΌ��\�ҊC�݂ɏ㗤�n�������@�`���l�����͏o�_���Ƃ̑掵��剤�i��E���喼�����j
�V�̓~�߂̕P�@���ƕP��W��a�����u�Ζ���A�ق�����v�Ɩ���蒷�j�\�҂�݂��܂��B
�����ĕ����̕���i���̏o�_��Ћ{�i�̑c��j�ɖ����ďo�_�����̎剤���疵�ƕ����i��E�������j
���d�g�Ðg��H�E�Q���@�������a���̉��ɂȂ낤�Ƃ��܂����@���ʉʂ������@��U�A�����܂����B
�����Đ`�̎n�c��ɍX�Ȃ鎑���Ɛl�ԁi�C���ƌĂ�鑽���̐N�j���j�����炢�@��x�ڂɍ���̕��t�ɏ㗤���܂��B
�����͘a�����`�����i�ɂ��͂�Ёj�Ɩ����A�@���Ɓi�o�_���Ƃ̕��Ɓj�̎O�o���̖����̎s�n���P��W��@
���܂ꂽ���j�̕��o���i�ققł݁j����B�������Ƃ��N�����܂��B
���Ő��܂ꂽ�䉮�P�Ɓ@���j�̌\�҂����������܂ꂽ�̂��V�̑��_�Ł@������a�̊���n���ɈڏZ���Ă���
�o�_���Ƃ̍c�q�����@�������F�i�������������Ђ��j�������i�����Ђ����j�Ȃǂ̋��͂Ł@�����a�剤�ɏA���܂��B
������������������̂��Ɓ@�v������ł��܂������@���̌n�}������Ɓ@��Ⴂ�̌Z���Ō�������̂�
����ӂ�Ă��܂��ˁB���̎���́@����ȂɃ^�u�[�ł͂Ȃ������̂ł��ˁB
�Ƃ������Ƃ́@������s�䓙���������̂́@�����B�̑c�悪�@�n���l�Ł@�������o�_���Ƃ�|����
�u�����n�������v���Ƃ����̂��B�����������̂ł��ˁB�����玩���B�̑c��͍��V�����獂����
�~��Ă����Ȃ�ē��b���K�v�������̂ł��傤�B
���V������_�X�𑗂�o���Ď��U�����Ƃ����_�X�̈�l�Ɂ@�u���ؐ��P�v�Ƃ��������̃I�J���̖��O��
�����Ă���̂́@���܂��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���q���@����1
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�S�̂̎ʐ^�ł��B������̂Ƃ��������ȋu������ł��B����͂��ׂēc�ނł��B
�����Ԃɏ���������ēc�ނɂȂ����̂ł��傤�B���Ƃ��Ƃ͋���ȌÕ��������͂��ł��B
���R�͌�ŏq�ׂ܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�˂̐��ʂł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�����̐����Ŕł��B�����ɂ͒|�c�c�q�i���ÁA�q�B�̊Ԃ̍c�q�j����������Ă��邻���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�̒����̉��͎G�ؗтɂȂ��Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���Â̎���ɂ͂܂��u�V�c�v�Ƃ������t�͂���܂���ł����B
�ߔN�{���������̐Δ�����Ă��̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�˂̗����ł��B�Õ�������Ĕ��ɂȂ����̂��悭������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���Ï���́@�����P�i�ΐ�̐b��ڂ̖��j�ƋԖ��剤�̍c���Ƃ��Đ��܂�z�c���̍c���Ɩ��t�����܂��B
�Ԗ��剤�́@�I�z�h�剤�Ǝ蔒���P�i�I�P�剤�̍c���j�Ƃ̍c�q�Ȃ̂Ł@�z�c���c���́@�o�_���Ƃ̌��ƂƂ���
�r�₦���吝�i�����������j�����̌��������Ă��܂��B
�ΐ�̐b�Ƃ͕����̐b��c���̎q���Ł@�o�_���Ƃ̌��������Ă��܂��B�@
���i������c���͓����͋�B�������Ƃ̃C�N�����ɕt���]���@�����̏h�H�Ɩ����܂��B�h�H�Ƃ́@��������
�̏d���̏̍��ł��B
�ނ́@鰂ւ��x�X�����ɍs���@鰏��ɂ����O���ڂ�܂��B�C�N�����̑�����ɎQ�����܂���
�@��ɃC�N�����ɔ�����|���Ĉ�鉤�����ɕt���܂����@��ɔj�ꔌ�˂ɓ���܂��B
�������@�C�N���剤�̕������h�q�ɒǂ��ďo�_�֍s���@�o�_���Ƃɓ����@�o�_�̕P��W��@
�Ȍ�͏o�_���Ƃ̏d���̏̍��@�b���݁@�𖼏�鎖��������܂��B�j
�����b��c���̑��Ղ́@���̃u���O�́@�_���_�Ј�Ձ@2015�N11��13��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���_�Ё@�@�@2017�N10��12���@�ɍڂ��Ă��܂��B�@�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����I�z�h�剤�Ǝ蔒���P�̊Ԃɐ��܂ꂽ�q���j���剤�i�Ԗ��j�͑O�剤�̉��|�i�鉻�j�Ƌk���P�i�n�����N�l
�ږ��Ђڂ��̎q���@�����Ɓi�����Ȃ����A�����ѕP�u�_���c�@�v�̎��Ɓj�̕P�j�Ƃ̊Ԃ̐ΕP���c�@�Ƃ��Č}���܂��B
�����Đ��܂ꂽ���ʕ~�c�q���Z�i�������A�剤�Ƃ̐Վ��j�Ƃ��A��̕q�B�剤�ƂȂ�܂��B
���ʕ~�c�q��11�ő剤�ɑ��ʂ��q�B��N�ƂȂ�A15�ő����Ƃ̑����^�艤�̖��L�P���c�@�Ƃ��܂��B
�q�B�̍c�@�ƂȂ邱�Ƃ����҂��Ă����@�ٕ�o��̊z�c���c���́@�L�P����ɑ��Ƃ����Ă��܂��B
�L�P�͑����F�l��Z����@��̋}��������܂��B�����Ă��̌�q�B�剤�͊z�c���c�����c�@�Ƃ��܂��B
���̑����n�i���N�n�j�̍@�Ɛΐ�b�n�i�o�_�n�j�̍@�̐����ꂼ��̍c�q�����̌�@����ȑ剤�̍����߂���m��
���J��L���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�܂��z�c���c�@�́@�a���×��̖����̕�̓��̐_���A�����ȎM�Ɍ�H�i�݂��j�����Đ_�O�ɕ�����_����
���悵�čs�����̂Ł@��H�����i�݂���������j�P�c�@�Ƃ��Ă�܂����B
585�N8���ɕq�B�剤�͓ˑR�a������܂��B�z�c���c�@�̗��_�͔��ɑ傫�������Ƃ����܂��B
�䂪�c�q�̒|�c�c�q��剤�ɂ���ɂ͖����Ⴗ�����̂ŁA�����̌Z�̖L����Z���������|�C���g��
�剤�Ƃ��ā@���������@�Ƃ��Č��͂����낤�Ƃ��܂��B
�����������`�����ā@���Ŕh�̕M���@�ΐ�b���ÂƐ_���h�̑��@�Ƃ͒������Ɉ��������̂ł���
�f���ł���ΐ�b���Â���c�i�������j�{�ɌĂ�
�Ȍ�͕������@�̌��݂ɔ����Ȃ����A���������@�Ƃ��Ď��������鎖�A�Z�̖L����Z��剤�Ƃ��邱�ƁA
�ΐ�b�̗̒n�̈�u�ߒÔv������ōw�����A�ΐ�b�̌��������剤�̗˂���邱�Ƃ����������܂��B
���̗˂̒��S�ɉȒ��_�Ђ����݂����̂ł��B���̑��q���̋߂̒n�ɑ����̌Õ�������̂͂��̂��߂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ȓ��i���Ȃ��j�_��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̐_�Ђ͂킩��ɂ��������B�n���̕��ɕ������@�悤�₭���������B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������E�Ȃ���⓹��o��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�₪�Đ_�Ђ炵�������������Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�悤�₭���ǂ蒅���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ʂɔq�a������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̉������ɉ��܂��B��荞�ނƒ����Ɩ{�a������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�͎c�O�Ȃ���u��Б���v�ł͂���܂���ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ł���́@�����l���̉��킬�ł͂Ȃ��ā@�o�_���̏c�킬�ł��B
���Ï���̓I�z�h�剤�̑��ł�����@���R�����͏o�_���Ƃ̌��������Ă���̂�m���Ă����̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���얅�q�̕�
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ȓ��_�Ђ̉��ɒ����Βi������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o���Ă����Ƒ傫�Ȃ��悪����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ȃ�Ə��얅�q�̂��悾�����ł��B
���얅�q�͍��g�Ƃ��ā@�哂�ցi�������@�̍��j�n�������ƂŗL���ł��B
���얅�q�͑�Z���a����剤�i��鉤���̑剤�j�̍����l�i���ɂ����ЂƁj�̖��Ⴞ�Ƃ���
���킳��������Ă���悤�ł��B�i���^�e���r�^�����g�����얅�q�̎q�����Ƌ��Ă���悤�ł����j
�V�̑��_�A���쎨�A�ʎ�ŁA�X�L�g���A�J�G�V�l�ɑ��������l�͐���107�N�Ɍ㊿����ɒ����������Ƃ�
�x�߂̗��j���ɏ����Ă���܂��B
���@���̑��q�t�g�j�剤�i��̑��薼�͍F��j�͗~�ɋ���Ď����B�̖{�Ƃ̏o�_���Ƃ�
�U�ߗ��Ăāi��ꎟ�o�_�푈�j��a�𗣂�܂��B
���̊Ԃɋ�B�������Ƃ̑�ꎟ�����������@��a�̓o���Ɖ��Ό��ÔV�g�̗U���ő�a���肵�܂��B
���̌��ʃt�g�j�́@��a�ɋA��Ȃ��Ȃ蔌�˂̍��Ł@�]�����߂����܂��B
�ł�����@�����l�̌n�����@�t�g�j�œr�₦�܂����B
�����獑���l�̎q���ƌ����̂́@���ɉ������ł��ˁB
�t�g�j���剤�łȂ��Ȃ�@�����̒n�������Ƃ��ā@���l�Ɨ]�����߂������@��Ղ́u�����_�Ёv
�K��L�́@���̃u���O��2016�N11��22���Ɂ@�ڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�߂������@���̂Q�֑���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
64�@�u�߂������v�K��L�@����2�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�߂������K��L�@����2
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�p���剤��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��ɏq�ׂ��悤�Ɂ@�p���剤�͊z�c���c�@���@�킪�q�|�c�c�q��剤�ɂ���܂ł̃����|�C���g�̑剤�Ƃ���
�����̌Z�̖L����Z�����@�剤�ɂ����̂ł���B
�p���剤�́@���J�̐ȂŁ@���l�����Ɂu���͎O��ɋA�˂���v�ƕ������̗p���鎖��錾�����ŏ��̑剤�ł��B
����ɂ������ā@�����牮�ƒ��b���C���u�Ȃ��@�����̐_�ɔw���@�O���̐_���h���̂��v�ƍR�c���đސȂ����Ƃ����܂��B
���̂��Ƃ��̂��̏@�������������܂��B
�܂��ނ͑c���̌p�̑剤�h���Ă�������@�c���̌̋��o�_����@�Õ��Z�p�҂��Ăъ�
�r�Ӌ{�̓�Ɂ@���ˁi���O�ɑ��c����ˁj�̓����˂�z�����B����͏o�_���̐����`�̗˂Ƃ����Ă��܂��B
���Ȃ݂ɂ��̓����˂́@�̂��ɐ��Ñ��@�ɂ��y����菜����ā@�Ύ����ނ��o���Ɏ��c����܂��B
���ꂪ�Ε���Õ��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����牮�͕����Ƃ̓��̂ł���@������ő�a���肵�ā@�Ώ�_�ЂŐ������s���������C�N���剤�̎q���ł��B
�����ĐΏ�_�Ђ̎ЉƂƂ��ā@�{�����J�������ǂ��Ă��܂����B
�����Ē��b�Ƃ��{�����J������s���ƌn�Ȃ̂Ł@��l�́@����������ɂȂ�Ύ��Ƃ̌������������
�����ɋ��s�ɔ������̂ł��B
�܂��p���剤������ɂȂ�@���̍c�q�̏�V�{��Z�i�������q�j�����̑剤�ɂȂ��
�����̑��q�̒|�c�c�q�͑剤�ɂȂ�Ȃ��Ɓ@�z�c���c�@�́@�뜜���܂����B
�@
�����ōc�@�́@�����牮�ƒ��b���C�𖧂��ɌĂс@�p���剤���P�������l�Ɏw�������̂ł��B
��l�͌��䕔�c�q�Ƒ�c�q����������ā@�����������A��Ēr�ӂ̋{���P���@�p���剤���E�Q���܂����B
���Ȃ݂Ɂ@�L�I�ł�587�N�ɗp���剤�͕a�������悤�Ɍ��������Ă��܂����@�L�I���쐬������
�ō����͎҂̉E��b�����s�䓙�������̑c��̈�������������͂��͂���܂����ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�p���剤�̋��剻�������ꂽ�z�c���c�@���@�䂪���̊L���c���Ə�V�{��Z���̂������̍c�q��
�z�c�������i�����炨���j�Ɗz�c�����u�����o�_�ɕ��C�����ĉ������Ă��܂����B
����ł���l���狌�o�_���Ƃ̕x�ƂɁ@���̂�����̏��͒���m�炳��Ă��������ł��B
��V�{��Z���́@��ɕ��e�̕��Q�ɂ����ā@�����牮���͓��a��̎牮�@�Ŏ牮���U�ߖłڂ��܂��B
��ŏq�ׂ܂��B
�����Ȃ݂ɂ��̖{�̒��ҍ֖؉_�B�搶�́@�x�Ƃ̖���̕��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ʉ��̋u���p���˂ł��B���ԏ�̃o�C�N�͂킪���Ԃł��B
���̂�����͓��������@���ԃX�y�[�X�������ׁ@�o�C�N�ł����s���܂���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ԏ�����ɍs���Ɓ@�˂������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ʂł��B���̓��͂��܂��܋{�����E���̕������|�ƙ��������Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�����̊Ŕł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Δ薼�Ղ����ĂĂ���܂����@������ŋ߂̕��ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�w��̉��̎G�́@���̂ł��Ȃ����̂Ȃ̂ł��傤���B���Ƃ��Ƃ̌Õ��ɂ͖Ȃǐ����Ă��Ȃ������̂ɁB
�o�_�̌Õ��́@�قƂ�ǂ������̎p�ɕ�������Ă��܂����B���̌ł��{�����́@
�Ȃɂ����ʂ̃��[���ł�����̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�q�B�i�т��j�剤��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ԗ��剤�ƐΕP�Ƃ̊Ԃ̍c�q�����ʕ~�c�q�ł��B
�ΕP�͐鉺�剤�Ƌk���P�i�����Ɓj�̍c���ł��̂Ł@���ʕ~�c�q�͏o�_���Ƃ̌��ƂƂ��ɒ��N�l�ږ�
�i�Ђڂ��j�̌����Ђ��Ă��܂��B
���ʕ~�c�q��11�ŕ��L��剤�i�Ԗ��j�̂��Ƒ剤�ɏA�C���q�B�ƂȂ�܂��B
������15�ɂȂ�Ɓ@��̗��̑����Ƃ���L�P���}���čc�@�Ƃ��܂��B
�z�c���̍c���͑��ʕ~�c�q�̍@�ɂȂ肽�������̂Ł@�L�P��傢�ɍ��Ƃ����܂��B
����ő剤�Ƃ͂܂��܂����N�n�̌����Z���Ȃ�܂��B
�L�P�͒��j�����F�l��Z�i�c�����A�̂��̘����剤�̕��j���Y�݁@����ɒ����k�P
�i��̔����剤����肨�����݁@�̍c�@�j�݂܂��B
�����Ĉ�ÊL�P���Y��@���̂��}������܂��B
���̒���Ɋz�c���c�����@�ƂȂ�@�|�c�c�q�i��ɈÎE����܂��j�A�����c�q�i��̔����剤�j���Y�݂܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�q�B�剤�͕������D�܂��@�Ǐ����D�Ƃ����܂��B
������585�N8���ɕa�v����܂��B���ʂ�572�N�Ȃ̂�13�N�̎����ł��B
11�ő��ʂ���24�ŖS���Ȃ�ꂽ�@���ɒZ���̕��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�B�˂͂ƂĂ�������ɂ����ꏊ�ł����B�����ꏊ��������O���O�����܂����B�ē��Ŕ�
�ƂĂ�������Â炭�A���܂��U�����̏f������ɐq�˂�Ɓu�����A�q�B����͂˂��v�Ƌ����Ă��������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̒�������Ă����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�₪�Đ��ʂɗ˂������Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L���˂ł����������G�ɕ����Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�����̊Ŕł����@�ʂɂ������Ȏ��͌�������܂���B�{�����̊Ŕɂ͎��X�ԈႢ�������Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�F����
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�O�q�̕q�B�剤�Ƒ����A�L�P�̍c�q�������F�l��Z���ł��̍c�q���c�����ł��B��̘����剤�ł��B
�����̑剤�͐ΐ�b�n�������Ă��܂����B����ɑ��Ē��N�n�̑����Ƃ͑傢�Ɋ�@���������Ă��܂����B
�����ő����n�̓c�����͐e���������@���b��H�q�ɑ��k���܂����B
���b�Ƃ͎����_�{�̐_���̕��ƂŁ@�L��ɈڏZ���Ē��ÕF�i�L�I�ł͒����Ƃ�����剤�����ł����@
�����P�̕����Ł@�O�ؐ�����f��@���P�Ƃ͕ʂ�Ă��܂��B�j�̑��߂ƂȂ�@
�����ѕP�̎��ォ��{�����J�̖������ƕ��ƂȂ�܂����B
��H�q�́@�܂��ΐ�b�̎傾�����l����l�����n�E���Ă������B�����Ċ��ɐΐ�b�Ƃ։ł��ł���
�����n�̕�P�𗣍������ā@�c�����ƌ������@�����n�̌��W��}�邱�Ƃ�i�����܂����B
��P�͊��Ɂ@��C�l�̍c�q���Y��ł��܂������@�ΐ�̐b�����ƕʂ�ēc�����ƌ������܂��B
�a��ŐQ����ł����@�����剤�̂��Ƃց@��H�q�̐i���Ō������ɖK�ꂽ�c�����Ɂ@�����剤��
���̑剤���������Ɓ@��b�̐ΐ�Y���ɓ`���܂��B
�������Y���̒�̋����������́@�����܂ő�Z�ł���R�w��Z�����̑剤���ƌ�������܂��B
��H�q�́@����͔����剤�̈ӎv�ɔw�������Ɓ@�������W�߂ā@���������n�E���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
629�N�ɓc�����͑��ʂ��@�����剤�ƂȂ�܂��B������630�N�ɕ�P���c�@�Ƃ��܂��B
��P�͘����Ƃ̊ԂɁ@����̍c�q�i��̒���Z�j���Y�݂܂��B
���̊���̍c�q�ƒ��b���q�̌R�����@641�N3���ɓ˔@�@��b�ΐ�Y���̖L�Y�̓@������͂�
�n�E���܂��B�卋���ΐ�b�Ƃ��������Ȃ��@�s�ӑł��ɂ��|����Ă��܂��܂��B���q�̉��ł��B
����̍c�q�͗Y���n�E�̌��тŁ@��Z�Ɏw������ā@����Z�𖼏��܂��B
���̔N��10���ɘ����剤�͖v���܂��B����������Z�ƌÐl��Z�Ƃ�����l�̑�Z������̂ŐՌp�������܂�܂���B
������643�N�ɕ�P�c�@�́@���瑦�ʂ��ā@�c�ɏ���ƂȂ�܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��P�c�@�͒���Z�����̑剤�ɂ������Ǝv���܂����@�����剤�ɂ͐�ȂƂ̊ԂɁ@�Ðl��Z�����܂��B
�����Ł@�����Ⴂ����Z�����̑剤�ɂ���O�Ɂ@��̌y���������|�C���g�̑剤�ɂ��悤�Ǝv���܂��B
���Â�������Z�p���𗘗p�������@�Ɠ����ł��ˁB
�y�����Ăт��āu�Ðl��Z���o�Ƃ�������@���O���N�ɂ���v�Ǝ��������܂��B
�y���́@�͂��育�Ƃ����ČÐl��Z���o�Ƃ����ċg��֒ǂ����܂����@�Ðl��Z�͍ŏI�I��
�n�E����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
645�N�Ɍy���͑��ʂ��ā@�F���剤�ƂȂ�܂��B���������G�����X���n�E�����肵���̂Ł@�l�S������
�������s����ɂȂ�܂��B���g���ÎE��������ā@��g�̊e�n��_�X�Ƃ�����@�L�n����ɓ���������
���܂����@649�N�ɓ�g�L��{���������@�����Ɉڂ�܂��B
���̌�@�N����賂ɕς��@������̋A���m�@����������쟺������̈ӌ������Ē����W������
�i�߂Ă������Ƃ���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����čF���剤�͂킪�q�@�L�n�̍c�q�����̑剤�ɂ��悤�Ɖ����n�߂܂��B
���̂܂܂ł͊�Ȃ��Ɗ���������Z�ƒ��b���q��654�N�Ɂu�s��Ɉڂ��v�Ɛ錾���ā@�F���剤�̍c�@��
�Ԑl�c�@�ƂƂ��ɔɈڂ����B
�Ԑl�c�@�́@�F�����n�E���ꂽ�Ðl��Z�̖��Ł@�Z�Ɓ@���̎q���B���@�S���F�����n�E���ꂽ�̂�����ł����ƌ����B
��g�L��{�ɂƂ�̂����ꂽ�@�F���剤�́@�}���ɐ����͂������ā@�Q���ނ悤�ɂȂ�܂��B
654�N�̕��ɐQ���剤�̌������Ɂ@�Ԑl�c�@���@��g�̋{�������܂����@���̎����̂�
�剤�͋}�����܂��B
���N��655�N�ɊԐl�c�@�͑剤�A�C��錾���܂��B
�ƌ������ƂŁ@�F���剤������ɑ����A����ɗ��p����A���b�̊��q�̂ǂ������d���ɂ������Ď���
����ȑ剤�̈�l�ł��B
���Ȃ݂ɂ��̂ǂ������~�]�̒��b�̊��q�́@��̐��Ɏ����̖��O���c��̂������@���b�̊����Ɖ�����
���̌㒩�삩��@���X�̉A�d�̂��J���ɓ�������Ⴂ�@���̌��N�ȏ㒩���H�����ɂ��ē����Ƃ͐������т܂��B
��������̋߉q���������̊��q�̎q���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̎���@�ł�̐H���ɗ^���ā@���S������Ƃ����̂́@���ʂɂ����Ȃ��Ă����̂ł��ˁB
�u���̂��}�����܂��v�Ə������̂��������ł��ˁB
�Ⴆ�@�C�N������������Ł@��a���肵�Ă������̓c���Ԏ�i���N�l�ږ��̎q���j���i�R����������a����n����
���͂��L���đ剤�̂悤�ɐU�镑���܂��B���̒n�̓^�W�}���Ȃ܂��ā@�^�C�}�i�c���j�Ƃ����܂��B
�������@���ځi�����߁j���i��̑��薼�͐��m�j�́@���o�_���Ƃ̕x���c�F�ɏo���𗊂݂܂��B
���c�F�͖쌩�Ɩ��O��ς��đ�a���肵�ā@�c���Ԏ�̌R�����R�U�炵�܂��B
���̎����́@�����K���i�����܂̂��͂�j�Ɩ쌩�̏h�H �i�݂̂̂����ˁj�̑��o�̎����ƌ����b�ɒu���������ā@
���o�̎n�܂肾�Ɓ@�L�I�ɏ�����܂����B
�܂������@�����A�s�䓙�͂Ƃ�ł��Ȃ��@�a���̗��j��P���Ȃ����̂ł��ˁB
���̌�C�N�����͈�鉤�Ƃ�|���@�������ɘa���̑剤�ƂȂ�܂��B
���̌��тŖ쌩���c�F�́@�C�N���剤����@��a�̈��A�֗]�̕x�Ƃ̗̒n������A�܂��h�H�̏̍���Ⴂ�܂��B
�����ā@�쌩�̏h�H �Ƃ��ăC�Y���A���r���ɂ��܂��ܗ���������C��̒n�i���̕��Ɍ�����s�j�Ŏ��ڑ҂�
�ł��ā@�}���������܂����B��ł킩�����̂ł����@���̉Ƃ́@���N�l�ږ��̎q���ƌ������Ƃ������̂ł��B
�ږ��͍ŏ��a���ɗ����Ƃ��ɃC�Y���ɏ㗤���悤�Ƃ��܂����@�o�_�̝|����邩�@�ƕ������
�C�����Ɠ����@�㗤�����ۂ���܂��B
���̌�o�_��������]�X�Ƃ��܂����@�l�̂��߂Ȃ��R�ǐ�̒��F���n�тɏ㗤��������܂���
�l���Z�߂�悤�Ɋ�����@�r���H������ς������Ɓ@�������Əo�_������ł����ƌ����܂��B
���S�N���������q�����@���̎d�Ԃ�������Ȃ�ā@���N�l�̎q���͂��킢�ł��˂��B�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����͍F���˂̒��ԏ�ł��B��̋u���˂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ʐ̕~���l�߂�ꂽ�Q��������Ă����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ʏ�͂����܂ł�������܂���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������ɓ��ꂽ�̂Ł@���ʂ������Ă��炢�܂��������ɕ��ʂł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�̂̐H���蒤��Œ������悤�Ȗ��̂��鎚�̂ł��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F���˂͒|�V���X���ɖʂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�|�V���X���͐̂̊����ō��̖�l���������܂���ł����B
��g�̋{����߂�ʂ艓�֎��铹�H�œ������L�������Ƃ����Ă��܂��B
���̎ʐ^�̓��͋����Ƃ�������̂Ł@���͍���166�����ɂȂ�@�������H�ł��B
���E��Y�F��Ó��̏��ӘH�A���ӘH�A��ӘH�A�ɐ��H�ȂǂƂƓ��l�Ɂ@�̗̂��j���̓A�X�t�@���g��
���H�ŃY�^�Y�^�ɂ���Ă��܂��B���̂悤�ɂ��ꂢ�Ɉێ�����Ă���̂͂ق�̈ꕔ�ł��B
���̒|�V���X����F��Ó��A���Γ��Ȃǂ�����Ɣ߂����Ȃ�܂��B�̂̐Ώ����͂��������ꕔ��
�قƂ�ǂ��@�A�X�t�@���g�̍�����n�����A�ѓ��Ŕj��Ă��܂��B���ɂ͍��쒬�Γ��̂悤��
�S���t��̒����������Ƃ����@��펯�ȁ@���E��Y�̎Q�w��������܂��B
���{�̖�l�̃��x���̒Ⴓ�������Ă��܂��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�߂������@���̂R�֑���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
64�@�u�߂������v�K��L�@����3
���q������3
���{��͓��S���q���u�߂������v��q�˂��L�^�Ɛ������q�̍c�q�̏o�_�ł̋O�Ղ��ڂ��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��V�{���q�͗p���剤�ƌ��䕔�Ԑl�c�@�̍c�q�ł��B
�p���剤�́@���Ƃ��Ɛ��Ï��邪�@����̍c�q�̒|�c�c�q��剤�ɂ���O�́@�����|�C���g��
�剤�̂͂��ł����B
���Ï���́@�Z�̎q���̏�V�{���q�ɉ䂪���i�L���c���j���łɍs������قLjꎞ�͂��킢�����Ă����悤�ł��B
�L���c���̑��q���@�z�c���̍����Ɠ��u���ł��B����l�͏o�_�Ŋ���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����2�̖`���ŏ����܂������@587�N��4���ɕ����牮�ƒ��b���C�͗p���剤���E�Q���܂��B
�p���剤�̍c�q�̏�V�{���q�͓���16�ł������@���Q�S�ɂ����ā@�ΐ�b���ÂƂƂ��Ɂ@�����h�����W����
7���ɓ����牮���B��Ă����@�͓��a��i���̑��{�����s�a��t�߁j�̎牮���P���E���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����s�̏a��_�Ђł��B���͏a�쒬�ł͂Ȃ��@�A�����ɂ���܂��B�^���ŗ������16���I��
�ړ]�����Ə����Ă���܂��B�������̐_�ЂȂ̂Ł@��������i�`�����j���J���Ă��܂��B
�͓��̍��a��ɕ����牮�̖{���n���������Ɠ`���܂��B
�����֏�{���q�R���U�ߍ���Ŏ牮��łڂ��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��V�{���q�͐폟�F��Ɂ@�M�M�R���쑷�q����K��ċF�����Ƃ���Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���쑷�q���ł��B�M�M�R�R���ɂ���@�ƂĂ��傫�ȌÙ��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���q�����̂������ʂ肩����Ɓ@������V������ā@���q�ɕK���@�������������ł��B
���ꂪ�ДN�A�Ղ̓��A�Ղ̎��������������Ł@����������Ƃ���ɌՂ������Ă���܂��B
�_�l���l�E���̕��@�������Ă��ꂽ�Ȃ�āA�ق�܂����ȁI
���쑷�q���K��L�͂�����ł��B
https://blog.goo.ne.jp/yochanh1947-koyotazune2015/e/03620c9fbac23be3bcb1a9e5d620a862
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��V�{���q�́@16�Ɩ����Ⴉ�����̂Ő����P���@�͏������m�c�q�i�����P�̕��q���j���剤��
�ꌘ���P�̎o�̐ΐ쏬�o�N�Ƃ̊Ԃ̍c�q�j��剤�Ɏw�����܂��B588�N8���ɏ������m�c�q�͑剤��
���ʂ��܂��B�i��̑��薼�͐��s�j
����4�N���592�N�ɒ|�c�c�q���ÎE����܂��B�Ɛl�͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ����������ł���
�|�c�c�q���S���Ȃ�@�����̎q�����̑剤�ɑ_���Ă����@���s�剤�̍@�̏���q�܂炵���ƕ�����
����̐����ȋV���̐ȂŁ@���s�剤���S�E�����Ƃ����O�㖢���̎������N�������B
�Ɛl�͓����i��܂Ƃ̂���j�^��Ł@�Ɛl�͌������ׂ̈ɑ����@�ΐ얃�Ñ�b�ɂ�菈�Y���ꂽ�B
���@�̖�E�ł͎����̎q���������Ȃ��ƍl�����@�����P���@�́@�����N�Ⴂ�����c�q���N�ɂ���܂ł�
�P���g���剤�ɂȂ�܂��B
593�N12���Ɋ��������L�Y��{�ő��ʎ����s���@�L�Y�剤�ƂȂ�܂��B�i��̑��薼�𐄌Áj
�����ď�V�{���q�����̑剤�ɂ���Ɩ��ā@�剤�⍲���Ƃ��܂��B�i�ې��ƋL�I�͕\�L�j
��������V�{���q�̐l�C�����܂�ɂ�ā@�L�Y�剤�͂킪�q�����̍c�q�̎����S�z�ɂȂ�
��V�{���q�̐��͂��킮�ׁ@���q�̍ȂŖ��̊L���c����L�Y��{�Ɉ����グ�����@�L���c���̎Y����
�����Ɠ��u���������o�_�̒n�ɕ��C�����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
603�N10���ɏ����c��{���������Ĕ����c�q���������܂�����V�{���q�ɉ������ā@�����𓌋{�i�c���q�j
�Ə̂��܂��B
���̔N��11���Ɂ@��������������{�ŏ�V�{���q�́@��R�̏d���B���W�߂đ剤�A�C�錾�����܂��B
����ɋ������@�L�Y�剤�Ɣ����c�q�͑����A�n�̏d���B���W�߂đ��������B
�����Ă��ׂĂ̊�����12�̊K���ɕ����ā@���̐F�ŊK����\���Ď�����Ɣ��\�����B
����́@��ό��ʂ�����@12���ɂ��ׂĂ̏d���B���W�܂�A���ʏ\��K�̎��^��������܂����B
�܂������ɑ��@�P��10�����߂��B����͓ޗǎ���ɂȂ萹�����q����߂��\�������@��
����������ꂽ�B
604�N���U�Ɂ@�����c�q�͑剤�ɏA�C���@�����剤�Ə̂����B�n���̍��������X�ɏ����c��{�ɏW�߂�
�e���̗̒n�̈ꕔ��剤�ƂɊ�i�����ēԑq�����B
������{�̏�V�{�剤�͌Ǘ����@�剤�̖��͗L�������ɂȂ����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�ɂɂȂ����@���i�剤�ɂȂ�Ȃ�������V�{���q����̑m����e���͖@���ƌĂj�͕��T�̕��⍑�j
�̍쐬�ɑł����B
�������{�ɏZ�ޑ��q�̔܂̈�l�ɓߕ��k�w�l���@���܂��ܔ����{��q�˂Ă����Ƃ��Ɂ@���̍��j��ǂނ�
���Ï���̎��̑剤�͏�V�{�剤�Ə����Ă���@�����̕��e�̔����剤�̖��O�͂ǂ��ɂ��Ȃ������Ƃ����B
�����납��@��V�{���q�̑ԓx�i�剤�̖��ł��鎩�����@�܂ƌĂ��ɋk�v�l�ƊF�ɌĂ�����
���q�̕�̌��䕔�Ԑl�O�c���@�Ɠ�����������@���̑��������j�ɕs�������������Ă����̂�
��x�ɔ������ā@�E�ӂƂ����B
621�N���Ɍ��䕔�Ԑl�O�c���@���ˑR�|�ꂽ�B�������ɖK�ꂽ���q�Ɂ@��́u�k�v�l�ɓł�ꂽ�v
�ƌ������Ƃ����B����Ȍ㑾�q�͔����{�ł͐H������߂Ĕ܂̑V���P�̖O�g�{�ʼn߂������Ƃ����B
����ŋk�w�l�͂܂��܂����q�ނ悤�ɂȂ����Ƃ����B
���q�̕�́@���̔N12���ɖS���Ȃ����B���N1��22���@��N�̂Ђƌ��̖@�v�����{�ōs���@�Q���������q��
�V���P���H����ɑ������œ|��ĖS���Ȃ����B
�����o�_�ɕ��C���Ă��đ��V�ɎQ�����q�̑��q�́@�z�c�������́@�Z�őr��̎R�w���ɓŎE��������
�o�_�ɋA���Ă��ā@�o�_�����Ƃ̕x�Ƃɂ��̂��Ƃ�`�����Ƃ����B
�z�c�����������u�����@�s�ɋA��C�����@�o�_�̒n�Ő��U���I���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�o�_�̓��u��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�C�Y���ɕ��C�������u���́@�����s�ł͓��Ə̂��Ă��܂����B�����o�_�ɂ́@�Ԗ��剤�̎����
�Ԗ��剤�̎w���Ł@���u�̔������h������ā@�Ԗ��剤�̕��I�z�h�剤�̌̋��o�_�Ɂ@�Õ�����葱���Ă��܂����B
�s�ł͎���Ɂ@���N�n�̑����Ƃ����������߂Ă����̂Ł@���́@���N�n����̔��Q�������
���N�n�̖��O�̓��u�Ƃ����̂ł��B
���u���́@�z�c���剤�����̊L���c����ʂ��Ĉ����p�����@�L�x�ȍ��͂����@�剤�̊�]����
�����_�Ђ̌��݂ɖv�����܂��B���@����n�ɏ�芥�����Đ�����D�œ����������������������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
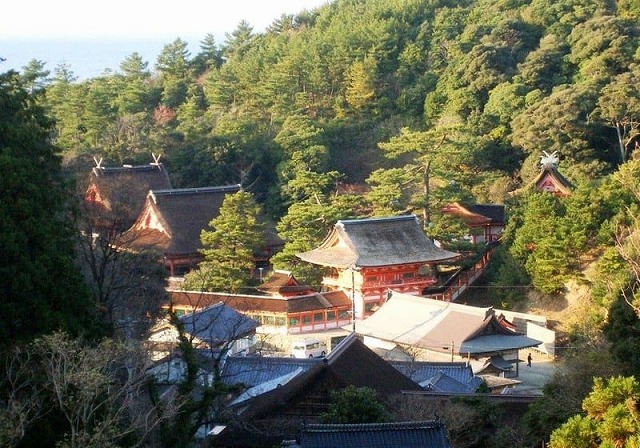
�����_�Ђ̑S�i�ł��B��R�̋{������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����͂��̈�Ł@�����݂̋{�ł��B�[���Ɍ����Č��Ă��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�q�B�剤���ݒu���ā@�z�c���剤����@���u���i���j�������p�������́@���z�M�ł��@
���ɗ[����q�ނƂ����܂��B����ŗ[���Ɍ����Č��Ă�ꂽ�̂ł��傤�B
�����_�Ђ̊������ā@�z�c���剤�͑傻����ꂽ�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎ʐ^�͏o�_�s�̍֒J�ɑ����z���ꂽ�@�o�_�����Ɛ_��b�Ƃ̉��Ƃ̕�@�l���ˏo���u��̈�ł��B
���u���́@�������ő��c���ꂽ�@�㉖��z�R�Õ��ɑ����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ���̓��u���̌Õ����甭�@���ꂽ�i�X�ł��B
���̂ق������̑����⑽���̃u���X���b�g�ƃl�b�N���X������܂��B
�������ʂ�l�b�N���X�Ȃǂ̑����i�͉��������g�ɕt���邱�Ƃ�������܂���ł����B
�u�o�_�퐶�̐X�����فv���w�L�͂��̃u���O�́@2014�N6��18���̋L���ɂ���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ�������ꂽ���u���̎ʐ^�ł��B�����ق̃p���t�ɍڂ��Ă���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�o�_�̍����i�����炨���j
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����Z�́@�z�c�������́@�����@��̓��u���Ƌ��ɏo�_�̒n�ɓs���畋�C���Ă��܂����B�@
�o�_���ӉF�i�����@�[���̏��]�s��������_�Еt�߁@�j�S�@�ɐl���̐��q���Ƃ��ĕ��C����Ă��܂����B
�����ē������L�x�ȍ��͂Œ�̌��Ă������_�Ђ̕��Ђ����Ă��܂����B
�i�����s����144�Ԓn�@�������邻���ł����܂��s���Ă��܂���j
�����ē����Ƃ��Ă͒����������d���̂���@�厛�@�̋��ݎ��i�����s������j�����Ă܂����B
���������͌����͂Ȃ��@�c�^�̂��Ƃ�����݂̂ł��B
�����č������@���̒n�Ő��U���I�����܂����B
���̂��悪�@���c�R1�����Ł@�����͐��O����Õ���z���Ď��˂Ƃ��Ă��܂����B
���c�R1���Õ����甭�@���ꂽ�����̑����ɂ́u�z�c���̐b�v�ƌ����������ǂ߂Ĕ��������傫�Șb��ƂȂ�܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���c�R1���Õ��ł��B�����̂���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���@���ꂽ�����ł��B���̌Õ��̔��@���́@���]�s���̕��y�L�̋u�ɓW������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���y�L�̋u���w�L�́@���̃u���O�́@2015�N12��13���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�����]�s����ψ���̐����ł́@���̂�����̌Õ��i���c�R�Õ��Q�A�o�q�ˌÕ��Q�j�͏o�_��Ћ{�i�̑c��o�_������
�̂��悾�Ə����Ă��āA�ē��l�̏f����������������܂����B
���c�R1�����́@�ȑO�K�˂��u�R��o�q�ˌÕ��v�̂����߂��ɁA������������ɑ���ꂽ�B�@
�x�Ƃ̓`���ł́@�x�Ƃ̉��˂ׂ̗Ɋz�c���̐b�̉�������ꂽ�Ƃ����B
����͓����@�s���畋�C���Ă����@�z�c�������ł���܂��B�o�_���Ƃ̑��F�a�����Ƃ̉z�O�h��{�ƁA�U�P�ɗ{�q�ɍs����
�ƋƂW�����ā@�l�]���W�߂��@�s�Ɍ}����ꂽ�̂��@�I�z�h�剤�i�p�́j�Ł@���̑��q�q���j���剤�i�Ԗ��j
�̖����@�z�c���剤�i���Áj�ł��B
�z�c���剤�̌Z�A�L���剤�i�p���j�̑��q���@��V�{���q�i�������q�j�ł��̑��q���@�z�c���̐b�����ł��B
�����́@�����@��̓��u���Ƌ��ɏo�_�̒n�ɓs���畋�C���Ă��܂����B�@�o�_���ӉF�S�ɐl���̐��q���Ƃ���
���C����Ă��ā@���̒n�Ő��U���I�����܂����B
���̂��悪�@���c�R1�����Ł@�����͐��O����Õ���z���Ď��˂Ƃ��Ă��܂����B
�Õ������i�́@���]�s���̕��y�L�̋u�ɓW������Ă��܂��B
���y�L�̋u���w�L�́@���̃u���O�́@2015�N12��13���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�����]�s����ψ���̐����ł́@���̂�����̌Õ��i���c�R�Õ��Q�A�o�q�ˌÕ��Q�j�͏o�_��Ћ{�i�̑c��o�_������
�̂��悾�Ə����Ă��āA�ē��l�̏f����������������܂����B
�n������Ȃ��́B�����Ƃ́@���������̏Z�ޏo�_�̌Ñ�j������Ȃ��ƁB
����̎q���́@��B�������Ƃ̑�������ɓ����R�̕ʓ����i���N�l�q�{�R�̎q���c���Ԏ�Ȃǂ̌R�j
���@�o�_�R�̌x���̎蔖�ȏꏊ���@�ē����ďo�_���Ƃ̖ŖS�Ɋ��A���̌��тŏo�_�����Ƃ�
���Ă��炢�܂����B
�C�N��������a���肵�Ă��ɑ�a�̑剤�ƂȂ������ƁA�U�ߖłڂ����o�_�̐i���R�i�ߊ����o�_�����Ƃ���
�����̏\�獪���h������ā@�������Ƃ̉��{�ɒ��C���܂��B���̏��]�s�_���i�������j�_�Ђł��B
�������o�_�����ɂȂ��Ƃ�����҂��Ă����@���ڂ̎q���̉ʈ��̓C�N���剤�Ɏ����̉ʂ��������т�A�Ȃ�
�i���ā@���������o�_������|�������l�҂��ƌ����ɑi���ā@����Əo�_�����ɂ��Ă�������Ƃ������Ƃł��B
�i�����̂�����́@�u�Î��L�̕ҏW���A�e鰘a���̓s�A�o�_�Ƒh�䉤���Ȃǂ��Q�Ƃ��Ă��������B�j
���]�s����ψ���͔n���ł��˂��B�����̒����ȕ����̖��ځi�قЁj�̎q�����@���������̑c�悪�E����
�o�_���Ƃ̕x�Ɓi���Ɓj�̂���Q�̒��Ɂ@�����B�̂�������킯������܂����˂��B
���̈ē��l�̏f������ɂ́@�֖؉_�B�搶�̖{��ǂ�Ł@�����ƕ����Ȃ����Ƃ����Ă����܂����B����Ƃ�Ƃ��Ă��܂����B
���Ȃ݂ɖ��ڂ̎q�������̏o�_��Ђ̋{�i�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���q���@����3�@�͑����܂��B
���́@�g�p���ގ��̕揊�̂���b�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�b������O�̒��ԏ�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�傫�Ȏ�h��̎R������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��������������܂����A���ꂪ�{���Ȃ̂ł��傤���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
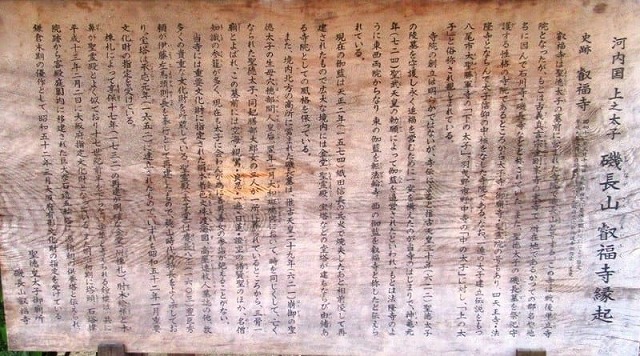
���̉��N�ł��B�����ǂނƁ@���̕揊�ɂ́@��V�{�@���̐���@���䕔�Ԑl�c�@�A��V�{�@���A
�����Ė@���̍@�̑V����Y���̌�O���̂�������������Ă��邻���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L������������ā@���q�˂i�݂܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���q�˂̓����ɂ��@�R�傪����
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���E���ꂼ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�m���l����������Ⴂ�܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������ƕ揊�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����͋����ł͂Ȃ��ā@�{�����̊Ǘ��̂��悾�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�剤�͗˂Ə�����Ă��܂����@���q�͗˂Ə�����Ă��Ȃ��ā@�u�揊�v�Ɠǂ߂܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ�[�����Ȃ̂ł��傤���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�]���Ŕ`���ƎO�l�̕��l���@�荞��ł���܂��B��O���̕揊������Ȃ̂ł��傤���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���q�˂��狫���������낵���Ƃ���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��������̕�X���@���������Ɍ����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
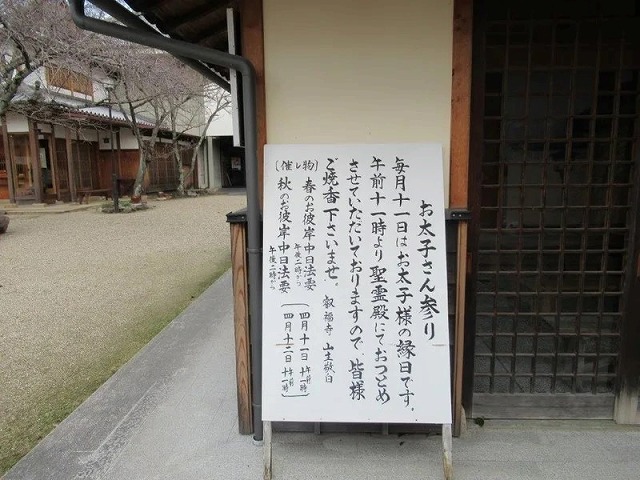
����11�����@���q�̖����ʼn����̖@�v�����邻���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����ꂽ�������q��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�l�X�ȉA���Ȗd���Ł@������l��������オ�������������̑��q���s�䓙�ł��B
�������ւ̔�������p�\�̗��ł͔j��ā@�V�����ɂ͕s�䓙�́@�n���n�̓c�ӉƂɉB��Ă��܂����B
���̂Ƃ��Ɂu���q�v��ǂ��d�p�Z���w�т܂��B
�������Ɏ���ɓ��p�������@�Y���Ȃ̔����ɂȂ�@���G�����X�Ɗׂ�Ė��E���܂��B
�����ēޗǎ���ɂ́@�E��b�ƂȂ�@�L�I�̕Ҏ[���n�߂܂��B
�s�䓙�͑��������Ɗ`�{�l���C���ċւ��閧���ɋL�I���������܂��B
�i�֖؉_�B���@���t�̂̓V�ˁA�Î��L�̕ҏW���@�Q�Ɓj
���̒��ŏo�_�����n�c�̐��V���䎨�i���䎨�_�j���܂˂ā@��V�{���q���@�L�����c�q�i�Ƃ�Ƃ݂݁j�Ɩ��t����
��x�ɑ�R�̐l�̘b���������Ƃ��@�������ɓ`�����Ă����L���X�g�̂܂˂����ā@�n���̌ˌ��Ő��܂ꂽ�Ƃ���
�X�ˍc�q�i���܂�ǂ݂̂��j�Ɩ��t�����B�܂������剤�̊���10���̋��P���@17�����@�Ƃ��đ��q�̋ƐтƂ݂��������B
�܂��s�䓙�́@��F�̍c�q�̑\���@�ߍ]�W�C���w�������͔��m�ɍ̗p���@���̑剤�̖����������ŕ\�L�������B
�ł�����@���̂Ƃ��ȑO�̑剤�̖��́@���ׂĊ������ɏ���������ꂽ�̂ł��B
�s�䓙�́@�剤�Ƃ܂�V�c�Ƃ�_�i�����čc���j�ς�n��グ�ā@�������O��I�ɂ���𗘗p����
�������₷���Ƃ̎d�g�݂�n��グ�ā@�Ȍ��N�ȏ�ɓn��@�c���𗘗p�������ā@�����Ƃ͓���ƁA����ƁA�߉q�ƁA
��i�Ɓ@�Ȃǂɕʂꂽ���̂́@��т��čc����H�����ɂ��ĘA�ȂƑ����̂ł��B
�܂���{�̗��j���䂪�߂ā@�Ȃ̓s���̗ǂ��悤�Ɂ@���������̂��@�s�䓙�ł��B
������R�̐l���L�I�̎����Ɏ��t����Ă��܂��B���̎R���Ԃ̂e����̉��l�������̈�l��
���̂��̃u���O�ɓG�ӂ�����@�䂪�Ƃ̗��R�̊�N�R�Ł@����тɁ@�����U���I�ȃR�����g�����܂��B
�L�I�̎����Ɋ��S�Ɉ��ݍ��܂�Ă�������Ⴂ�܂��̂Ł@���l�̈قȂ�ӌ����������S�ɍǂ��ł����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��V�{���q���J��@��������������ď������@�����̑m���B���e�n�ɎU��܂����B���܂Ŕ����������{������
�n�܂肾�Ɓ@�������Ă����m���B�́@��V�{���q�����������Ė��O���L�߂����ƍl���܂��B
�����đ��q�䂩��̎l�V�����Ȃǂł��@���q�̑������q�ݎn�߂܂��B�����đ��q�̑������A�V�ːU����������b
�����X�ɍ���čL�߂��܂��B
���q�̎���129�N�o���@751�N�ɉ������̂Ȃ��Ł@���Ɂu�������q�v�ƌ������t���o�ā@�����J�c�̕�F�Ƃ���܂����B
���̐������q�́@��V�{���q�A�R�w��Z�A���q�̕��̗p���剤�̎O�Ђ����̂�����F�Ƃ����܂��B
�p���h�̕����牮�ɏĂ��E����ď}�������p���剤�͕��������F�����ŏ��̑剤�ł���A�R�w��Z�͔�������
���{�������ĕ����ɐs�����܂����B�܂肱�̎O�҂̎��т��܂Ƃ߂Đ������q�Ƃ����̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���������ɂ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���Ƃ͓��{�L���̗R������ƌn�ł��B
���ツ�}�g�剤�u�V�̑��_�v�͈��Ƃ̃^�^���\��P�i�����Ƌʈ˂�P�̕P�j�ƌ������A���̍c�q
�u���쎨�i�ʂȂ���݂݁j�v�����ڑ剤�ƂȂ�܂��B���쎨�̓^�^���\��P�̖��u�\��˂�P�v�ƌ�����
�ʎ�Łi���܂Ă݁j�Ɣ��䎨�̍c�q�����܂�܂��B
���ʂ��p�����̂́@��̋ʎ�Łi���܂Ă݁j�Ł@���䎨�́u���b�Ɓv�̎n�c�ƂȂ�A���̉ƌn���A�ȂƑ���
�����ޗnj��c���{�̑��_�Ђ̎ЉƂ�����Ă��܂��B���Ƃ��Ɛb�͏o�_�����������ƌn�ł��B
�����ċL�I����҂̑��������́@���Ƃ̎q���Ł@���_�Ђ��J���Ă��܂��B
���_�ЖK��L�́@���u���O��2015�N12��26���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
���������́@�L�I�������グ�����ƁA�L�I�̔閧����邽�߁@�l���C�Ƌ��ɕs�䓙�ɂ��H����܂��B
���������́@�K�^�i�H�j�ɂ�����c�̒n�@�o�_���Ɠ����Ƃ̌��Ƃ̗̒n�ɗH����܂��B
���������́@�H����Ȃ�����@�閧���Ɍ���ƂƘA�������u�����͏o�_���Ƃ̌��������@���b�Ƃ̖����
�R���Ԑl�̖��O�Ł@�H����Ȃ���L�I���������ꂽ�v�Ɠ`�����ƌ����܂��B
�����āu�Ñ�o�_���\����̉��̖��O���Î��L�ɏ������ꂽ�v�Ɠ`���A����ɑ��Č��Ƃ͏o�_���Ƃ��\����
������q�ׂ��Ɠ`����Ă��邻���ł��B
�����������H����ā@�]���𑗂����ꏊ�́@���������]�s�́u�ӉF�̐X�i�����̂���j�v�ň�������_��
�i�������₶��j�����Ă��Ă��܂��B
��������_�ЖK��L�́@2014�N4��10���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̍��́@�֖؉_�B���@�����Ə@�������@�@�匳�o�Ł@�@�Ɋ�Â��ď����܂����B
�܂����̑��̗��j�́@�䉾���ƃ��f���A���t�̂̓V�ˁA�K�̐_�Ɨ��A�o�_�Ƒh�䉤���A�Î��L�̕ҏW���A
�e鰘a���̓s�A�o�_�Ƒ�a�̂����ڂ́@�ȏア������匳�o�łɊ�Â��܂����B�܂��_�ЂȂǂ̖K��L��
���ׂĎ������ۂɁ@�q�˂��L�^�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�u�Ñ�o�_�����䂩��̒n��K�˂āv�g�b�v�y�[�W�͂�����ł��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
63-2�@�j��瑑剤(���قǂ�������)�̑��Ղ�K�˂�z�O���@�@����1
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018�N4��5��
�@�@�z�O�O�������Ƃ̑h�䑍�{�Ƃ֖����肳�ꂽ�o�_�x�ƁA�F���̌N��
�@�@���̔����̐U���̂̑��Ղ�q�˂܂����B�̂��̒j��瑑剤(���قǂ�������
�@�@�[�̂��̑��薼���p��)�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����248�N�Ɏn�܂�@��B���������̑�����ɂ��A�킪���ŏ��̉����ł���o�_�����͓|����܂����B
���������̌���@�o�_�����̍K�̐_�͊e�n�ŐM����A���ɓ��o�_���Ƃ̑c�_�̂�����@���Ȃ�R�@�F��R
�i���]�s�V�{�R�j���J��W��́@���N�s���@�S���ɎU�����o�_���Ƃ̕��m�B�̎q���́@�u�U�Ɓv�ƌĂ��
�F��R�Ղ�̏W��ɎQ�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�������|���ꂽ�Ƃ͂����@�o�_���Ƃ͂܂������̍��͂ƕ��͂������Ă������Ƃ͎����ł��B
���ۂɁ@��B�������Ƃ̃C�N�����͑�a�ɐi�U���Ĉ�鉤�����a���炨���������Ƃ͂����A�����̒��N�l�ږ��i�Ђڂ��j
�̎q���̒A�n�炪����n���ʼn��̂悤�ɐU�����̂𐧌�ł����ɂ��܂����B
�����ŃC�N�����͋��o�_���Ƃ̕x�ƂɁ@�A�n������悤�ɗ��݁@�x�Ƃ̑�c�F�́@�o�_���𗦂��Ċ���n������
�A�n��������ǂ������W�H���֓��������܂����B����ɂ��x�Ƃ̑�c�F�Ɓ@�o�_���Ƃ̑�a���Ƃ̕x����
�́@��a�ɗ̓y�����A��c�F�͕����̏d�b�̏̍��u�h�H�v��^�����܂����B
�����ɂ��ā@�C�N�����͖������ɑ�a�́u�剤�v�i���̎��_�ł͂܂��V�c�Ȃ錾�t�͂���܂���j�ɂȂ�̂ł��B
���̎����͋L�I�ł́u�쌩�h�H�v�Ɓu�����R���v�̑��o�b�ɏ����������܂����B���̎������告�o��
�N���������ŁA�܂������̂����ł��B�������l���Ă݂�Ɓ@���̐푈�����̂܂ܗ��j���Ƃ��ď�����
��B���痈�������̎q���̕������Ƃ��@��a�ɉ���������Ă����@�o�_���ƂƏ����̎q���̘A�������̈�鉤����
���͂Ő������ā@�������Ƃ�����������ā@������s�䓙������Ȏ��������킯���L��܂���l�G�B
���Ȃ݂Ɂ@�쌩�h�H�́u�̂݁v�Ƃ͕x�Ƃ́u�Ƃсv�̂��ƂŁ@�u�����܁v�Ƃ͒A�n�̂��Ƃł��B�܂������c����
�̂����c���͒A�n�炪�n�ՂƂ����n��Ł@�A�n�i�����܁j���Ȃ܂��āu�����܁v�ƂȂ������̂ł��B�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����@��a�ɐi�U�����������Ƃ́u�C�j�G���v�͎����̕��������������h�H������ ��鉤�Ƃ̕F����剤
�ƘA�������R����j��܂��B�F����剤�͖��̓��o�X�P���C�N�����ɍ����o���ā@�����h�H�ƂƂ��Ɉ����̍���
������ā@���������ƂƂ��ė]�����߂����܂��B
�������C��G�剤�i��̑��薼�͐��m�j�͕����h�H�������Ȃ��āA�h�q������܂��B�����m�����q�o�X�P�c�@��
���e�F����ɒm�点�܂��B���������̍��ɏZ��ł��������h�H�́@������Ƃ���Ȃ������@�_���̎p������
���֓���@�o�_�̕x�Ƃɏ��������߂܂��B
�x�Ƃł́@�o�_���Ƃ̍c���剮�P�̎q���ł��镐���h�H���ӉF�̐X�ɏZ�܂킹�܂��B
�����ĕx�Ƃ̕P��^���Č��������A�o�_���Ƃ̏̍��u�b�i���݁j�v��^���u�����b���c���v�Ƃ���
�]�����߂������܂����B���̂��Ƃ������̓��{�̗��j�ɑ傫�ȉe����^���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
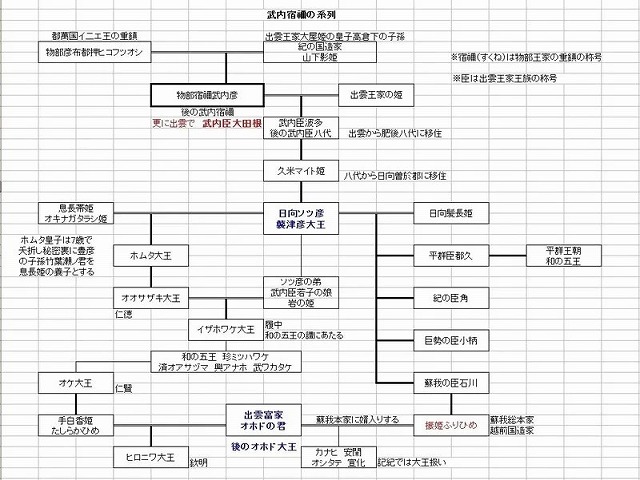
�����b��c���i�����������̂��݁@�������ˁj�̎q������͓��{�j������R�̑剤
�i�������݁[�܂����̂���͓V�c�̏̍��͂���܂���j���a�����Ă��܂��B
�����b��c���̑\�����P�ÕF�剤�Ł@���̌�̕��Q�����i�x�߂̗��j���Ɍ����a�̌܉��j��h��̐b�ΐ�Ȃǂ��q���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ƃ������ƂŁ@�b�͂͂��߂ɖ߂�܂����A�h�䑍�{�ƂƃC�Y���̕x�Ƃ͐e�ʊW�Ȃ̂ł��B
���̑h�䑍�{�Ƃł͐U��䔄�̎���ɂ́@�q���͐U��䔄��l�ɂȂ����Ƃ����܂��B�����ŕx�Ƃ��玟�j��
�F���i�Ђ��ӂƁj�𖹗{�q�ɂ��炤���ɂȂ�A���̔N�̌F��R�̑�Ղɉz�O�̑h�䑍�{�Ƃ���U�䔄���K���
�Q�����܂����B�����đ�Ղ̌�@�F���͐U��䔄�𑗂��ĉz�O�֍s���@���̂܂ܖ����肵���̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�x�Ƃɓ`���`���ɂ��ΐV���̓�l�͂܂��@�U��䔄�̑c��ł���u�����̐b��c���v���J��
�u�����_�Ђ֎Q�q���܂����B���̏��]�s�|��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��������D�ɏ�舢������_�Ђ����܂��B���̏��]�s���o�_���o�_���i���������@�Ɠǂ݂܂��j�ɂ���܂��B
�����͕����b��c�����x�Ƃɓ����ā@�Z�ꏊ�ňӉF�̐X�i�����̂���j�ƌĂ��ꏊ��
�����Ŗ���S�����܂����B���̉��~�Ղɐ_�Ђ����Ă��܂����B
�������_�ЁA��������_�Ђ̖K��L�́@2014�N4��10���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������炵�炭�D�𓌂i�߁A�����̍��őD������܂��B�F���_�ЂɎQ�q����ׂł��B
�F���_�Ђ́@�����h�H���@���������Ƃ��đ�a����ڂ�Z�F���剤�i�����剤�ł͂���܂���j�ɕt���]��
�ڂ�Z�ꏊ�ŁA�C�N���剤���h�q���͂Ȃ����Ƃ����m�点�Ł@����ĂĎp�����������~�ՂɌ��Ă��܂����B
���̐_�Ђ̔q�a�̑O�́@���s�䏊�Ɠ������u�E�߂̋k�A���߂̍��v���A�����Ă��܂��B
�ނ̎q�������R�̑剤���o�����Ƃ��Î����Ă���̂ł��傤�B
���F���_�ЖK��L�́@2017�N10��12���̋L���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�F���ƐU�P�͉z�O�̕���ŏj���������@�u�I�z�h�̌N�v�ƌĂ�ā@�������J�n�����B
���Q�̑��������㓪����̉͌����L���āA�O���`�������B�����ē��{�C���Ղ�ɂ�����ȍ����Ȃ����B
�����ዷ�A����A�z�̍��ɂ́@�o�_���Ƃ̐e�ʂ̈�鉤�Ƃ̑�F�̎q�������������ƂƂ��ďZ��ł���
�u���̌N�v�ƂƌĂ�Ă����B���W���d�˂��h�䑍�{�Ƃ̃I�z�h�̌N�́@�����̖���ƂȂ�
�����̍��X�͂₪�đh�䉤���ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B
���ɃI�z�h�̌N�͓։�̍`����הn�ԂŎR�z�����ā@���i�Ɨ�����M�ʼn^�ѐ��˓��C�Ɠ��{�C���p���q�H��������B
�����ē�g�����a���ʂ�s�ւ͒��ډ����ŗ����̂Ł@�s�ɂ��I�z�h�̌N�̖����͕��������B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̎O�썇���n�_�̗l�q�ł��B���s�{�����s�t�߂ŁA�E�肪���{�O���S���{���A���s�{��R�蒬�A
���������s�ƍ��Ύs�A�������s�{��z�s�A�v��R���A�F���s�Ɠ���g��ł��܂��B���̉Ƃ͉E��O�ł��B
���̐�͖ؒÐ�ʼnE���F����ł��B�����ƉE�Ɍj�삪����Ă��ā@���̐�ŎO�̐삪�������ė����
�Ȃ�܂��B
�h��I�z�h�̌N�͗���̒�����A���P���̎O�썇���n�_�i����A�F����A�ؒÐ�j�Ɍ��Ղ̋��_�ƍL��ȉ��~��������B
���̒n�̐��͎O���ł���A���đ攪��o�_���ƕ����A�����̔��d�g�Ðg�ɉł��ꂽ�ʋ��P�i���ʈ˂�P�j
�̎��Ƃ�����@�o�_���Ɨ̂̈ꕔ���������B�����ɂ͑�R�̏o�_�����ڏZ���Ă���A�ނ�̎q��������
���P���~�ɏW��j��瑂̌N�ׂ̈ɓ����n�߂��B
�܂��֓��̍����Ƃ��@�قƂ�ǂ��o�_���Ƃ̎q�������Ȃ̂Ł@�ނ�����P�̒n�ɏW��@�I�z�h�̌N�ׂ̈�
�����悤�ɂȂ�@�܂��܂��I�z�h�̌N�̖����͂����܂����B
�����̃I�I�T�U�L�i�吝�j�����ł͐e���̓������₦���A���Ƃ̗͂͐��������ł���A�܂肵��
�I�P�剤�i�m���j�A���J�T�U�L�剤�i����j���������Ŗ����Ȃ�Ռp�����₦���Ƃ����B
�����ŃI�I�T�U�L�����̏d����l���@���P�̉��~�ɃI�z�h�̌N��K�˂ā@�剤�A�C�𗊂ݍ��Ƃ����B
�d����l�́@�唺�����Ƌ����̐b�j�l�ł���A�����̐b�͏P�ÕF�剤�̎q���ł���B�i��}�Q�Ɓj
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�d����l�̓I�z�h�̌N���剤�A�C�̏����Ƃ��ā@��X��剤�̃I�P�剤�i���薼��m���j�̍c���ł���
�蔒���P�i�����炩�Ђ߁j���@�ɂ���Ƃ��������������o�����B�I�z�h�̌N�͂��������ő�N�ƂȂ�
�I�z�h�剤���a�������B���������ꂪ�̂��̂����G�Ȗ��������N�����܂��B
�U�P�Ƃ̊Ԃɂ́@�J�i�q�A�I�V�^�e�Ƃ�����l�̑��q�����ā@�L�I�ł͂��̓�l�����̂��剤�����ɂ���
���ꂼ�ꑗ�薼���u���Ձv�A�u�鉺�v�Ƃ��Ă���B
�������蔒���P�Ƃ̊Ԃɂ́@�q���j���c�q���a�����@�̂��Ƀq���j���剤�i�Ԗ��j�ƂȂ�@���̑剤�����
�n�������̍c���ɑ������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����̃u���O�̗��j���e�́@�֖؉_�B���@�u�Î��L�̕ҏW���v�A�u�o�_�Ƒh�䉤���v�A�u�o�_�Ƃ�܂Ƃ̂����ڂ́v
�u���t�̂̓V�ˁv�A�u�䉾���Ƃ��̃��f���v�A�u�����Ə@�������v�@�@
���F�F���u�e鰘a���̓s�v�A�u�Q�@�̖������Ձv�@�J�˒�F���u�K�̐_�Ɨ��v�@��������匳�o�łł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�j��瑑剤�̑��Ղ�K�˂�z�O�������̂Q�֑���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�j��瑑剤�̑��Ղ�q�˂�z�O�����@����2
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���H�_�ЂƑ��H�R�����@����s���H
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���H�_�Ђ̒�������́@�����́u���H�_�Ђ̎}�����v�������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�͑傫���ė��h�ł��B���傤�nj������̋L�O�B�e���s���Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
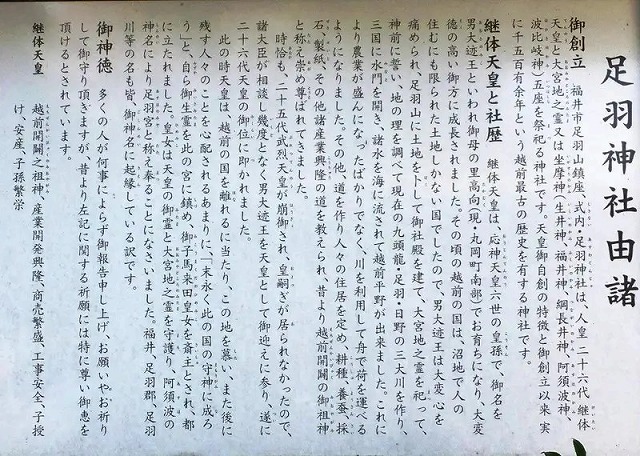
���H�_�Ђ̗R�������ł��B�܂��ł����グ�A���b�����̓��{���I�����̂܂܉L�ۂ݂ɂ���
������Ă��܂��̂Ł@�_�b���ɂȂ��Ă��܂��B
�L�I�̍쐬�𖽂������������s�䓙�������@��Ԍ����������Ƃ��u�����B�̑c��̐`���l��
�n���l�̏����̎q���B���@�|�����o�_���Ƃ̖���̎�l���@��a�̑剤�Ɍ}�����v�ƌ������Ƃł��傤�B
���̂��߁@�I�z�h��N�́@�z���^�剤��6���q�����Ƃ��Ă��܂��B����������͖��炩�ɊԈႢ�ł��B
���z���^�剤�ƃI�z�h�剤�Ɍ����W�͂Ȃ����A����ɍ��b�̋L�I�ɋ���z���^�剤����11��ڂ��I�z�h�剤�ł��B
���ۂ̓z���^�剤�̌�̓I�I�T�U�L�i�m���j�A�C�U�z���P�Ɏn�܂�a�̌܉�
�i�~�c�n���P�A�I�A�T�d�}�A�A�i�z�A���J�^�P�j�A�I�P�i�m���j����Ƀ��J�T�U�L�i����j���̎����I�z�h��9��ڂł��B
�����Ĉ�ԋ����̂��@�I�z�h�N�́@�U�P�̗��̍����i�����ނ��j�Ő��܂ꂽ�Ƃ����̂ł��B
��قǁ@�����̋��֍s���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Ђ��o�ā@��������o��Ɖ��̍ŏ㕔�ɃI�z�h�剤�̐Α�������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���J�̍��߂�I�z�h�剤�B�����̐�͕���s���̎s�X�n�Ł@�w���ɂ�
�^�����ɋP����̔��R���@���̐�Ɍ����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����_�Ё@���䌧���s�ۉ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����_�Ђ̓}�C�i�[�Ȃ̂��ߏ��̐l�ɕ����Ă������m����܂���ł����B�J�[�i�r�������Ă���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ƐΔ�͐V�����ė��h�Ȃ̂ł����A�Ђ����킢�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ȗ{�a���|�c���Ɨ����Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�I�ł́@�剤�����́u�J�i�q�i���Ձj�A�I�V�^�e�i�鉻�j�v�̓�l�̕���J��_�ЂƂ��Ắ@
���킢�����߂��܂��B��l�̑剤�̕��̕P���J��_�Ђł����B
�Ȃ��̂�����̑��̒���l�ƌ��������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
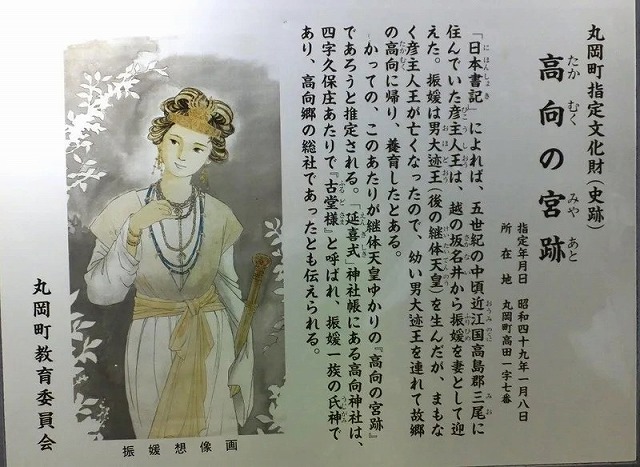
�����Đ����Ŕ����Ă܂����т�����A�U�P���I�z�h�N�Ə����Ă���܂��B
�܂����{���I�ɋ���Ɓ@�Ƃ������ӏ���������܂����B
�U�P���J��̂��@�����_�Ђ��Ɩ{�Œ��ׂė����̂Ɂ@����ł́@�U�P�����킢�����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�㓪������͌��̎O�����班���k��Ɓ@�����ƌ����ꏊ������܂��B�������h�䑍�{�Ƃ�
���~���������ꏊ�ł��B���̉��~�̐���Ɂ@�Õ��Q������܂����@���̌Õ����h��{�Ƃ�
�Õ��Q�Ł@���̒��̘Z�C���R1�������U�P�̕悾�Ƃ����Ă��܂��B���ɑ傫����ł��B
�܂������ȍc�@�ł͂Ȃ����ǁA�剤�̉��l�Ȃ̂ł�����@�Õ����傫���̂͂�����܂��ł��B
�����a����̍��͂��ւ����h�䑍�{�Ƃ̕P�ł�����܂����B
����ɂ��Ă��@���̐_�Ђ͂��킢�����߂��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̖�����➁i�����傤�j�����́@�����_�Ђ̋����ɂ���܂��B���̐_�Ђ̒����̑O�ɗ������Ƃ�
�s���Ɨ��܂����B�����Ƃ͕F���̂��Ƃł͂Ȃ����ƁB�܂肱�̐_�Ђ͕F���̌N�ɕt���Ă����C�Y������
�h�䑍�{�Ƃ̌Õ�������`���ɗ����C�Y�����i�o�_�x�ƂƑh��ł́@���݂��̌Õ�����
�Z�p�҂��@���݂��ɔh���������đ���܂����j�����Ă��_�ЂƎv���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
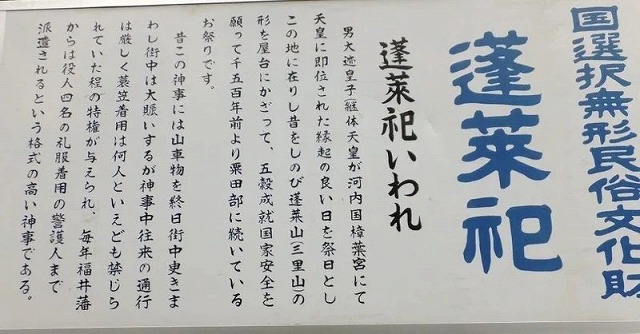
���̐_�Ђ̐_���u�H���J�[���炢���v�̐������ł��B��͂�I�z�h�剤�܂�
�F���̌N���J���Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̈ē��}������ƃC�Y���̍��̏k�}�Ȃ̂�������܂��B���������ɏo�_�̒n��������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Ђ̔q�a�����h�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����_�Ђ̖{�a�ł��B�c�O�Ȃ����Б���ł͂���܂���ł����B
�����ė��h�ȑ���̖{�a�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ���o�_�Ђł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Ă����炪�@�����䗅�_�Ђł��B
����͂������@������ɗH�E�Q���ꂽ�o�_���Ƃ̑攪��剤���疵���i�L�I�ł͑卑���
�����������܂����j���J��_�ЂŁA�]��̋����䗅�{�ɂ͂��̋����ɔ��ےÕP���J����ےÕP�_�Ђ�����܂��B
�卑��Ƃقړ����ɗH�E�Q���ꂽ�攪�㕛���̎����܂蔪�d�g�Ðg���J��
���߁@�x�Ƃ����Ă����ې_�Ёi���]�s���ۊ֒��ɂ���S���̌b����_�Ђ̑��{�Ёj�ŁA
���̔��d�g�Ðg���J��_�Ђ̛ޏ��Ƃ��ĉ߂����������̍c���̔��ې{�{���P
���J���Ă��܂��B
�܂�����䗅�_�Ђ̓C�Y�����̐_�ЂȂ̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s�̔��ې_�Ђ̐_�傩��q�a���݂��Ƃ���ł��B���d�g�Ðg�́@�L�I�Ŏ����Ə�����
���̂����Ɂ@�b�������Ƃ��Ă��悤�ɂȂ�܂��B
�����ł��̔��ې_�Ђ͑S���̌b����_�Ђ̑��{�ЂƂȂ�܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
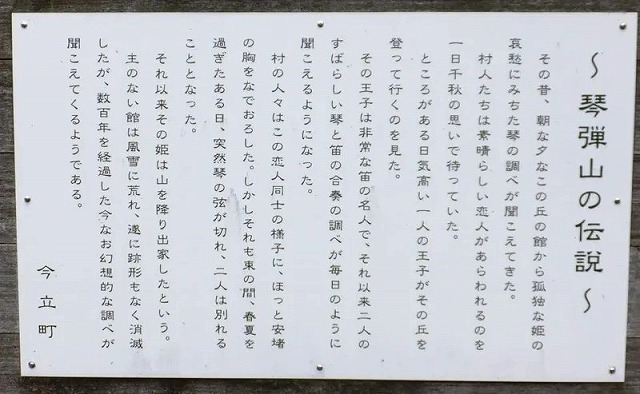
�܂����̉����_�Ћ����ɂ͋Ւe�R������܂��B�������{�Ƃ̋Ւe�R�͏o�_�ɂ���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
.jpg)
���̎ʐ^�͓��������o�_���̋Ւe�R�i1180���j�̎R���Ɍ��Ă�ꂽ�Ւe�_�Ђł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�ƌ������Ƃʼn����_�Ђ͏o�_���̌��Ă��@�F���̌N���J��_�Ђƌ����̂��ǂ�������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
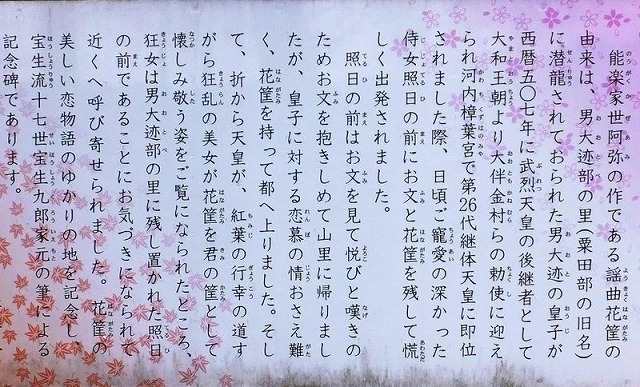
���Ȃ݂Ɂ@�����_�Ђ𒆐S�Ƃ������̂�����̎R�Ɂ@����A���ĉ�➌����Ƃ��Đ�������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ñ�o�_�����g�b�v�y�[�W�͂����炩�ɖ߂�܂��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
63-1�@��B�@���Ƃ̍��J�̏�@���m����NHK�e���r���f����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂Ƃ�ł��Ȃ��f�^�������e�ɂ�����ʂĂ܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2017�N11��1��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���m���́@��ʐl�͍s�������Ă��㗤�ł��܂���̂Ł@�e���r�ł݂邵������܂���B
�����Ő���m�g�j�̔ԑg�ŏЉ�Ă���̂����Ă�����A�Ƃ�ł��Ȃ��������e�Ȃ̂�
�т�����V���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���m���̉f���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
1.�@���Ƃ͊C�̖��ł���B
2.��w�p�����ŎO�p���_�b�������@���ꂽ�B���̎O�p���_�b���͑�a�������V�i�����������̂Ȃ̂Ł@
�@��a���������̓��Ł@���ƓI�ȍ��J���s����
3�܂��w�p�����Ł@�����ɓS�̔��������ꂽ�B�@�����͓S�����߂ā@���N�����֏o�������C�̖��ł���B
�ȏ�O���ԑg�œ��X�ƌ����Ă����@�Ƃ�ł��Ȃ��f�^�����̑�\�ł��B
���ɂ��o�L�ڂ���R����܂����������ł͏ȗ����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
1.�@�����ɂ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��������i815�N�j�ɏo�����u�V����^�v�ɂ́u�@�`�̌N�͑卑��Z������c�Ћ��̎q���ł���v�Ə�����Ă��܂��B
�܂�Ñ�o�_���Ƒ�Z��剤�i��E���喼�����j�b�Ö�i�o�_�ł͍��������ƌĂ��j�̑��̌�c�Ћ��i�����������j
����B�֍s���@�N�������̂��@���Ƃł��B
�܂�@�����͓����a���ŏ��̉����o�_���Ƃ̗R�������������Ȃ̂ł���B�����ĊC�̖��Ȃǂł͂���܂���B
�I���O3���I���ɐΌ��̌\�ҊC�݂ɑ吨�̐`���l�C����A��ď㗤���A���̌��U�`�ɋA�����Ďn�c�邩��
�X�Ȃ鎑���ƊC����Ⴂ�@����̕��t�̒n�ɓ�x�ڂ̏㗤�����`���l�̓����t�̏����B
�ނ��A��Ă����吨�̐`���l�����́@�L�͈͂ɍL����@������D���ƂȂ�܂����B
��ʓI�Ɂ@�C�̖��Ƃ́@�������A��Ă����`���l�C���̖���B�ł���A�@���Ƃ͏o�_���Ƃ̌������������Ȃ̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
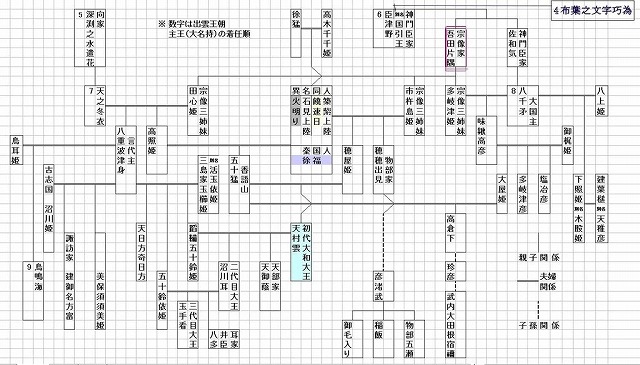
�@���Ƃ̎n�܂�Ɓ@�o�_���Ƃ̌n�}�ł��B�u�V����^�v�ɏ����ꂽ�̂Ƃ͏����Ⴂ�@���m�ɂ�
�卑��Z���̑��ł͂Ȃ��A��Z��喼�����i�剤�̂��ƂŁ@�L�I�ł����卑��Ƃ͑攪��喼�����̔��疵�̂��Ƃł��B�j
�b�Ö�̍c�q�i���j�j�Ȃ̂ł��B
�����ď@���Ƃ̎O�o���Ƃ��̍c�q�A�c���������@�Ñ�j��傫���������̂ł��B
���\�͍֖؉_�W���́u�Î��L�̕ҏW���v�A�u�C�Y���ƃ��}�g�̏��v���̖{��莄���쐬���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
2.�O�p���_�b��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
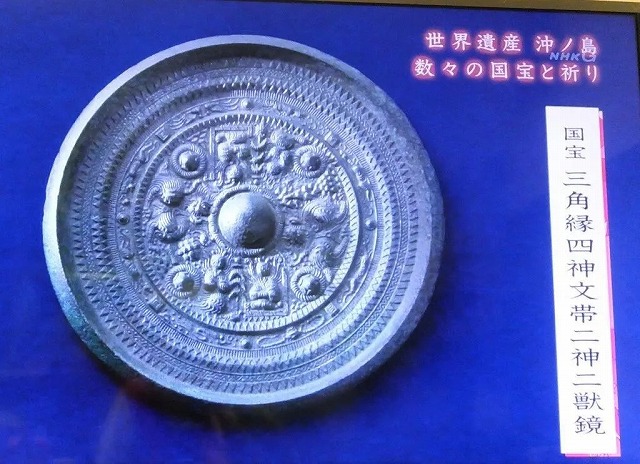
���ꂪ�o�y�����O�p���_�b���������ł��B
�m�g�j�̔ԑg�ł́@���j�w�҂̂��[����u�O�p���_�b���́@�a�����x�߂����������̂Ȃ̂Ł@���̓��Ł@
��a�������C���ʂ̈��S���肢�@���J���s�����v�Ɓ@�Ƃ�ł��Ȃ����������o�����B
���������@�O�p���_�b���́@��a���������ڎx�߂���Ⴂ�A��a���������������Ă��Ȃ��������̂悤�ɕ������܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�m���ɘa����鰂���_�b�������Ă��܂��B
�����a���ɂ́@�������̍����������Ă��ā@���ꂼ�ꂪ鰂ɒ������Ă��܂����B�����̘a�̑卑�́@�o�_�����A
��a�̈�鉤���A�����ē����̓s�ݍ��܂蕨���F���A�������ł��B
鰏��ɓo�ꂷ���Ԗڂ̕P�c���i�q�~�R�Ə����ꂽ�j�̓��}�g�̃����\�P�Łu���̏��������Ƙa���ɕ��a���K�ꂽ�v
�Ə�����܂����B��Ԗڂ̕P�c���͓s�ݍ��̃C��G���S���㏗���ƂȂ����u�F���L�ʕP�v�ł��B
����240�N��鰂ւ̒����g�ߒc���A������Ƃ��Ɂ@鰗̑ѕ��S�����l�e�C�V�������ɓs�ɕt���Ă��܂����B
���}�g���̏����ƌ����q�~�R�ɐe鰘a���̋���Əُ��A�ёсA�����i�ژ^�ڎ�n���ׂł��B
���̃��}�g���̏������Ƃ����L�ʕP�͑�a���痈���ӂ�����ēs�ݍ�����o�����Ă����A�e�C�V�������璼�ڌ���
���ёт������Ă��炢�܂����B���������q�~�R�͍��E�Ɂ@�g�ߒc�̓c���Ԏ�i�C�؉��q�q�{�R�̎q���j�╨���\�獪
�ɐёт����ɂ��������ā@�傢�ɈЌ����������Ə�����܂����B��l�Ƃ�鰂̊��ʁu���N���v��^������
�ёт������Ă�������ł��B���̎��_�ł̓C�N�����͂܂����̊��ʂ������Ă��܂���ł����B��Ɏg�ߒc�Ƃ���
�a�̑�N������鰂ɏo�����ā@���N���̊��ʂ�Ⴂ�܂����B
鰏��ł́@�C�N�������C�T�`�i�c���j�Ə����Ă��܂��B
�L�I�ł̓C�N���������ړ��F�\�������i�����߂���Ђ��������݂̂��Ɓj�Ə����Ă��܂����a���̑剤������鰂֒���
�ɍs�����Ƃ͏����Ă��܂���B
���a����鰂̑����ł�����������L�I�͈�ؐG��Ă��܂���B�x�߂̗��j���Ɏc���Ă���̂ɁB�������Ɏ������s�䓙��
�a����鰂̑����ɂȂ��Ă����̂�p���Ǝv�����̂ł��傤�B�@
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����ĉ����i�Ƃ��Đ_�b����100����������܂����B�������O�p���ł͂���܂���B
�x�ߑ嗤�ŏo�y���������͂��ׂĕ����̐_�b���ŁA�O�p���ł͂���܂���B
���Ƃ��Ǝx�߂ł́@�����̐_��v�z�Ɋ�Â��_�b��������ꂽ�͕̂����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��鉤��11��F����剤�̍��@�x�߂ł́@鰂ƌ����Η����Ă����B鰂̗ɓ����ʂɂ́@������������Ƃ���
�傫�ȗ͂������Ă����B�������͓Ɨ����悤�ƍl���Č��̑����Ɏg�҂𑗂����B������͌�������Ɨ�������
�������Ƃ����B������235�N�i��3�N�j�ɑ�ʂ̍���悵�A���̒��ɑ�R�̓����ޗ���H�l�������B
�����������m����鰂͌������ɂ������ā@�������A�����߁@���낢��D�������o�����炵���B
�Q�Ԃ����������́@鰂̎g�҂̎���͂˂�鰂ɑ������Ƃ����B
�Q�Ăӂ��߂������̎g�ߒc�̑D�́@�����o�������̂̂��������œ�j�����Ƃ����B�����x�ꂽ�H�l�B�͘a���ɖS������
�ŏ��͓����̑卑�s�ݍ��ɗ������A�q�~�R������鰂ƍ������J���ƕ����@����Ăč��x�̓��}�g�̈�鉤���֍s��
�������B���ꂪ�q�~�R��鰂��瓺����Ⴄ�O�̂��Ƃł��B
��鉤���͂����̓������x�z���̍����B�ɔz��܂����B���{���Ύs�A���s�{�|��S�A�R�����������Ȃǂ���o�y�����A
��3�N��Ԓ����N�̔N���̓����������������̘a�����̂��̂Ƃ����܂��B
�H�l�B���Z��ŋ������ꏊ�Ɂ@�u����蕔�_�Ёv�����Ă��܂����B
�ޗnj��c���{�s�ł��B
������蕔�_�Ђ̖K��L�́@���̃u���O�@45��2015�N12��26���ɍڂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
������x��鰂ւ̎g�ߒc�Ƃ��čs�����A�����h�H�͎������f����炿�̈����@�c���Ԏ�╨���\�獪���u���N���v��
���ʂƐёт������Ă���̂Ɂ@�����ɂ͉������炦�����̂ŕs���Ɏv���@�s�ݍ��𗣂�Ĉ�鉤���ɕt��
���Ƃ����߂܂��B
�����h�H�̍˔\�����ꂽ�����q�~�R���ƖL�ʕP���@�����̑��q�i�L�����F�j��C�N�������̂��Ȃ�Ȃ��悤�Ɏv���A
���ʂ�������悤��鰂ɓ��������Ȃ���������ł��B
�ȑO����e���������@���}�g��鉤���̓��q�����N�ɔ閧�ɗ��܂�Ă��������h�H�́@鰂̋A��Ɂ@��ʂ̓����ޗ��ƍH�l��
�ѕ��S�Ł@�d����ā@���}�g�֑���܂��B
����������a�̑剤�͐��R�i�����F���A�������̓s�ݍ��R�j�ɑΌ�����ׁ@鰋����傫�������ʂɍ��A
�x�z���̍����B�ɔz��܂��B�傫�������͊���₷���ׁ@�O�p���ɂ��ċ��x�𑝂����ƌ����Ă��܂��B
�O�p���_�b����300�ʈȏ����܂����B�܂���鉤�����x�����o���Ƃ̑��ΒÐg��100�ʈȏ���܂����B
�����͋ߋE�Ⓦ�C����400���ȏ�o�y���Ă��܂��B
���Ɉ�̌Õ������ʂ̎O�p���_�b�����o�y�����@���}�g�̍��ˌÕ��A���}�V���̒ֈ��ˎR�Õ��͂��ꂼ��
�F����剤�̕��e�̓��q���剤�Ɓ@�o���Ƃ̑��ΒÐg�̕悾�ƍl�����Ă��܂��B
�܂������h�H��100�ʈȏ��点�āA������鰂֎{�ݒc�Ƃ��Ă������L�O�Ƃ��Či���O�N�̔N�������܂����B
�����h�H������ꂽ�@�_��s�_���_�ЌÕ�����o�y�����@�i���O�N�̔N������O�p���_�b��������ł��B
���_���_�ЌÕ���q�˂��L���́@���̃u���O�u42�ԁA2015�N12��13���v�̐_���_�Ђ̋L���ɏ悹�Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����Љ�Ȋw�@�l�Êw�����������̉����ꂪ1984�N�ɂ킪���ɏ����ꂽ�V���|�W�E���Łu�O�p���_�b����
�a�����ł���B�����ł͂��̋��͈�ʂ��o�y���Ă��炸�@���̋��̊}�����͗l�͒����̂��̂ɂ͖����v�ƒf�����Ĉȗ�
���̋����ǂ������Ƃ����c�_�́@���������͂��Ȃ̂ɖ����Ɏx�ߐ����Ƃق����Ă���w�҂�����Ȃ�ā@�����ł��B
���Ȃ݂Ɋ}�����Ƃ́@���}�g��鉤�������R�i��B�����R�j�ɑR���đ������R���̖͗l�ł��B
�܂艫�m���̎O�p���_�b���́@��鉤�����̓o���Ƃ���@�����o�_���Ƃ̐e�ʋ̏@���Ƃ���ɓ��ꂽ���̂�
�v���܂��B�@���Ƃ��s�ݍ��̃q�~�R�������������ł��Ȃ��A�܂��đ�a�����̈��Ƃ����̓��ō��J��
�s�������̂ł�����܂���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
3.�S��ɂ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�a���̓S�̗��j�͌Â��B
�U�肾�炯�̓��{���I�̒��Ł@�u�����̔䔄�̖����@�^�^���C�X�Y�P�Ƃ����v�Ƃ�����Ă��܂��B
���܂ɂ͖{���̂��Ƃ��������Ƃ�����悤�ł��B���̏ꍇ�̎����Ƃ́@���������ɎE�Q���ꂽ�C�Y������
�攪�㏭�F�i�����j�̔��d�g�Ðg�̂��Ƃł��B
�I���O3���I���ɐΌ��̌\�ҊC�݂ɏ㗤���������Ƃ��̒����ȕ����̕���i���̏o�_��Ћ{�i�̑c��j��`��
����A��Ă����吨�̊C���B�ɂ��@�f�v�H����ĎE�Q���ꂽ�����i��E���͏��F�A�{���͔��d�g�Ðg�j
�ƎO���i���̑��{���Ύs�A�O���S���{���j����`���ꂳ�ꂽ���ʈ˂�P�Ƃ̊Ԃ̕P�N�̖��O���^�^���\��䔄
�ƌ����܂��B
�܂蓖�����ɏo�_�������Ő��S���@�^�^���ɂ��s���Ă������Ƃ��������킹�܂��B���Ȃ݂Ɍ\��i�C�X�Y�j
�Ƃ͌Ñ�C�Y���ł́@���S���Ӗ������Ƃ����Ă��܂��B
�܂��������Ȃ�c��Ղ���o�y�����S��́@�������j���������ك`�[�����@2003�N5���ɔ��\�������ł�
�`�l�r�����ɂ��N�㑪��ŁA�]���̖퐶����̎n�܂����500�N�k��@�S��͋I���O10���I�̂��̂�
���\����܂����B
����x�ߑ嗤�̍ŌÂ̓S��́@�u�����v�̏I��育��̈�Ղ��甭�@���ꂽ�S��ŋI���O9���I�Ƃ���Ă��܂��B
�܂�S��͎x�߂���`������̂ł͂Ȃ��A�o�_���Ƃɓ`���悤�Ɂ@�C���h����N�i�g�����A��Ă����Z�p�҂ɂ��
�C�Y���̍��S�ő���ꂽ���Z���傫���̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ñ�C���h�̃h���r�_�l���@�A�[���A�l�̐N���ɂ�艟���o����@��֓��ꂽ�W�c�����̃^�~�[���l�ł���A
�N�i�g���𒆐S�ɖk�֓���ăT�n���������z���ăV�x���A�̃u���A�[�g���獕���]�i�A���[���j���~��a����
����Ă����̂��C�Y�����Əo�_���Ƃł͓`�����Ă��܂��B�u�����[�g�̍אΊ�n��������k�C���ɓ`��������[�g�ł��B
���̂��߃^�~�[����Ɠ��{��ɂ͋��ʂ�����̂������Ƃ����Ă��܂��B�i���{��ƃ^�~�[����@���W���j
�^�^���Ƃ͌Ñ�h���r�_��Ō������R������Ӗ����邻���ł��B�����������u�J�l�v���������Ӗ�����h���r�_��ł���A
�Ñ�C�Y�������̍����̍K�̐_�O�_�̂����̃T���^�F�̃T���^�Ƃ́u�@�������v�ƌ����Ӗ��ł܂�q���h�D�[�̏ې_�A
�K�l�[�V���̂��ƂŁ@�o�_�k�R�@���R�i�͂Ȃ�������j���J���܂����B
�k�C��������{�C�`���ɓ쉺�����C�Y�����͓����������ӂɑ�ʂ̍��S�����ā@�����ɗ��������Ƃ����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
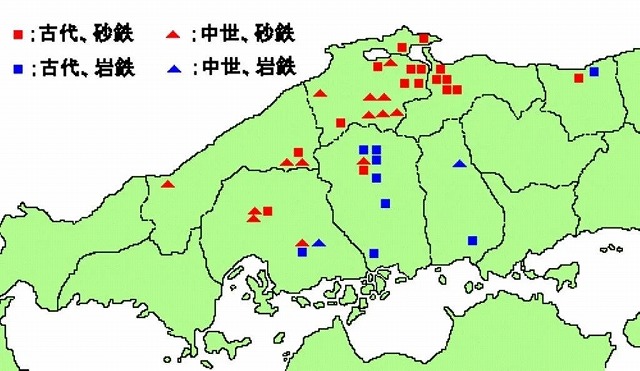
�^�^���ɋ��鐻�S�̈�Ղł��B�i���������z�[���y�[�W���j
�C�Y���ł͍��S��쓥��i�̂�����j�Ő��B����܂����B�A�i�̒�ɗ��܂����P���i�ˁj����̓E���K�C��
�Ă�闼�n�̏��������ꂽ�Ƃ����B
�쓥��̋߂��ɂ́@��b��ꂪ����ē��䂩��o���b�S�����M�E�Y�A���B����A���̋߂��̏��b���ōX�ɒE�Y
���ēS���i�������܂����B
���݁A�����R�n�̓��������o�_���œ����ۂ����炪�Č�����Ă��܂����A����͌��݂̓��{������錴���Ƃ��Ă�
�ʍ|���������邽�߂Ȃ̂ł��B
�܂���J�����m���ōs���Ă��������ɂ́@�a���œS�������Ă����Ƃ������Ƃł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�y�����S�̔ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
4.���̑��̏o�y�i�Ȃ�
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�o�y���������ł��B
�C�Y���������J�ɓ������g�p�����悤�ɁA��B�����Ƃ͓������V���{���ɂ��܂����B
�n���`���l�����̎��j���o���Ɏn�܂��B�����Ƃ͊e�n�̍����B�ɂ��̓�����z��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
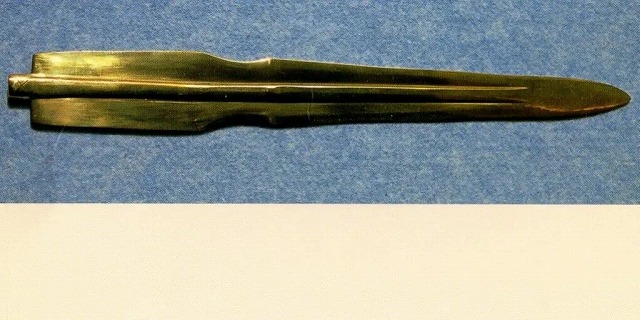
�o�_���Ƃ͐e�ʂ̏@���Ƃ�ʂ��Ă��̓�������肵�ā@������q���g�Ɂu�o�_�������v�����o�����Ƃ����Ă��܂��B
���ʐ^�͍֖؉_�B���u�o�_�Ƒ�a�̏��v�̃J�o�[�ʐ^�́u�C�Y���������v
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�C�Y�����̗��_�M��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���m������o�y�������������̓��̏��肩�u���ł��B
�C�Y�����͊C�̎L�i���j�ƌ������j��_�Ƃ��đ��h�������@�����ɗ��_�����@�M�����B�@���Ƃ��C�Y������
�Ȃ̂Ł@���R���_�M�������Ă����Ǝv���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s�K��_�Ђ̗��ł��B���̂͌�̖ɂ܂����Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���]�s��������_�Ђ̗��ł��B��������̂͌�̖Ɋ������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����M��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����ɃT�T�Q�������Ă���@���Ƃ̋M�l�̑z���}�������ł��B�i�m�g�j�e���r���j
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����ɑ���M���C�Y�����̓����ł��B���̃u���O�u�Ñ�o�_�����䂩��̒n��q�˂āv�ł��e�n�̋��₪
��_�̂ɂȂ��Ă���_�Ђ֏o�����Ă��܂��B
�������_��s�Ւe�_�ЁA�a�̎R���V�{�s�_�q�_�ЁA�O�d���F��s�Ԃ̌A�@���̂ق��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ƃ������Ƃ�
�Ƃ������Ƃ�
�Ƃ������Ƃ�
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ñ�C�Y���g�b�v�y�[�W�͂�������߂�܂��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�����̃u���O�͑匳�o�ł̖{���ׂĂ��Q�l�ɂ��Ă��܂��B�u���O�̖K��L�̋L���́@���̉��m���̋L���ȊO��
���ׂĎ������ڐq�˂Ē��ׂ܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�ł�HK�͈ȑO����@�f�^���������������M�p�ł��܂���B�����Ɠ��̈����A����
�ԑg���삵�Ă��邹���ł��傤�B
�ߕr�̉��Ƃ��Ɋ��t�Ƃ����ԑg�ł��@�n���ȏ��q�A�i���u�������̂悤�ɋ����R��
���{�ō���Łv�Ɣԑg���@5�炢����ł��܂����B
�����R�Ƃ������O�̎R�͂Ȃ��A�����R�n����x�A����x�A�N�o�x�A���_�x�̎l���Ƃ�
�ޗnj��䏊�s�ɂ���܂��B���{�ł͂���܂���B
�܂����̃j���[�X�ԑg�ł��u�ޗnj��̊���R�̗l�q�ł��v�ƌ����ĉf���o�����ꏊ��
���{�瑁�ԍ㑺�̑����ł��B�R���ɑ��Ɠޗǂ̌���������A�X�X�L���̑啔����
���{���Ƃ������Ƃ�n���ȏ��q�A�i���f�B���N�^�[���m��Ȃ��̂ł��B
�܂��̔ԑg�ł��A�Ȃ�Ƃ���X�ԂƂ����n���ȏ��q�A�i���@���s�̎���u�A�[�e�B�X�g�v
�Ȃ�ČĂԂ̂ł��܂�@���̃e���r�ł��@�̎���A�[�e�B�X�g�ƌĂԂ悤�ɂȂ��Ă��܂���
�A�[�e�B�X�g�Ƃ͌|�p�Ƃ��Ƃ������Ƃ��@�m��Ȃ��̂ł��ˁB
�|�p�Ƃ������Ƃ����܂�ɂ��y�X���������Ă��܂��ANHK�́B
�̎�ŃA�[�e�B�X�g�ƌĂׂ�̂́@���l�I�ɂ́u�G���t�C�b�c�W�F�����h�v�ʂ��Ǝv���Ă��܂���
�l�ɂ��Ⴄ�ł��傤���A���Ȃ��Ƃ��|�b�v�X�̎�≉�̉̎�͌|�p�Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�ŋ߂ł�HK�̗��j�ԑg�͌��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B�����畠���������Ȃ̂ŁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2017�N10��12��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���ɑ掵��剤�i��E���͑喼�����j�̐b�Ö�i���݂ʁj�̎����
�̓y���傫���L����A�b�Ö�́u���������v�Ƒ��h����܂����B
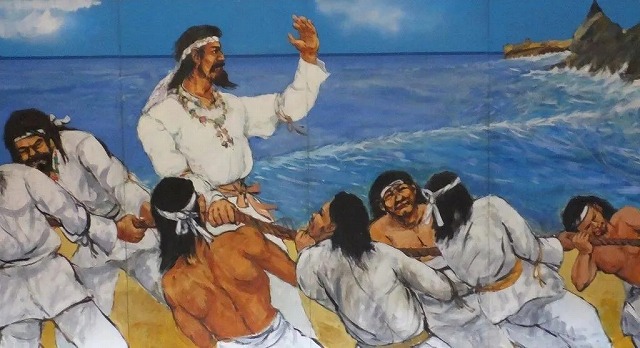
��̊G�́u�����i���ɂ��j�A�����i���ɂ��j�v�Ɛl�X���܂��ā@���y��������b�Ö쉤�ł��B
�i�b�Ö���J��@�o�_�s���l�_�Ёj
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�����͓��͉z�̍��i�攪�㕛���@���d�g�Ðg�Ɍ�`���ꂳ�ꂽ����P���z�̍��̕��ł��B�j���琼��
�@�������i�b�Ö쉤�̍c�q��c�Ћ����ڏZ���đ���܂����j�܂ōL�͈͂ł����B���R���ˁA��t�̍���
�o�_�����ł����B
�����̏o�_�����́@�e�n�͂Ő��������̂ł͂Ȃ��āA�����u�K�̐_�O�_�v�̐M��}�̂ɂ��Ċe�n�̍�����
���˂��@�����Ƃł����B
���̈�t�̍��̏o�_�����̖��c��q�˂܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����1�@�F���_�Ё@�����h�H���Z�ꏊ���N���̐_��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�L�I�ŕ����h�H�Ə����ꂽ�@�����b���c���i�����������̂��݁@�������ˁj�͂��Ƃ��ƕ��������F�������B
����232�N���@��B�������Ƃ̃C��G���i�L�I�ł͐��_�j����a�̈�鉤�Ƃ�|���ׂ��������J�n����
�Ƃ肠���������Ɂ@�s�݉����𗧂ĉF�����Ƃ̉F���L�ʕP�i鰏��ł̓q�~�R�Ƃ����ꂽ�j�Ɠs�݉F���A��������
�ł����Ăā@�����̏����Ɋ|����A�e�n���狌�����Ƃ̏d�����Ăъn�߂��B
�I�̍��ɂ����@�����F�z�s�������q�̕��������F�Ƌ��ɂ��������B�˔\���镐���F�̓C��G���ɂ��킢������
�����Ƃ̏d���̏̍��u�h�H�i�����ˁj�v��Ⴄ�B���̂Ƃ����畐���h�H�Ƃ𖼏��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�������F���L�ʕP�̓C��G���̍c�q�C�N���i�L�I�ł͐��m�j��킪�q�L�F�i�L�I�ł͖L�L���F�j��蕐���h�H��
���p�������̂����ꂽ�B�@鰂։���������ɍs���������h�H�A�c���Ԏ�A�C�N���c�q�̂����@�n�����N�l�̎q���A�n��
�c���Ԏ��C�N�����i鰏��ł̓C�T�`�Ə����ꂽ�j��鰂��璆�N���Ƃ�����E��������Ă���̂Ɂ@�q�~�R���e����
���������Ȃ���������ɕ����h�H�́@�����̂܂܂������B
���]���������h�H�́@�����푈�̂��Ȃ��Ɂ@�C�N���R�𗠐�@��鉤�����ɕt���B��������鉤���R�̓C�N���R
�ɔj��ā@�Ō�̈�鉤�ƕF����剤�͖��̃q�o�X�P���C�N�����ɍ����o���ā@�~������t�����Ƃ��ā@�����h�H�Ƌ���
��t�̍��ɏZ�ށB���̎��_�ŃC�N�����́@�������ɑ�a�̑剤�ƂȂ�A�Ώ�_�ЂŎ������s���B
�����h�H�͂��̒n�ɕ�炵�Ă������@������q�o�X�c�@����u�C�N���剤�������h�H�Ɏh�q��������v�ƘA������
�ߕ���_���̎p�ɕς��ā@�����Ɂ@���o�_���Ƃ̌���Ƃɏ����𐿂��B����Ƃ͕����h�H���@�ӉF�̐X�ɏZ�܂킹��
���Ƃ̖����ł����ā@�o�_���Ƃ̏̍��@�u�b�v��^���@�����̐b���c���Ɩ����ӉF�̐X�Ő��U���I����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���̋��o�_���Ƃ������h�H�̖����~���������@��̘a���̗��j�ɑ傫�ȉe����^���܂��B
�����ѕP�i�����Ȃ����炵�ЂߋL�I�ł͐_���c�@�j�Ƌ��ɎO�ؐ����ɑ听�����ā@��N�ƂȂ����P�ÕF���₻�̌��
�z���^�剤�A�i�L�I�ł͉��_�j�A�I�I�T�U�L�剤�i�L�I�ł͐m���j�₻��ɑ���鰏��ɂ����a�̌܉��Ȃǂ̑剤��
�h��b�ƁA���Q�b�ƂȂǂ̍����ݏo���@�a���̗��j�����̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
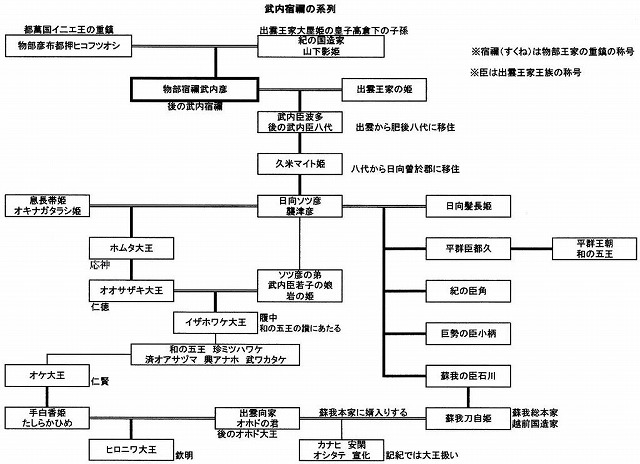
�����h�H�̌n��ł��B�a���̒��S�ƂȂ��B�X����l���̑c��ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�F���_�ЎQ�������ł��B��{�Ȃ̂ŋ��炭�����瓖����Ɉ�̒������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̌l�I�Ȋ��z�ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ꂪ���݂̈�̒����ł��B�͓̂�̒����������̂�������܂���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̓�̒����ł��B���̒��������ƒ����Βi�֑����܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����Βi��o���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Ȃɂ��傫�Ȑ��ꖋ���|�����Ă��܂����B�єN�ɂ��Ȃݒ���[���傤����Ɠǂނ̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�L�������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̑O�ɂ́@�䏊�Ɏ����ĉE�߂̋k�A���߂̍����A����Ă��܂����B�����h�H�����R�̑剤���y�o������
���Î����Ă���̂ł��傤�B���Ȃ݂ɍ��߂̍��͌͂ꂽ�̂��A���͎O�t�̑���̖������A����Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�Ƃ���ɑ����{�a�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�c�O�Ȃ���@�{�a�͑�Б���ł͂���܂���ł����B��������͏o�_���̏c�킬�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�̂��傤����̋e�̖���剤�̑c����Î����Ă���̂ł��傤�B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̒r�ƐԂ��[�̗R���͕s���ł����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a���狫���������Ƃ���ł��B���̉E��ɖʔ������̂�����̂Ō��ɍs���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
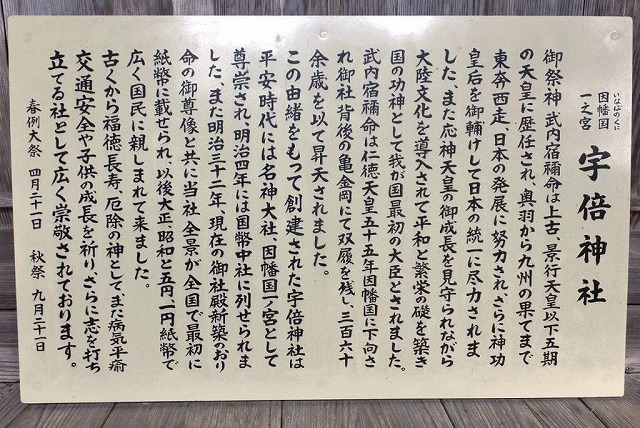
�F���_�Ђ̗R�������ł��B���b�̋L�I�̂Ƃ���ł��B�ܑ�̑�N�Ɏg���ė�360�Ł@���̐��֗��������Ƃ��A
���_�̐�������������Ƃ��A�f�^�����u���ɏ��Ă��܂��܂��ˁB360�܂Ő������l�Ԃ��Í���������̂ł��傤���B
���_�̕��e�͏P�ÕF�剤�ł��B�L�I�����������܂Ƃ��ȉR������̂ɁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�������班���u��o��Ƒo���ΐ���҂�����܂����B�����h�H���͂��Ă��������������ɒE���ł��̐��֗������������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
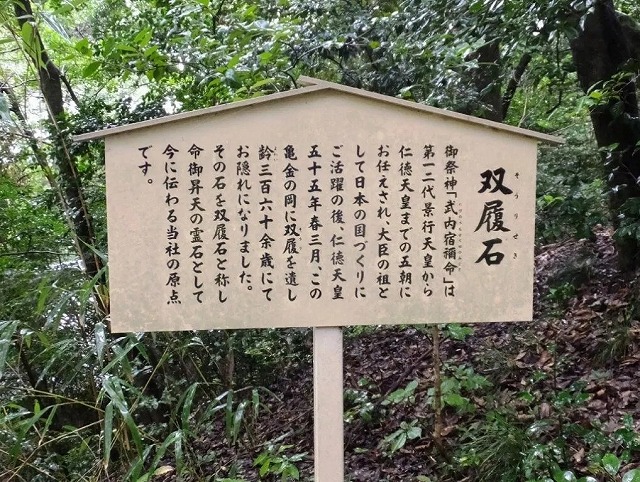
�����h�H�́@�C�N���剤���������h�q�̂��Ƃ��Ɓ@�}���ňߕ��Ƒ�����E���̂Ăā@�_���̎p�ɕϑ�����
�o�_�̌��Ƃ֓���܂����B���̑������ɂȂ��������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�_�Ђ̘e�̎R����i�ނƈɕ��g�������P�̕揊������Ƃ����̂ł����Ă݂܂����B
���܂��ܒʂ肩�������n���̕��ɓ����Ɓu������������Ă����Ƃ��悾���A���͕��u���ꂽ������
�L�h�S����|�������ǂ��@�l�Ԃ͒ʂ�Ȃ���B���̑�������v�ƌ����܂����B
�����i�݂܂��������܂�ɂ�������ԂŁ@�i�߂܂���ł����B
�ɕ��g���Ƃ͉F���_�Ђ̎ЉƂŁ@�o�_���Ƃ̐e�ʂŁA�����P�͕����V�c�ɍя��Ƃ��Ďd���]7�ʂ̊��ʂ����Ă�����
���ɏ����Ă��邻���ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���͈�t�_�Ђł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
61�@���o�_�����̂̈�t(����)�̍�������@����2�@��t�_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2017�N10��12��
����2�@��t�_�Ё@�����P�ÕF���O�ؐ����̐܂ɐ폟���F�O���Ă��̒n�Ɋ��𗧂Ă��̂��n�܂�Ƃ����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�O�ؐ����ɂ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�I�L�i�K�^���V�P(�����ѕP)�́@1���I�㔼�ɒ��N�����C����n�������C�̉��q�q�{�R�̎q���ł��B
�q�{�R�͍ŏ��o�_�����̒����n�ɏ㗤���悤�Ƃ������A�o�_�̖@������鎖�����ۂ������߁@�o�_����
�㗤�����ۂ���A�����N���Z�߂Ȃ������@�O�g�~�R��㗬�̎��n�тɏ㗤���@��J���ĊJ���Ƃ����B
�I�L�i�K�P�̓C�N���剤�̑��@���J�^���V�剤�̍@�ɂȂ�A��̑��薼�͐_���c�@�ł��B
���̂Ƃ��C���łѐV���ƂȂ�܂����B�I�L�i�K�P�c�@�͐V���ɑ��C�̍��Y�̕��^��v�����������ۂ���܂��B
�v�N�̃��J�^���V�剤�ɒ��N�o�������������邪���ۂ���܂����B���̂��ƃ��J�^���V�剤�͐펀����܂��B
�����ŃI�L�i�K�P�͓����̖L�O�̑卋���A�L�O���ÕF�ɑ��k����邪�@��������ۂ���ā@�����ÕF���펀���܂��B
�L�I�̓C�N���剤�Ɏn�܂镨���������O��ŏI����������B�����ߒ��ÕF��剤�Ɋi�グ���āu�����v�Ƃ��Ă��邪
�L�O���ÕF�͑剤�ł͂Ȃ��A�I�L�i�K�P�c�@�̕����Ł@�P�Ȃ�L�O�̍����̉��ł��B
���ɃI�L�i�K�P�c�@�͓����\�c�F�ɑ��k����ă\�c�F�́@���N�o������������܂��B
�\�c�F�剤�͏����a�剤�u�V�̑��_�剤�v�ٕ̈�퍂�q��(�������炶)�̎q���̕����h�I�̂Б���
�����b�\�c�F�Ƃ����@�����̉��ƂȂ��Ă����̂œ����P�ÕF�Ƃ��Ă�Ă��܂����B
���q���̕�P�͏o�_���Ƃ̑剮�P������\�c�F�剤�����R�o�_���Ƃ̌������������Ȃ̂Őb�𖼏���Ă���ꂽ�̂ł��B
�P�ÕF���͉ؗ�Ȑl�������ċI�ɉƁA�����ƁA�O�g�C���ƂȂǑS�����琅�R��g�D���ĎO�ؐ����̑��叫�ƂȂ�A
���N�����Ɍ���ꂽ�B
�C��ߐs�������삵���R�D�������V�����͐�킸���č~�������Ƃ����B���̌�S�ς��~���������Ƃ����B
�O�ؐ����ɑ听�������߂����ʁA�a���ɂ͒��N���甜��Ȑł������Ă���悤�ɂȂ�܂����B
�����ďP�ÕF���͑�a�ɊM�����@�剤�ƂȂ��܂����B
�܂��������������݂����悤�Ɍ����邽�߁A��B�����x���o���ɕa�������C�N���剤�̕��N�C�j�G����
��a�̑剤�Ɋi�グ���āu�~�}�����F�C�j�G�剤�v�Ƃł����グ�ā@�C�߂���C�j�G��������Ă������ɂ��Ă��܂��B
�������@�C�߂��ł����̂́@�\�c�F�剤�ƃI�L�i�K�P�̎O�ؐ������������������ƌ�̘b�Ȃ̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
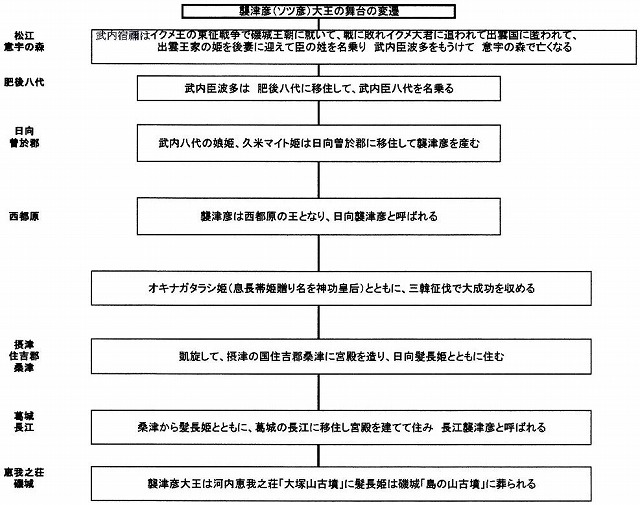
�P�ÕF�剤�̊�������̕ϑJ��]�c���̕����h�H����܂Ƃ߂܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�L�I�ł̓z���^�剤�͑����P�ƒ��ÕF�̎q���Ƃ��Ă��܂����A�z���^�c�q�����܂ꂽ�͎̂O�ؐ����̌�Ȃ̂�
���R�@�z���^�剤�̕��e�͏P�ÕF�剤�ł��B
���������ۂ̃z���^�c�q��7�ɂ��Ě�܂���܂����B�����P�͍���ʂĂ��܂����B�����p�������Ȃ���
�V�����N�v�̎x���������Ȃ��Ȃ�͖̂ڂɌ����Ă��邩��ł��B
�����Őe���̂�������і썑���Ƃ̒|�t���m�N������7�ƒm��@�閧���ɌĂъđ����Ƃ̍c�q�Ƃ��܂����B
�|�t���m�N�́@�F���L�ʕP�����@�L�F�i�L�I�ł͖L�L���F�Ə����ꂽ�j���C�N���剤�ɒǂ��ē��֓�����
�q���ł���B���̘b���ā@��Ԋ�̂��@�F�������{�ł���B
���Ƃ��ƉF�������{�́@�L�ʕP�i鰏��Ńq�~�R�Ə����ꂽ��ԍŏ��̕P�j���J���Ă������@���̒|�t���m�N�̘b����
�}篃z���^�剤�Ƃ��܂��Ƀz���^�剤�̕�e�Ƃ����@�����P���J��@���݂���Ր_ �͂��̂��O���ł��B
��ʓI�ɂ́@�F�������Ɖ��̊W�������@�z���^�剤�A�����P����Ր_ �ɐ����Ă���̂́@����ȈӖ����������̂ł��B
�����ā@�ł����グ�̗��j�����ł���@�L�I�́@�������������݂����悤�Ɍ����邽�߁A��B�����x���o����
�a�������C�j�G���i�C�N���剤�̕��N�j���a�̑剤�Ɋi�グ���āu�~�}�����F�C�j�G�剤�v�Ƃł����グ�ā@
�C�߂���C�j�G��������Ă������ɂ��Ă��܂��B
�������@�C�߂��ł����̂́@�\�c�F�剤�ƃI�L�i�K�P�̎O�ؐ������������������ƌ�̘b�Ȃ̂ł��B
�܂��s�䓙�⎝�������́A鰏��ɉ��x���o�ꂵ�Ă���u�q�~�R�v���������Ă��܂����A�ǂ���
�_���c�@���q�~�R�Ǝv�킹�悤�Ƃ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����h�H���U���ɉ����������Ă��܂���
�ނ�300�N�ȏ㒷���������ā@�����P�̎���܂Ŋ������̂́@���̕\�ꂾ�Ǝv���܂��B
���U���ł͕����h�H���ڎz�G�z�i�����������j�Ə����Ă��܂����Վz�G�z�i�����������j�̑Ղƍڂ̎ʂ��ԈႢ�Ǝv���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�܂��P�ÕF�剤�̒핐���b��q�̖����P�̓I�I�T�U�L�剤(�m��)�̍c�@�ƂȂ�A�C�U�z���P�剤�������݂ɂȂ����B
����œ����\�c�F���Ƃ������̂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��t�_�Ђɂ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�O�ؐ����̏������A�P�ÕF���͐e���̏Z�ދI�B�A�����͂������̎��A������O�g�A�n�ዷ�Ő��͂�����
����C���Ƃ̌��U�F�i���Ăӂ邭�܁j�h�H��������͂����t���ā@�����̋��D�R�D���W�߂܂����B
���̓r���@���̒n�ɗ�������t�R�̘[�ɂ�����T�ɂ���c��̕揊�ɂ��Q�肵�����Ɓ@���̒n�Ɋ��𗧂Ă�
�폟���F�����Ƃ����܂��B���ꂪ���̈�t�_�Ђ̂͂��܂�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

��t�_�Ђ̕\�Q���͕�����Â炭�ā@�ߊ��܂���ł����B�����ɂ͑傫�ȓ��H�������Ă��āA�ׂɂ͈�t���w�Z��
����A�����̒��ԏ�ɏ���ɎԂ��~�߂����Ă��炢�܂����B���߂�Ȃ����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����͔�r�I�L���A�ǂ���������Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�q�a�ł��B�ߏ��̕������l����Q�肳��Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�ł��B�c�O�Ȃ����Б���ł͂���܂���ł����B��������͏o�_���̒G�킬�Ȃ̂ň��S���܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�Ɣq�a�̊ԂɁ@�傫�Ȑ�����܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
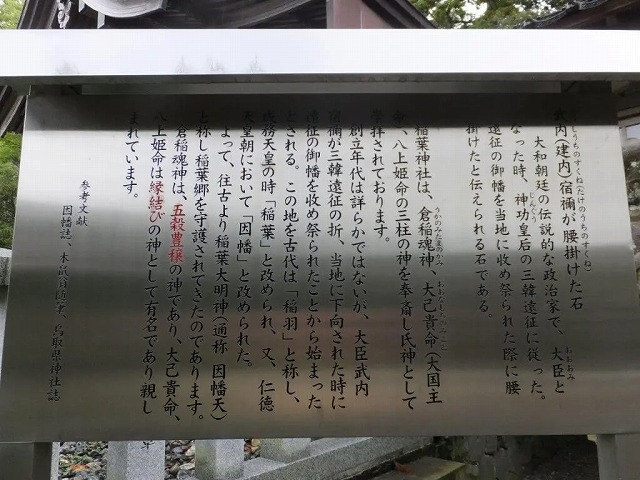
����������ǂނƁ@�Ȃ�ƕ����h�H���@�O�ؐ����̂Ƃ��ɂ��̒n�Ɋ����[���ā@�폟���F�肵���Ƃ��ɍ��|�������Ƃ���܂��B
�܂��ł����グ�̋L�I�̓��e�ɏ]���Ă���̂Ł@���傤���Ȃ��ł����@����ɂ��Ă��Ђǂ����܂��B
�����h�H�̑\���̏P�ÕF�̊������h�H�ƍ������ď�����Ă���̂́@�����o���܂���ˁB
���܂��ɕ����h�H�́@�����i�₵�Ⴒ�j�̃z���^�剤�ɂ��d�����Ə����Ă���̂Ő��S�N�����������ɂȂ�̂ł��B
���������܂Ƃ��ȉR����ׂ�Ηǂ��̂Ɂ@�L�I�̕ҏW�҂́B
�Ȃɂ��@�v�f�������Ă��������̂ł��傤�ˁB��҂̑����������o�_���Ƃ̌������������ł�����@��������Î�
�����������̂ł��傤�B�@
���炩�ȉR���������Ƃɂ��A���̏����͐M�p�ł��Ȃ���Ɓ@�s�䓙��ɓ����Œm�点���������̂�������܂���B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ͕ς�������̂�����܂����B�Ñ�o�_�́@�����̌��^�ł��B��{�̊ۑ��𗧂Ăā@���̊Ԃɒ��A���n�����̂ł��B
�₪�čK�̐_�O�_�M������ɂȂ�Ɓ@�O�����ɕω����܂��B
���@�O�����́@�o�_�s���l�_�Ђ�ޗnj��N��s�w���_�ЂɌ������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���͔��e�_�Ђł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
60�@�@���o�_�����̂̈�t(����)�̍�������@����3�@���e�_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2017�N10��12��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����3�@���e�_��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���e�_�Ђ́@��B�����R�̑�a�ւ̓������C�N�����{�̂����˓��C�𓌐i���ċg�������ƌ�����J��L���Ă����Ƃ���
�ʓ����́@���{�C��k�㓌�i���ā@�o�_����������̖��~�������āA�X�ɓ��i����r���A��t�̍��̕����
���炭�؍݂����B���̑O�i��n�̐Ղ��@�F���ЂƂȂ�A�X�ɔ��e�_�ЂƖ���ς����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�܂��@�Ñ�o�_�����̉����ɕt����
�Ñ�o�_�����͓��Ɛ��̓�̉��Ƃ��������B���́u�_��b�Ɓv�œ��́u���Ɓv�ł��ꂼ����݂Ɂ@�剤
�i��E���͑喼���@�����Ȃ����j�ƕ����i��E���͏��F�@�����ȂЂ��j���o���Ă��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��B�}�㕽��ɘa���ւQ�x�ڂ̏㗤�������`���l�����i�L�I�ł͑f���j�j�̎q�����ł����Ă��u�������Ɓv�͐���232�N��
�C�j�G���i�L�I�ł͐��_�ƕ\�L�j�͑�Q�����������ӂ��쉺���n�߂܂����B
�����ē����̒n�Ɂu�s���i�܁j�����v�����@�F���̖L��������L�ʕP���}���u�s���L�A�������v��������B
�c�q�̃C�N���͐��˓��C�𓌐i���@�g���ŋg�������̌�������R���Ă��܂����B
�ʓ����̏������i�����������[��a�̓o���Ƃ̕��Ɓj�Ɠp�㉤�i���̂��݂����[�F���Ɓj�����{�C�𓌐i����
���o�_���Ƃ��}�P�����B��17��喼�����́u�R��щ��i��܂������炵�j�v�͓����q��{�{�a�i�o�_�s�_�咬�j�ɋ������@
�Q�Ăӂ��߂��Ĕw��̎R�ɓ������B�����ɐV�{�����ā@��R�������₪�č~�����܂����B
���̐V�{�ōu�a�����@�����R�����o�_�ɒ������邱�ƂƂȂ����B�V�{�͌�X�܂Łi�]�ˎ��㍠�܂Łj��
�u�a�]��i��͂���j�̋{�v�ƌĂꂽ���A���݂́u�v�ގq�_�Ёv�ƂȂ��Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
����@�s���L�A�������̕ʓ��������{�C��i�݁@���o�_���Ƃ��}�P�����B
����W�O�N���ɓn���������N�l�i�C�̉��q�j�q�{�R�̎q���@�c���Ԏ�i�����܂���j�����o�_���Ɓi��17�㏭�F�@�쌩�F�j
�̋{�a�̓c�a�R�_�a�i���]�s�c�a�R���j���P���j���B�c���Ԏ�͒����ɓ��{�C�𓌐i�����@���ɑ�a���肵�Ă���
�s���L�A�������@�C�N�����ƍ�������B
���̌㕐�����i�������낸�݁j�����镨���R�����˂̍�����S�����ʂɐN�������o�_���Ƃ��~������B
�쌩�F�͋{�a���R�ɖ����n���A���Ƃ͔��_�Ɉڂ�B�i���R�̑叫���@�����̏\�獪�ł��B
�����R�͋{�a�̌����ɒ������@���ꂪ���̏��]�s�u�_��(�J���X)�_�Ёv�ł���A���Ƃ̏Z�܂������̏��]�s�u�F���Ёv�ł���B
�ƌ������Ƃő�17��喼�����u�R��^���V���v�A���F�u�쌩�F�v�ŌÑ�o�_�����͏I���ƂȂ�B
���c�a�R�_�a�Ղ́@�������Ƃ��ā@��������A�N�ł����w�ł��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���e�_�ЂƓe�_�ɂ���
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��t�̍�����ɂ��炭�؍݂����p�㉤�͖L�����F���Ƃ̌�q����������@�F���̓e�_�i���_�j��M���Ă����B
���̒��ɓe������̂Ł@�u���ǂ݂̐_�v��e�_�Ƃ��̂����B
�������_�{�́u���v���ȗ������������u�F���_�{�v�ɂȂ����ƉF���_�{�ЉƂ̓`���ɂ��邻���ł��B
�����ĉF�����Ƃ̐l�͖��O�ɓp�̎�������̂��@�d����ł����B�p�㉤�i���̂��݂����j�����̗�ł��B
�L���R�̈ꕔ�͕���̐�̌R�Ƃ��Ďc��A�����ɉF���Ђ����Ă��B�Ր_�͌��_�i�e�_�j�ƖL�ʕP�ł���B
���C��G�����s�݉����̐��s���ŕa��������@�����R�ō��w���҂Ƃ��Ċ撣�����F���L�ʕP�������r�����|�̋{����
�a�C�ɂȂ肻�̒n�ŕa�����܂��B��͉̂F���ɉ^��ĉF���_�{���J���܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
������Ƃ��Ɓ@��t�ׁ̗A���˂̍��̒��R�ɓe�̘b���������B��̗��ɏ�����e���C�ɗ����ꂽ�b�ł��B
�܂����������R����a�i�����@��a����ǂ��o������a����́@��鉤���şN��s�a玁i��Ɂj�ɂ���܂����B
�����ČÑ�o�_�����ł́@���_�M������ł������A���j�i�L�̂��Ɓj��������ā@�_�Ƃ��Đ��߂��Ă��܂����B
��t�̕���ɏZ�L���n�̐l�X�́@�a玉�����o�_�l�����h���郏�j�ɑR�S��R�₵�āA���˂̖��b��
���ς��ā@���j���e�ɊQ��^���鈫�҂ɂ��āA���e�_���卑����̂��Ƃ����b�ɂ��܂����B
�����̘a���ɂ́@�����e�͑��݂��܂���ł������u��t�̔��f�i�͂����j�E�T�M�v�̘b�ɍ��ς��܂����B
�����ĉF���Ђ𔒓e�_�Ђɖ��O��ς��܂����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�L�I�̍��b�ł́A�卑��͌Z�B�Ɣ���P�Ƀv���|�[�Y���ɂ��̒n��ʂ肩�������Ƃ����B�����Ĉ����L�ɔ��
�����ꂽ�E�T�M�������A���̃E�T�M�́@�卑��Ɂu�Z�B�͔���P�邱�Ƃ͏o���Ȃ����낤�B�Z�����̉ו���
�w�������@���O���䔄��ł��낤�B�v�Ɛ�����Ƃ����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�I���O2���I���́@�����a���B��ő�̉����@�o�_�����̑攪��剤�@���疵���ɂ͌Z�͋��܂���B
�܂��ē����̉����l�̉ו���w�����ė�����Ȃǂ��肦�܂���B�����Ĉ�n�������̖��u��t�̔���P�v��
�킴�킴�v���|�[�Y�ɂ͗��܂���B���ɂ͉��l���@�����ā@�n���������������Ė������ɍ����o���Ă���
�ł��B��t�̃n�_�J�E�T�M�̘b�́@���ɏo�_�ɓG���S������Ă����z�炪������b���ƒ���������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���݂̔��e�_��
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���e�_�Ј�̒����ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���������ƒ����Βi��o��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Βi�̍��E�ɂ́@�E�T�M�̒u��������܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�Βi�̏�̏����ɂ͍���������܂��B
�卑�傪����P�Ƀv���|�[�Y���Ă���悤�Ɍ����Ă�����E�T�M��������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����̃C�`���E�͐F�Â��n�߂Ă��܂��B�n�[�g�^�̊G�n�͗������A�̋F��̂悤�ł��B�ǂ�ł͂��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���h�Ȓ��A��̉�����q�a�ł��B���h�Ȓ��A��͏o�_���̂܂˂����Ă��܂��B�L���l�͓e�_��M���Ă��邭����
�o�_�l�̐M���间�_��^�����Ă��܂��B���̒��A��́@�q����s���߂ł�����ւ������Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���̔q�a�̉����̔���͉F�������{�̉����̔���Ɏ������Ƃ����Ă��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�Ɛ�́@�o�_���̒G�킬�Ƒ�Б��Ɍ����܂��B��������̂͂��@�F�����Ƃ͂��Ƃ��Əo�_������Z��
�剤�ō��������̐b�Ö�̎��j��c�Ћ�����B�ֈڏZ���Ďn�܂����@���Ƃ����ɂȂ��Ă��܂�����B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�����ɂ���u�s���s���v�̒r�ł��B����ꂽ�E�T�M�����̒r�ő̂����������ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�̒��̊�b�͋e�̉Ԃ̖�͂��@�荞��ł���܂��B���̂��킩��܂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
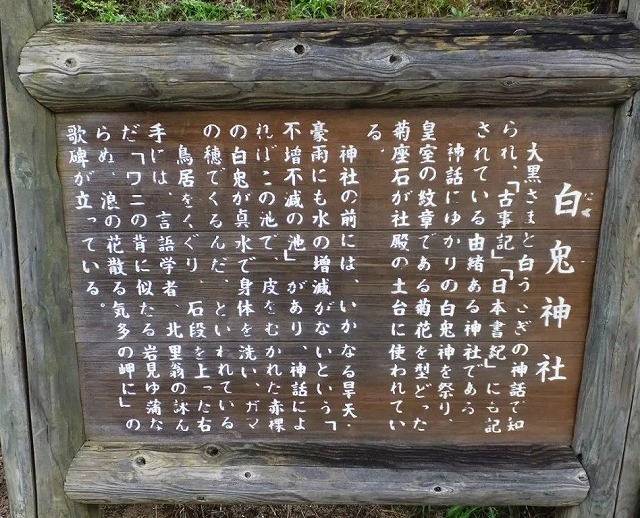
�_�Ђ̗R���Ŕł��B�Î��L�̐_�b�̘b���������Ă܂���B�p�㉤���F���L�ʕP���S���o�Ă��܂���B
��B�������Ƃ̂��Ƃ��@�����ŏo�_������|�������Ƃ��@���珑���܂����Ȃ��B
��a�����͓V����~��Ă����l�Ɏn�܂�@������n�炵������A����Ȃ��Ə������炽���܂����߂ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�{�a�ɕt���Ă���_��͉����̂ŗǂ������܂��@�T�b���ԕH�̂悤�ł��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

������́@���̏o�_��Ёi�卑�傱�Ɣ��疵�����J��j��o�_�s���{��_�Ёi�����₻�̕������
�[���̏o�_��Ћ{�i�̑c�悽���ɗH�E�Q���ꂽ���疵���̌�q�������F���J��j�̐_��œ�d�T�b���ԕH��ł��B
�o�_�����������g�p�ł������@�Ȃ�ƃE�T�M���g���Ă��܂��B�푈�ɏ��ĂΖL���l����肽������ł��ˁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���e�_�Ј�̒����̑O�ɂ́@�Ȃ�Ɓu���l�B�̐��n�v�̊ŔƓɂ��B���e�_�Ђ��Ȃ��Ȃ��q�W�߂̏�����肾���ƁB
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�Ñ�o�_�����g�b�v�y�[�W�͂�����ł��B
http://yochanh.sakura.ne.jp/kodaiizumo/index.html
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[